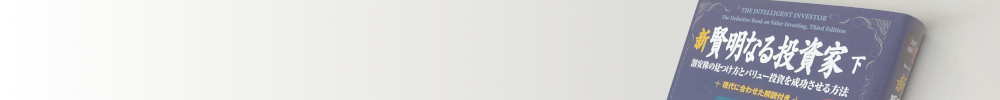
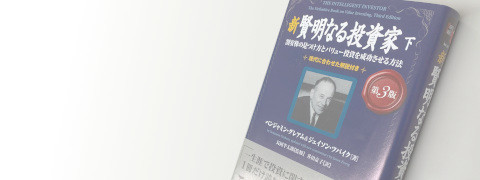
グレアム・ドッド村のスーパー投資家たち
ウォーレン・バフェット
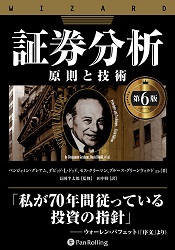
この文章は、ベンジャミン・グレアムとデビッド・L・ドッドの共著による『証券分析』(パンローリング)の出版50周年を記念して、1984年にコロンビア大学でウォーレン・バフェット氏が講演した内容を書き起こし、編集したものである。『証券分析』は、その後『賢明なる投資家』によって投資家に広く知られるようになった投資概念を、初めて世に紹介した本である。バフェットのスピーチは、グレアムのバリュー投資法を実践することによって、彼の門下生たちが株式市場で驚異的な成功を収めてきたことを示す非常に興味深い内容になっている。
「株価に対して大きな安全域を有する価値がある銘柄を探す」というグレアムとドッドの安全性分析(security analysis)の手法は、今や時代遅れなのでしょうか。この問いかけに対して、今日、投資のテキストを執筆している学者の多くが「イエス」と答えるでしょう。
彼らは、市場は効率的なので、株価は企業の将来の展望や経済の状況といった周知の情報をすべて反映していると主張しているからです。彼らは、頭脳明晰な証券アナリストたちが、入手可能なすべての情報に基づいて、常に株価の適正水準を割り出しているので、過小評価された株式など存在しないと言います。
また、毎年、市場に打ち勝っているように見える投資家は、単にラッキーだっただけだとも言っています。ある投資テキストの執筆者は、「株価が入手可能な情報をすべて反映しているならば、投資で熟練するなどということはあり得ない」とも言っています。
確かにそうかもしれません。しかし、私はみなさんに、毎年S&P500を上回るパフォーマンスを上げている人たちの話をしたいと思います。(中略)
投資の世界におけるコイン投げの勝者が、偶然では到底説明できないほど「グレアム・ドッド村」という名の小さな知性の村の出身者に偏っていることにあるときみんなは気づくでしょう。
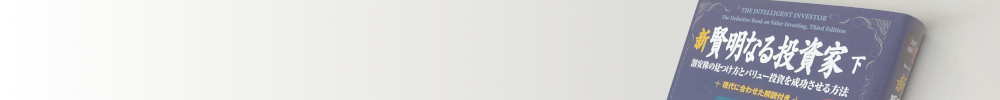
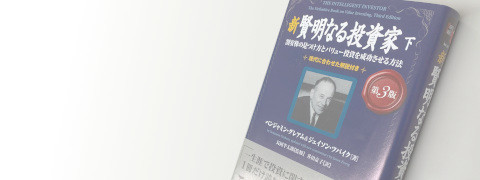
株券ではなく企業を買う
これからお話しする投資の成功者たちには、知的な家長がいます。
それがベンジャミン・グレアムです。

グレアム・ドッド村出身の投資家たちに共通する知的テーマは、ある企業の価値と、その企業の小さな一部分に付けられた市場価格との不一致を探すことです。彼らは、本質的にその格差を利用して利益を得ており、効率的市場仮説(EMH)理論の支持者たちのように買うのが月曜日か木曜日か、あるいは1月か7月かなどとは考えていません。
ちなみに、多くの実業家が企業を買収するとき(実は投資家が市場を通じて株を買うのと同じこと)、それが月曜日でも金曜日でも関係ありません。それなのに、学者たちはなぜ企業の一部分である株を買うときには多大な時間と労力をつぎ込んで買いのタイミングの違いを調べようとするのか私には理解ができません。
グレアム・ドッド村の投資家たちは、もちろんベータ値やCAPM(資本資産評価モデル)やリターンの共分散などは検討していません。そういったことには関心がないからです。実際、彼らの多くはその意味すら正確には理解していないでしょう。彼らが重視するのは2つの変数、つまり価格と価値だけです。
株価と出来事の動向などといったチャート分析に関して、あまりにも多くの研究がなされていることに私はいつも驚いています。先週や先々週に株価が大幅に上昇したという理由で企業を買うなどということが想像できるでしょうか。
株価と出来高などといった変数を用いた研究がなされている背景には、今日のコンピューターの時代において、無数のデータがあるからです。こうした研究が行われるのは、必ずしもそれが有用だからではなく、ただそこにデータがあり、学者たちがそのデータを操作するための数学的技術を習得するために懸命に努力してきたからです。このような技術を身につけると、たとえ有用でなくても、むしろ有害であっても、技術を活用しないことが罪のように思えてきます。友人の言葉を借りれば、「ハンマーを手にした人には、すべてが釘に見える」ということです。
私は、この共通の知性の家を持つ集団は、研究する価値があると思っています。ついでに言えば、株価、出来高、季節性、時価総額などの変数が株のパフォーマンスに与える影響についてはさまざまな学術的研究が行われているのに、勝者が異常に集中するバリュー投資の手法に関する研究にはまったく関心が示されていません。(中略)
グレアム・ドッド村出身の9人の投資家たちは、投資のスタイルが大きく異なっていますが、常に株券ではなく企業を買うという姿勢で一致しています。
時には企業全体を買う人もいますが、ほとんどの場合はみんなその一部を買っています。 ただ、全体を買うときも、ごく一部を買うときも、常に同じ姿勢で取り組んでいます。幅広く分散する人もいれば、ごく少数の銘柄しか保有しない人もいますが、全員が市場価値と内在価値の差を利用して利益を得ています。
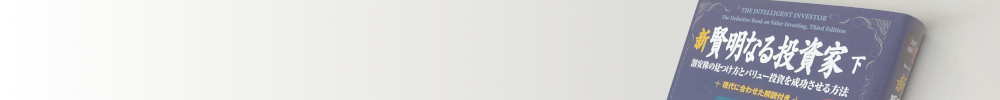
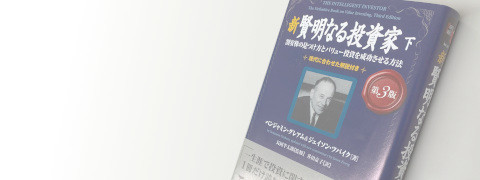
高リターンほど低リスク
私は、市場は効率的ではないときがよくあると思っています。だからこそ、グレアム・ドッド村の投資家たちは、価格と価値の差を利用して利益を上げることに成功しています。株価がウォール街の「大衆」に影響され、最も感情的な人や最も強欲な人や最も落ち込んでいる人たちによって決まっているならば、常に理性的な価格が付いているとは到底思えません。実際、市場では無意味な価格が付いていることがよくあります。
リスクとリワードについて、重要なことがあります。リスクとリワードは、明らかに相関している場合もあります。
例えば、だれかが私にこう言ってきたとします。「この6連発銃にひとつだけ弾が込めてある。これを回転させて一度だけ引き金を引き、生き延びたら100万ドルをあげますよ」。
私はこの申し出を、100万ドルでは安すぎると言って辞退します。すると彼は、「それならば、二度引き金を引き、生き延びたら500万ドルでどうかな」と言ってきました。
これこそ、リスクとリワードが明らかに相関しているケースです。
バリュー投資では、これと正反対のことが言えます。1ドル札を40セントで買うほうが、60セントで買うよりもリスクは低くなりますが、報酬に対する期待は前者のほうが高くなります。バリュー投資のポートフォリオでは、リターンを得られる可能性が高いほど、それに伴うリスクは低くなります。
簡単な例を挙げましょう。1973年に、ワシントン・ポストの時価総額が8000万ドルになったことがありました。しかし、その日のその瞬間に、もし買い手が10人いたら、そのだれにでも同社の資産を4億ドルか、それをはるかに上回る金額で売却できたでしょう。同社は、ワシントン・ポストやニューズウィーク以外にも、大都市で7つのテレビ局を所有していました。これらの資産の現在の価値は20億ドルですから、当時4億ドルでだれかが買っていたとしても、まったくおかしくはありません。
ところで、もしワシントン・ポストの時価総額がさらに下落して8000万ドルではなく4000万ドルまで落ち込んだとすれば、それに関するベータ値はさらに高まることになります。ベータでリスクを測れると思っている人たちは、株価が下がるほどリスクが高まると考えます。
しかし、これはまるで不思議の国のアリスです。4億ドルの価値がある資産を8000万ドルで買うリスクよりも4000万ドルで買うリスクのほうが高いとする理由が私にはまったく理解できません。
実際、事業評価に関する知識がある人がそのような株を買うのならば、4億ドルを8000万ドルで買うときの本質的なリスクはゼロです。資産を十分割して、4000万ドルを800万ドルで買うならばなおのことです。ただ、4億ドルの資産を直接管理するわけではないため、誠実でそれなりに能力がある人たちが管理していることを確認したいとは思いますが、それは難しいことではありません。
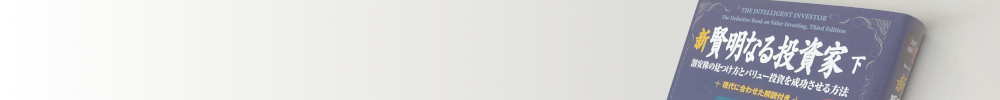
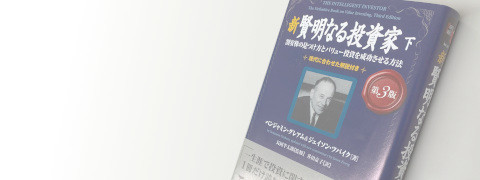
大きな余裕「安全域」
それ以外にも、対象となる企業の価値を概算する知識は必要です。ただし、ぎりぎりで見積もるべきではありません。
これが、ベンジャミン・グレアムが言う安全域の確保です。8300万ドルの価値がある企業を8000万ドルで買ってはいけません。大きな余裕をもって買うことが重要です。
橋を建設した業者が13トンの荷重に耐えると言っても、実際に走行させるのは4.5トンまでにすべきです。これと同じ原則が、投資にも当てはまります。
最後に、より商業的な考えを持っている人たちは、私がなぜこのような話をするのか不思議に思っているかもしれません。バリューアプローチへの転向者が増えれば、価格と価値の差は縮まるからです。
しかし、ベンジャミン・グレアムとデビッド・ドッドが『証券分析』を発表した50年前からその秘密は明かされているにもかかわらず、私がこの手法を実践し始めてから35年間でバリュー投資が流行したことはありません。
人間には、簡単なものをあえて難しくしてしまうつむじ曲がりの性質があるようです。実際、学者の世界では、ここ30年でバリュー投資をカリキュラムから外す傾向があり、その流れはこの先も続きそうです。船が地球を一周しても、地球平面協会は繁栄し続けます。市場で価値と価格の大きな乖離は今後も存在し続け、グレアムとドッドの著書を読んだ人たちも、繁栄し続けるでしょう。
『新 賢明なる投資家【第3版】下』付録
「グレアム・ドッド村のスーパー投資家たち」より
