�����ԡ������š��������ɥ���
�ƽ��ԡ�Ĺ��Ⱦ��Ϻ
�����ԡ����ĵ���
�ȥ졼����������åפ�������̵���Ǥ��Ϥ�
���ܽ�����ȻԾ�λ��Ȥߤ˴ؤ���ͤ�������Ѥ�������Ū���ܤˤʤäƤ��롣���ԤΥ������ɥ����������������Ƥ�������Ǥʤ���¿�����������ĥ٥��ȥ��顼��ȤǤ⤢�롣�ܽ�ǥ������ɥ����ϸĿ����Ȥ˸����ơ��ʤ�������̿�ˤ�äȲԤ��������ɥ֤˼ΤƤ�褦�ʤ��Ȥ�Τ����ޤ����ʤ����ȤǤϤʤ����ʤ��֥���������ڷ���Ҥ�ե���ɤ��٤ޤ���褦�ʤ��Ȥ�Ȥ��Ƥ��Τ��˵�����褷������ʤ��Ȥϰ������褦���⤭�����ԤΥ������Ϥ�뤿��˳Τ���¿���ξڵ���༫�Ȥηи��˴�Ť��Ƽ����Ƥ��롣
���ܽ�Ϥޤ������Τ���ɤ��������������ˡ��ʬ����䤹������ˤǤ�Ǥ���褦�������������˻Ծ��嵤��줬���ä��Ȥ��ˡ�¿�������Ȥ����̤��������ݤȶ��ߤ���ְ�ä�Ƚ�Ǥ��ʤ��Ǥ⡢����äƷ��Ƥ������ˤ��鳰��ʤ���ˡ��Ҳ𤷤Ƥ��롣�ܽ�ϡ��ʲ��Τ褦�ʤ�ؤ֤��Ȥ��Ǥ��롣
���ܽ�ϡ��Ծ�μºݤλ��Ȥߤ����������ɼԤ����ȻԾ���Ф��륢�ץ������λ������Ѥ����μ��˴�Ť�������Ƚ�Ǥ�����ν�ʬ���μ���Ϳ���Ƥ���롣����ϡ��Υ������ڤ�ΤƤ��������٤��ۤ������Ŀ����ȤˤȤäƤ�ɬ�ɽ�Ǥ��ꡢ���ʽ�Ǥ��롣
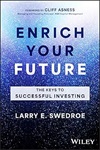 �Хå��ࡦ�����륹���ѡ��ȥʡ����ηкѡ���ͻĴ������Ǥ�ԡ�����������ȣ����ζ��������ꡢʣ���ι�Υ�ǥ����ˤ��Ƥ��Ƥ��롣��������βʳؤ�ʬ����䤹�����������ܤ�ȯɽ���Ƥ���������ˡ��شְ㤤���餱�����ˡ���ӡ����������Ȥ��٤�52����Ȥ���١إե��������������١ʤ������ѥ������ˤ����롣
�Хå��ࡦ�����륹���ѡ��ȥʡ����ηкѡ���ͻĴ������Ǥ�ԡ�����������ȣ����ζ��������ꡢʣ���ι�Υ�ǥ����ˤ��Ƥ��Ƥ��롣��������βʳؤ�ʬ����䤹�����������ܤ�ȯɽ���Ƥ���������ˡ��شְ㤤���餱�����ˡ���ӡ����������Ȥ��٤�52����Ȥ���١إե��������������١ʤ������ѥ������ˤ����롣
����: Enrich Your Future : The Keys to Successful Investing by Larry E. Swedroe
�����Ǥϡغ¤äƤʤ��ǹ�ư�����٤Ȥ����Τ��Q�������������ɥ����ϡ����ˤ����������������Ȥϡع�ư���ʤ��Ǻ¤äƤ����٤��Ȥ������Ȥ�¤�¿���λ��¤�ڵ�両�ڤ��鼨���Ƥ��줿���ºݡ�����㤤�������Ƥ����֥������ɥ����ե��������פϡ����������Ȥ����������䤷������μ���夲����֤ζ�ƻ�ȸ�����ס����������̡����ƥ����֥ʥ��ȡ���å����ۡ���ǥ��������롼�פ��϶ȼԷ�CEO��
����������Ū�ʥߥ����뤿�ᡢ���ݡ��ij���ͭ̾���ԥ����ɤʤɤ��Ѥ��Ƹ�����ά��ƶ�����դ��ҥ�Ȥ��ؤ٤�ڤ��������ס����С��ȥǡ��ޥ륭����ʡإ������볹�Υ����ࡦ�����������٤����ԡ�
�֥������ɥ����ϸĿ�Ū�ʥ��ԥ����ɤ�Ծ����ˤ��Ѥ��ʤ��顢ͭ���������ä�ڤ����Ǥ��դ��Ƥ��롣���Ȥ����Ƥ�����¤�����������θ�����ͦ���Ť����륬���ɥ֥å��ס������ɡ���������ʥǥ塼����طкѳ�����
���٤��ۤ���������ܽ���ɤ⤦���ܽ���ɤߤ䤹���������˿����ꥵ�����˴�Ť����ηä����ˤǡ����ˤĤ��Ƥ���ޤǤǺǹ�ζ��������Ƥ������������������ɥ����ζ����ϡ��ܽ�β��ʤ�100���ܤ�β��ͤ�����ס�������ɥ�塼���ϥ��ʡإߥꥪ�ͥ����ƥ������㡼�١إߥꥪ�ͥ����������ѥåȡ١إХ�٤����ԡ�
�֥������ɥ����ϡ���β��Ū���������ͻ�ξQ������Ǥ��դ������ꥹ���ȥ����δط���������������ư�ե����ʥޤǡ��ܽ�Ϻ���ü�����������Ū�ʥ��ɥХ����ˤ��ƾҲ𤷤Ƥ��롣�����������ꥵ�����㡼��饤�������ޤ�ǻ̩��¿���οͤ���Ω�ĺ��ʤ����߽Ф����ס����ȥӥ����������饤��ʥ����磻�䡼�����ե���ɤΥޥͥ����ǥ��쥯������
�֥������ɥ����ο���������٤ƻ��äƤ��뤬���ʤ��Ǥ��ܽ�ϻ�Τ�����������ס����ƥ��顼�����⥢�ʡإ����ܥ���إå��������ɡ��ȥ�������������ե���ɡ��ݡ��ȥե��ꥪ�٤����ԡ�
�֥������ɥ������ޤ���������ܽ�ϼ�ʬ�������¤��Ѥ��Ƥ���ͤ��ä˴���롣���Ԥϡ�ñ����㥳���Ȥ����ͣ���ɬ��ˡ���ȶ����Ƥ���ס����������֥饤����ȡ�������ʡإϥ����ȥ���������楢���ޥ͡����饹�ȡ٤����ԡ�
���ܽ�ϡ������åɥ�����ͥ�줿�ηä�ƶ�����Τ�����Ϻ����ʣ���ʶ�ͻ��ǰ���饷��ץ�Ǽ¹Բ�ǽ�ʥ��ɥХ�������Ф������ޤ��ޤʥ��ԥ����ɤ����ǡ������������뤿��γˤȤʤ븶§�Ȥ��ñ�������Ƥ��롣�ܽ�ϡ��и�˭�٤����ȤˤȤäƤ⡢��ͻ��ƻ����Ϥ�Ф���οͤˤȤäƤ�ɬ�ɽ����ɮ�Ԥζ�ͻ�����������������ˡ�����ǽ�Ϥˤ�äơ��ܽ�϶���Ū�˰¿��Ǥ���˭���ʾ�����ۤ����Ȥ��Ƥ��뤹�٤Ƥοͤؤε��ŤʻؿˤˤʤäƤ���ס����ӥ롦����륿�����ʡإ��������ҡ��ϥ���������٥������٤����ԡ�
�֥������ɥ��������Ȥˡ������Ũ�Ǥ��뼫ʬ���鼫ʬ������ˡ��Ҳ𤷤Ƥ��롣��ϺǤ⸷�ʤ�����Ū���椫����Ѥ������ͤ�����¤�ڵ��ʬ����䤹���������Ƴڤ����������Ƥ��롣����Ϸ����ס����ޡ��ƥ��ե�ɥ���ʥ��ࡦ�������ƥ�����������٥��������Խ�Ĺ��
�֥������ɥ����η������ɤߤ䤹�������˶�̣������ͤ��٤ƤˤȤäƶˤ�ƽ��פ��ܡס�������ɥ�塼���̡��С�����ʥ֥�å�������������ԥ��롦�ޥͥ����ȤΥꥵ������Ǥ�ԡ�
��¿�������Ȥ���ʬ�����㥳���Ȥ����Ǥ������Υ��������ΤäƤ��뤬���ºݤˤϤۤȤ�ɤοͤ��������ɤ��������ư���餱�Ƹ��̳�����ä���ʣ���ǹ�ۤ�����ʤ���ä��ꤷ�Ƥ��ޤ����ܽ�Ǥϡ�ͥ�줿���ԤǤ��륹�����ɥ�����Ĺ��Ū�����ݡ��ȥե��ꥪ���ۤ�����ˡ�䡢����ˤ�����봶��Ȥ���������н褹����ˡ�䡢���������Ǿ��Ԥ��襤������ˡ���������Ƥ��롣���٤Ƥ����Ȥ��ɤ�٤��ܤǤ���ס����ȥࡦ���å��ʥȡ������ꥢ�롦�ޥ͡��λʲ�ԡ�
��1�� �Ծ�λ��Ȥߡ��������η�ޤ����ȻԾ�ʿ�Ѥ��ȥѥե����ह��Τ�����ͳ
��1�� ���Ⱥķ��Υꥹ���ȥ���������װ�
��2�� �Ծ�ϤɤΤ褦�˲��ʤ����ꤹ��Τ�
��3�� �ѥե����ޥλ�³������������Ȥȱ��Ѳ��
��4�� �Ծ���³���ƥ����ȥѥե����ह��Τ�����ͳ
��5�� �����餷����Ҥ�������������ˤϤʤ�ʤ�
��6�� �Ծ�θ�Ψ���ȥԡ��ȡ��������Υ�����
��7�� ������ʬ�Ϥβ���
��8�� ����˾�फ�����դ�ɬ��
��9�� FED��ǥ�ȥޥ͡����롼�����
��2�� ��άŪ�ʥݡ��ȥե��ꥪ�ˤ������Ƚ��
��10�� �ȥåץץ졼�䡼�Ǥ⾡�Ƥ����ˤʤ��Ȥ�
��11�� �������
��12�� ����˹ͤ���
��13�� Ȭ���դ�����
��14�� ���������֤�Ĺ���˴ط��ʤ��ꥹ�����⤤
��15�� ���̳������Ȥ��ͤ���ʾ�˥ꥹ�����⤤��Ω���ɤߥڡ�����
��16�� ���٤Ƥο徽�̤��ޤäƤ���
��17�� �����������ϰ�Ĥ���
��18�� �֥�å������ȥե��åȥơ���
��19�� ��ϰ����ʤΤ�
��20�� ������̿�Τη�ǰ
��3�� ��ư�ե����ʥ���Ũ�˲�ä�������ϼ�ʬ���ä�
��21�� �֤��ޤ��Ϥޤ����¤�����ߤ���ʤ���
��22�� �ꥹ���ˤϤȤ���ͤ��ʤ���Τ⤢��
��23�� �����ɤ��Ȥ館��Ф褤�Τ�
��24�� �ʤ������ͤ������ʤ��Ȥ�Τ�
��25�� ��鷺���ƾ���
��26�� �ɥ륳����ʿ��ˡ
��27�� �ѥ�������Ҥ��ȸ���Ƚ��
��28�� �㤤����ͭ��������ͭ����
��29�� ���Ȥι�ư�θ�ư��
��30�� �к�Ū���Թ�����������������
��31�� ���ˤ������Գμ���
��4�� ���Ǥ�����Ǥ⾡���襤��
��32�� �ɥ뻥
��33�� ���Ȥκ����Ũ
��34�� �嵤����ɬ�װ�
��35�� �ޥåɥޥ͡�
��36�� �ե��å��������ζ��
��37�� ���롦���ᥤ������ͻ����������
��38�� ��ѥե����ޥΥե���ɤ��ɤ�������
��39�� ����Τ��Ω���ɤߥڡ�����
��40�� �礭����
��41�� ��Ĥ���ά��ʪ��
��42�� ����Ǥ��륢�ɥХ������θ��Ĥ���
����
��ϿA �¹ԡ����侩�������ե����
���ܽ�ϥХå��ࡦ���ȥ�ƥ��å��������륹��Ĵ����Ĺ�Ǥ���Ǥ�������š��������ɥ����ˤ���Enrich Your Future : The Keys to Successful Investing�ɤ�ˮ���ǡ����������Ĥꡢ���̤�夲�뤿����ηäˤĤ��Ʋ��⤷�������Ǥ��롣
���������ɥ���������Ǥ���Ȭǯ�˽��Ǥ��줿���ե���������������١ʥѥ������ˤ�ͭ̾�ǡ�����Ϥ��ʤ��Ū������Ǥ��ä������Ǥ�ե����������ˤĤ��ơ��������Ȥˤ�����Ǥ���褦��ʬ����䤹�������Ǥ��Ƥ�����ҤϤۤ��ˤϤʤ���
������������ʾ�˳�Ū���ä��Τϡ�����ǯ��ˮ�������Ǥ��줿�شְ㤤���餱�����ˡ���ӡ١ʥѥ������ˤǤ��롣����������ᤷ���ͤ��顢���˴ؤ����ɤ�Ǥ����٤����Ҥϲ��������졢�شְ㤤���餱�����ˡ���ӡ٤�������Ϥ������Ȥ�褯�Ф��Ƥ��롣�����Ǥϡ����ˤ�����ɬ�פʤΤ��ðۤʵ��Ѥ�ͥ�줿���ФǤϤʤ���ñ�˵Ҵ�Ū�ǹ���Ū��Ƚ�Ǥȼ�ưŪ�ʹ�ư�Ǥ���Ȥ������Ȥ������֤�����Ƥ��������Ǥ���������ǥå�������ͥ�����ȥ����ƥ��ֱ��Ѥη�٤Ϲ���ǧ������Ƥ��뤬�������Ϥ�������Ƥ���ͤϤۤȤ�ɤ��ʤ��ä������줫����ǯ�ʾ夬�вᤷ�������������ɥ����μ�ĥ���������������ä����Ȥ����餫������Υ��ɥХ����˽��ä��ͤʤ�С�¾�Τ�������������ο�路����ʬ�ʻ��ۤ����Ȥ��Ǥ������Ȥ�������
�������ǡ��伫�Ȥϥ������ɥ������ܤ˵����줿�ͤ�����������ȷŴ�˴��ä�����Ƥ����ˤ⤫����餺����ȴ���ʤ��Ȥˤ����������뤳�ȤϤʤ��ä����ޤ��Ȥ˲���ޤ�뤳�Ȥ������������ɤ����Ȥ��ΤäƤ�������ʤ���Фޤä�����̣�Ϥʤ��Ȥ������Ȥ���
�������ܽФ����Ȥǡ�¿���οͤ�������ˤ����ºݤ˥������ɥ����Υ��ɥХ����˽��äơ������������뤳�Ȥ��ꤦ������ۤ���������ɬ�פ��ݤ��ϡ��ͤˤ��㤦�������������ʤ��Ȥ⤽��������¸����뤿�������Ϥ����ˤ��롣
�����Ԥˤ����äưʲ��������˴��դΰդ�ɽ�����������ĵ��һ�����Τ�������ԤäƤ����������������ư���ãϺ��ˤ���ǫ���Խ���������ԤäƤ������������ޤ����ܽ�ȯ�Ԥ���뵡��������Τϡ��ѥ������Ҥθ�ƣ������Ĺ�Τ������Ǥ��롣
��2024ǯ10��
Ĺ��Ⱦ��Ϻ
�����������餷���ܤ��ɤ�С������������ɥ����β������ˤĤ����礤�˳ؤ֤��Ȥ��Ǥ��롣���Τʤ��Τ����Ĥ��Ƥ��������ޤ����μ������ꡢ���٤ʸĿ����Ȥ��������Ӥȥޡ����åȥ����ߥdzμ¤˳����Ծ���ȥѥե����ह�뤳�Ȥ��Ǥ��롣�⤷���줬�������ʤ��Ƥ⡢���ǹ����Υץ��Υޥ͡��ޥͥ��㡼�ϰ���Ū�˻Ծ���ȥѥե����ह�뤳�Ȥ��Ǥ��롣���������ʤ��������������������������ɥ����Ͼ��ʤ��Ȥ���˻Ծ���Ǥ��餫�����ͤϡ�����⤽�줬�Ǥ���������Ϥ���äƸ�äƤ��롣�⤷��θ��դ��ʤ��Ƥ⡢ǯ����������Ĥ����Ѱ���Τ褦���������줿�������Ȥϡ�Ĺ��Ū�ˤ���������ղò��ͤ�Ϳ����ޥ͡��ޥͥ��㡼��ۤä����ۤ����ꤹ�븢�¤���äƤ��롣�������ɥ������Ҳ𤹤�ץ����Ծ���Ǥ��餫�����ޤ��ޤ���ˡ�ˤĤ��ƤϤ��Τ��餤�ˤ��Ƥ��������ۤ��ˤ⡢������˴ؤ��뤿������ν��פʤ��Ȥ������Ƥ��롣�㤨�С������Ͻ�ʬ��Ĺ��������ͭ�����̵�ꥹ���ˤʤ뤳�Ȥ⤢�롢����ʬ�ζФ�Ƥ����Ҥ������鹥���ʤ�С����γ����㤤³�����礭�ʻ����äƤ������Ȥ��㥳���Ȥθ�������ˤʤ롢���ɥ륳����ʿ��ˡ�������������뤿�������Ǥ��롢�������ͭ���뤳�Ȥǥ���ե�ꥹ����إå��Ǥ��롢���嵤��줬�ʤ���г����Ծ�ϥѥ�������ˤʤ롽���Ȥ��ä����Ȥ����ޤ��ޤ����ȤϤǤ���ʤ��줬�ܽ���ˡ��Ĥޤꡢ�ܽ�ˤ������餷���ηä��ͤޤäƤ��롣
���ܽ�Ͻ��פ��ܤǡ����ƥ������ɥ������ܤ��ɤ�͡����и�������Τ�����ܤ��ɤ�����Ȥ��ʤ���ǰ�����ȡˤˤȤäƤϾ����ɤߤˤ������⤷��ʤ���¿���ο����ʵ����ɤ���Ƥ����¿�������Ȥ��줷��Ǥ��롢���Υե졼���ˤϻ�ε��˴ؤ���ʸ��⺮���äƤ���ˡ�����Ū�˸����ȡ����ʤ������줫���ɤ⤦�Ȥ��Ƥ����ܤϡ��䤬��������ǽҤ٤����Ȥ����٤ƴְ�äƤ��뤳�Ȥ��ʤ������Ϥ���ä������Ƥ��롣�¤���ζ����Ϥ����ȤϤޤä����դǡ��������Ƥ����Ĺ��Ū�ʻ����ˤ��ʤ�ͭ�����ȸ��äƤ��롣
�����Τ��Ȥϼ�ʬ��Ĵ�٤뤳�Ȥ�Ǥ��롣����ǥ�����Υ��ƥ����֥饤�Ȥϡ����Ȭ��ǯ�Υ���Х�ֻ��Ϥ���äƤ���פΤʤ��ǡ��ּ�����ɤ��������Ϥ����뤳�Ȥ˴ؤ�������Ȼפä��פȸ��äƤ��롣�饤�Ȥ���äƼ����ǽ餫���ɤ�Ǥ�褤������ϴ���ʤ����ä��᤹�ȡ��ܽ�������Ƥ��뤳�Ȥϡ��ؼԤ�����Ԥ���ʸ��ɴ�ܤ��ɤ�������ʬ���뤳�Ȥ��������������Τʤ��ˤ����ʿ�����ޤޤ�Ƥ����ɬ�פ��ɤ���ʬ����ʤ����ˡ�������������������ܽ����������֤dzڤ����ɤ�Ǥ��٤Ƥ����뤳�Ȥ�Ǥ��롣�ܽ�˽ФƤ���Τϡ���ǰ�����뤿���ɬ�פʿ��������ǡ����ʿ���ͤ䡢���פʤ��ȤȽ��פǤϤʤ����ȡ��ɤλ��֤˲����ɤΤ��餤�ε��Ϥǵ����뷹�������뤫�Ȥ��ä����Ȥ��餤�����������ɥ����ϡ���ɴ�ܤ���ܳ�Ū����ʸ�ο�����ʬ����䤹�����ԥ����ɤ˽����������Ƥ��롣
�����ʪ��ˤ�¿���ο������ФƤ��뤳�ȤϤ��Ǥ˽������������ब�����륨�ԥ����ɤϵ������������Υ��ꥷ��ͤ�ʲ���ФΤ��Ф�ϯ�ɤ����ۥ�����ۤ����ǤϤʤ������ʤߤˡ��ܽ�ǰ��Ѥ���Ƥ�����ʸ�Ϥ��ʤ����������������ɥ����������Ȥ��ñ�ˤ����ꡢʣ���ʤ��Ȥ�ץ�ˤ����ꤹ�뤿��ˡ��������Ƥԥ����ɤη��������Ƥ��롣��ϲ�ʬ�Ϥ����������Ѥ�������ˡ����������ɡ��ڥ���饷������ݥ��ޤ����������Ȥä��������Ƥ��롣����ϳؽ�Ū�ʥե����ʥ�롦���ʥꥷ�������㡼�ʥ��ˤ����Ф˽ФƤ��ʤ���
�����������餷���ܤǡ��䤬�Ǥⶦ�������Τ���24�ϡ֤ʤ������ͤ������ʤ��Ȥ�Τ��פǤ���ʤ��ʤߤˡ����������������̤���35�Ϥǡ��ãΣ£äΥ��ࡦ���졼�ޡ������Ȥ�ΤϹ⤯�Ĥ��Ȥ����ٹ���ˡ���ͳ�ϡ������Ϥ��λ�Ǥ⤫�ʤ����ˤ˥Х��ʤ��ȤƤ��뤫��ǤϤʤ����Τ��˻�Ϥ褯�Х��ʤ��Ȥ뤬��������֤��Ƥ��������䤬�פ��⤫�٤Ƥ���Τϡ����˸Ŀ�Ū�ʤ��Ȥ�������Ȭ������ǯ������Ū�����������ԤäƤ�����Ҥ�ͭ̾�ʡ֥Х�塼�ե��������פ��Ʒи������������������Τ��Ȥ����������ɥ����ϡ����Υѥե����ޥ�����Υѥե����ޥ���ΤǤϤʤ��Ȥ����ڵ���ȾҲ𤷤Ƥ���ʤ����Ͼ������դ�ɬ�פʤȤ����ǡ��������ɥ��������ڤ��Ƥ���Τϡ������Ѷ�Ū����������䥿���ߥ������������Ƥ⡢���줬�����ͽ¬�����ΤǤϤʤ��Ȥ������ȡ��äˡ�����Ū�ʻ��ּ��ˤĤ��ƤϤ��������롣�������к�Ū���������Ǥ��ơ�Ĺ��Ū���η�Ū�˹�ѥե����ޥ�夲��ե����������Ѥ����־ڵ�˴�Ť��������̤ǡ����̥��Ū���⤷��ʤ����ȤˤĤ��Ƥϻ��Ʊ�ո��ˡ����������¤Ϥ�����������ʤ�����ϡ�����⾭��Υѥե����ޥ�ޥ���ɤ�ͽ¬���Ƥ��뤬��������椬�ְ�äƤ���ڵ���Ƥ����Ĵ�٤����ּ��ϼ�˻�����ǯ���ޤ����֥ޥ���ɤˡפȤ������դ����ס��⤷�ɤ��餫���Ф�������ʤ��Ȥ��ϻ�����ǯ���餱���ۤ������֤Τ����ä��ۤ������֤��ϥޥ�����������⤢�ޤ꿮��Ǥ�����ά�ǤϤʤ��Τǡ������˺���Ҥ���٤��ǤϤʤ��ˡ���Ϥ��Τ��Ȥ��������ץ������Ѥ���ǯ����α��Ѳ�Ҥ������äΤʤ��ǡ���������Х�Υ롼��䤵�ޤ��ޤʥѥե����ޥ�ɾ����ˡ���㤨�С��٥���ޡ����Ȥ�����Ū�ʥѥե����ޥ����Υѥե����ޥ����ޤ��ޤʥꥹ��Ĵ����Υѥե����ޥʤɡˤ�ȤäƽҤ٤Ƥ��롣��θ��դ���Ѥ��褦�ʤ���ʳ��ˤ⡢��ϡֻ��饹�Υѥե����ޥ����������˿����ե���ɤ��о줹�뤳�ȤϤۤܤʤ��פȤ����ä��ۤɹ�����ʰ���ⵤ�����äƤ��롣������äȽƤ��졣����ʤ��Ȥϥ˥�ȥ�λ��ۤ��������ˡ�
��ɡ�¿�������Ȥ�Ʊ�����Ȥ�ⷫ���֤��ư㤦��̤���Ԥ��Ƥ��롣�����ơ�����¿�������ä���Ω���ߤޤäơ��ֲ��Υѥե����ޥ˴�Ť��Ƹۤä��ޥͥ��㡼�����Ѹ�˥ѥե����ޥ������ä��Τˡ�Ʊ�����Ǹۤä����Υޥͥ��㡼���⤤�ѥե����ޥ�夲��Ȼפ��Τ��פȼ��䤹�뤳�Ȥ�ʤ������������ɤ�����в����Ѥ��ʤ��ǡ��㤦��̤���ԤǤ���Τ�����������Ϥ���ޤǤ��μ����⤷�Ƥ��������������֤äƤ������ȤϤʤ����ݥ�����Ȥ�����������
��������Ŧ����Τϥ������ɥ��������ǤϤʤ����̤���������˵Ƥ��������䤬���ǯ�˥ե����ʥ�롦���ʥꥷ�������㡼�ʥ��˽��ֻ䤬����Ω�Ĥ��ȥȥåװ졻�פȤ����������軰�̤ϡֲ������꤬�ʤ���С�������ǯ�η�̤�ɾ����ΤϤ�Ϥ��ʤ��ȡפ��ä�������ϡ��������ɥ�����Ʊ�����Ȥ�ä�û�������ʤ��ڵ�ǿ���˽���Τ������Ԥα��Ѳ�ҡʸ��������Ǥ���饹�Ǥ���������פǤ�ˤ���ǯ�μ��Ӥ����֤Τϴְ�äƤ�������Ǥʤ��������̣�դ���ˡ�ʤΤ��⤷��ʤ���ʿ��Ū�˸��ơ��������Ԥ�õ����������ˡ�Ȥ������ʤ��������������ͽ¬�ϤϤ��ۤɹ⤯�ʤ��Τ������Ҥ��ƤϤʤ�ʤ��ˡ�������䤬�������Τϡ�������ǯ�μ��Ӥ����ʤ��ɤ��ä����ǯ���ä������Τ褦�ʤ��Ȥϡ��ߤ�ʤ����ޤ����äƤ��ʤ������ˤϽʤ�������ʤ��Ȥ��顢�ߤ���ܤ�त�Ƥ����θ��������ȸ��äƤ��롣����ʤ��Ȥ������Ƕ��٤�Τϡ�������ǯ�ˤ��ޤ����äƤ���Ȥ��˸¤��롣��⤽����������ξ��϶��֤Ȥ�������������������������Τʤ��Ǥ϶���Ǥ�����
�������ơ���Ȭ������ǯ�ˤʤ�Ⱦ����ϻ䤿��������ؽ�Ū�ʥե��������١�����ά�ˤȤäƤ��ʤ긷�����ʤä�������ۤɤ��ޤ������ʤ��ä���ͳ�����Τ˼������Ȥ�Ǥ��롣���Ū��ʸ̮�Ǹ���ȡ����줬�ɤ�ۤɤ��ˤߤ�ȼ�����䤿����������Ȼפä����Ȥ��ɤ����٤Τ�Τ��ä��Τ���¬�ꤹ�뤳�Ȥ�Ǥ��������ΤȤ������Х륫��ͤ��餤����Ū�����ȡ������ƻ䤿���⡢�Х�塼��������������٤����ä��Τˡ��䤿���Ϥ�������θܵҤ������Υ�����Τˤ������ȤϤۤȤ�ɤ��ʤ��ä����䤿���θܵҤǤ��������������줿�ͤ������㳰�ǤϤʤ��ä�����������Ƥ��Ƥ�ط��ʤ��Ȥ����������ɥ���������פ��Ф��Ƥۤ����ʥʥ졼�����ɡ�����ϤȤƤĤ�ʤ�����ˤʤꡢ���λ�ǯ�֤����ˤ��ޤ����ä�������������ǯ�������������ۤɤǤϤʤ��ä����Ȥ�ǧ��롣����ǯ���˺ǹ�Ĭ��ã�����������ʤ��ۤɵ�ϿŪ�ʥХ֥롽���Ծ�Ǥ������Τˡ֥����������ХХ�塼���פȸƤФ�Ƥ�����������ǯ�֡��������IJ��������Ū����ά��³���������䤷���ꤷ���ͤ��������줿��������ϴˤ䤫���ä�������ǯ���λ����˺Ǥ���Ƥ���Τϰ���������ǯ�ΣɣԥХ֥�Ȥ��θ�ǡ����ΤȤ�������ǯ����Υԡ������������ǯ�Ǥ��٤Ʋ�����������Ϥޤ���ʬ�ΰ줷�������Ƥ��ʤ��ΤĤޤꡢ���λ����ǻ�ǯʬ�Υѥե����ޥ���ꤹ�٤��ǤϤʤ�������ǤϤ�����������ά�ˤ����ʤ�ʤ��ϡ����Ū���㤬�ʤ��ۤɰ¤��Ȥ��ϡ��鷺����ʬ�ΰ�β����Ǥ�ʣ��ǯ�ˤ錄�붯�����ˤĤʤ����ǽ�������롣���������ޤ���ʬ�ΰ�����Ĥ�λ�ʬ����Ⲽ���Ƥۤ����ˡ����������ߤ�ʤϤޤ����Ƥ�դ�Ԥ����Ƕᤦ�ޤ����ä������������̤������餫��̥��Ū�ȸ��虜������ʤ�����������������������ɤ�ۤɤ��������ʤä������ڵ�Ͻ�ʬ������ۤɤ��ä����伫�Ȥ��ɤ������ˡְ��������˼�ưŪ�����ʡפȽ���������������ǯ�Τ褯�����������������Ӥ��˱ɤ����ͤϤ������ʬ���äƤ���Ϥ��������������ɥ������Ҳ𤹤���礫�ķ�ϴ�ʥꥵ�����Ǥߤ���㤦�٤���Τ���ꡢ���٤���Τ���äƤ��뤳�Ȥ�ʬ���äƤ���ˤ⤫����餺���ۤȤ�ɤοͤϤ����Τ��Ȥ��Ǥ��ʤ��ä��ʤ�����ꥵ������¸�ߤ���Τ������������ΤȤ���ˤ���Τ����ˡ�����������ʹ�����뤫�⤷��ʤ��������줬��Τ��Ĥ�θ��������ʻ������������ˤ���Ψ�����ʤ�⤤���Ȥ˸ؤ����äƤ��롣���Ȥ��������ɥ����Τ褦�ʿͤμ�ĥ�˼����Ƥ��Τ褦�ʴְ㤤���Ƥۤ����Ȥ������Ǯ���ʴꤤ���������ˤϾ����Ѥ��⤷��ʤ������䤬����������ά�ǡ��������ɥ��������빽¤Ū���ĥ����ƥ�Ū�ʥݥ������ϡ����Ȥ������Ū�ʤ��ȤƤ���ʤ���С�Ĺ��Ū��̥�Ϥΰ���������������ǽ�����⤤�����ȤϤߤ�ʤۤ������Ȥ������������������ˤߤʤ������פ��������ȻפäƤ��롣����������ǰ�ʤ��餽�����ޤ��Ϥ����ʤ����⤷������ȡ����٤ƤΤ��Ȥˤϴ�̯�ʸ�ʿ���Τ褦�ʤ�Τ�����Τ��⤷��ʤ����ɤ����Ȥ�³����Τ����ۤɡ����Ĥ����褦�������⤷�����³���뤳�Ȥ��Ǥ����Ĺ��Ū�ˤ��ɤ���̤�������ˡ�
�������ޤ��ɤ�ǡ��ܽ�Ϥ����Υ˥ҥꥺ��ǡ����ˤ�����ͭ���ʿ��ä����ˤ��뤳�Ȥ�Τ�������Τ�Τ��Ȼפ����⤷��ʤ����Τ��ˤ���������ʬ�⤢�뤬�����켫�Τˤ����˲��ͤ����롣����ˡ��������ɥ����ϥ˥ҥꥺ������ǤϽ����ʤ����ܽ�Τۤܤ��٤ƤξϤ���ϡ���¿��������Ū������Ȥ�����뤳�Ȥ��äƤ⾡�Ĥ��ȤϤǤ��ʤ��פȤ������ˤʶ��Ӥ�ʹ�����Ƥ��롣�����������ΰ����Ǥ���ϡ־��Ĥ���˾���ɬ�פϤʤ��פȤ�����ޤ��Ǥ⤢�롣��ϡ��ץ졼���ʤ����ȤǤ����Ƥ��Ͼ��Ƥ���������Ƥ��롣�����⡢�����ˤϿ����˴ؤ����ɤ����ɥХ��������ץ졼���ʤ����ȤǤ��͵ʡ�ˤʤꡢ�¿�������������Ǥʤ��������ΰ��������᤹���Ȥ�Ǥ��롽����ޤޤ�Ƥ��롣
���������ɥ����θ�����ñ���������ʬ�����������Ȥ��㤯�ޤ���������ʬ���äƤ���Хѥե����ޥ��ɤ��������ꡢ�������ѥե����ޥ���ƨ�줿�ꤷ�ʤ��Ȥ������ȤǤ��롣�ޤ����Ծ�ǥ����ߥ�פ뤳�Ȥ⤷�ʤ����Ծ���Ǥ��餫�����Ȥ��ʤ��ǡ��ؼԤ�ȯ�������ȳ��α��Ѹ���Ԥ��ʤ������֥ե��������פ˽��椷�Ƥ���Ф褤�ʥ������ɥ����Ϥ����˽�����������餯������������餬�֥١����פˤʤ�ĤĤ����ĩȯ���Ƥ���ˡ����κǸ�Υ��ɥХ����ˤĤ��ơ����ȿ������Ĥ��Ϥʤ��Ȥ������Ȥ������äƤ�����ƶ���ϤΤ����ɼԤʤ�С��䤬�������ζä��٤����ʼ���Ǥ��뤳�Ȥ˵��Ť��������ˡ�
����ư�Ͼ��ʤ�ˡ������Ȥ⾯�ʤ�ˡ����٤Ƥʤ�˹ͤ��롣���Ȥϡ����٤Ƥ�����ĤΤ���������ƤϤʤ�ʤ����ǰ��Υ����������ꤷ�����줬�����ä��Ȥ��˱�̿��Ȥ�ˤ��ʤ��褦�ˤ��Ƥ�������27�ϡ֥ѥ�������Ҥ��סˡ��⤷�Ծ���Ǥ��餫�������ʤ�С���ư�ե����ʥȤ���פ���μ¤ʾڵ�ȳؽ�Ū��ȯ���˴�Ť���ˡ���Ѥ��뤫���ꥹ���ץ�ߥ������ݤ��ƹԤ����Ȥ�롣�����ơ��Ǹ�ޤǤ���ڤäƤۤ�����
������ʤ�С��������ɥ����Ϥ����ζ��������̤γؽ�Ū�ڵ�������餷�����ԥ����ɤ��㤨�ä����Ф��ƺǽ餫��Ƥ����Ф褫�ä��Ȼפ����⤷��ʤ���������������ǿ����뤳�ȤϤǤ������������������餯̵�����������������ʤ�Ǥ���Ϥ�����
����ա������ͥ��ʣ��ѣҥ���ԥ��롦�ޥͥ����ȼ�
�ޥͥ�������ɡ��ե���ǥ����ץ�ѥ��
������ꥫ�ͤϹ����ʪ�ؤ�ؤ֤��ᡢ�����⥢��ФˤĤ��Ƥ褯�ΤäƤ��롣���Ϥ��٤ƤοͤˤȤä����餫�˽��פǤ���ˤ⤫����餺������ꥫ�ζ������٤ϥե����ʥ�����ʬ���ۤȤ��̵�뤷�Ƥ��롣��ؤηбij�����б���ر�������ʤ���С������ؤ֥���Ϥʤ����㤨�С����Ĺ���������餷����˹Ԥ�����ǯ�졻�̰����´�Ȥ����������ʪ�ؤä�����ϡ�����ФˤĤ����ΤäƤ����٤����Ȥ٤��ΤäƤ��롣����������ͻ�Ծ�λ��ȤߤˤĤ��Ƥϲ����μ���ʤ���������Ծ���ʤ��ɤΤ褦�˷�ޤ뤫���Τ�ʤ��������������Τ褦�ʴ���Ū�ʤ��Ȥ����Ƥ��ʤ���С��μ��˴�Ť������Ƚ�Ǥ���Ϥ����ʤ���
��¿�������Ȥ�����褦�ʾ����ˤ��뤬�����Τ��Ȥ˵��Ť��Ƥ��餤�ʤ��ͤ�¿�������ϻԾ�λ��Ȥߤ����Ƥ���Ĥ����������¤Ϥޤä����㤦���桼�⥢��ȤΥ���å��塦�ӥ���θ��դ�ڤ��С��֥Х��ʤ��Ȥ�Τ��Τ�ʤ�����ǤϤʤ����ΤäƤ��뤳�Ȥ��ְ�äƤ��뤫��ס���ɡ��Ŀ����Ȥϼ�ʬ��Ƚ�Ǥ��⤿�餹��̤����뤿��δ���Ū���μ�������ʤ��ޤ����Ƥ��롣����ϡ��Τ�ʤ������Ͽޤ�ǣУӤ�����ʤ��ǹԤ��褦�ʤ��Ȥ���¿�������Ȥϥե����ʥ������ʶ��������Ƥ��ʤ����ᡢ��������������Ƥ���Q�ʿ�����Ʃ���Ƶ������ĿͤϤۤȤ�ɤ��ʤ��ˤ˴�Ť���Ƚ�Ǥ���
���ܽ�˽Ƥ��뤳�Ȥ�����ʬ�ϡ��Q���������ƶ��٤ʿͤʤ�лԾ��Ŭ�����ʤǤʤ������Ĥ��뤳�Ȥ��Ǥ���Τǡ���¤γ�����ä��ꡢ���γ����������ꤷ����Ǥ��롽���Ȥ���ȿ�Ф����ƤˤʤäƤ��롣�ޤ������ξQ�ϡ����Τ褦�ʸ������ȤϻԾ�ǥ����ߥ�פ뤳�Ȥ�Ǥ��롽��������줬�Ϥޤ����˻ųݤ����嵤��줬�Ϥޤ�������뤳�Ȥ��Ǥ��롽���Ȥ⤷�Ƥ��롣���줳���������ƥ��ֱ��ѡ��Ĥޤ����������ƥ����ߥƥȥ졼�ɤ��뤳�ȤǤ��롣����ʳ�����ꥫŪ���Ȥ����ͤ����餢�롣����Τξ�ʤθ��դ�ڤ��С��ֶ��١����ϡ�Ĵ���������������餷����̤�⤿�餹�Ϥ������������ʤ��ǥץ��δ����˾���櫓���ʤ��ס�
��������������¿���Τ��ȤˤĤ��Ƥ����������ʤ�����Q�ˤʤäƤ���ˡ��Ծ���Ǥ��餫�����Ȥ��㳰�Ǥ��ꡢ�����ˤ��ιͤ��������꤬���롣�⤷���Ϥȶ��٤�����������餷����̤�����ʤ�С�������ǽ�Ϥ����ꡢ�褯Ư���ץ��Υޥ͡��ޥͥ��㡼�ΤۤȤ�ɤ���ǯ�Τ褦�˻Ծ���Ǥ��餫�����Ȥ��Ǥ��ʤ����Ȥ�ɤ���������Τ����������Ծ���ȥѥե����ष���Ȥ��Ƥ⡢������ʴ����ͤ�Ķ����ѥե����ޥ�ݻ��Ǥ��ʤ��ΤϤʤ��������������Υ���ƥ���Ҥ�����ι�ѥե����ޥ�夲�뱿�Ѳ�Ҥ�����Ǥ��ʤ��ΤϤʤ�����������
���⤷�����Ѥʤ������Ⱦڵ�˾Ȥ餻�С����ξQ���ְ�äƤ�������Ǥʤ����ǽ餫�����ˤ��ʤäƤ��ʤ��ä����Ȥ˵��Ť��������ʥ�å��塦��ӡ��ϡ֥����ƥ��ֱ��Ѥλ��»���פȤ��������Τʤ��ǡ�����ꥫ�Υ����ƥ��ֱ��ѥե���ɤΥѥե����ޥ�ɾ����������ꥫ���Υ����ƥ��ֱ��ѥե���ɤ����Ȥ���ä�»����ǯ���ޡ����ɥ�˾��ȿ��ꤷ�Ƥ���ˡ��ºݡ������������Ū�Ǥ��롣��ϡ��ܽ�ǾҲ𤹤륨�ԥ����ɤ�ñ�����̥��Ū�������ȡ������������դ���ڵ�ˤϰ���Ū�������Ϥ����ꡢ�ɼԤϤ������Τ���ǧ��Ƥ����ȳο����Ƥ��롣���ĤƤϡ��ϵ�ʿ����פ��ŷư��פ��Q���ä����Ȥ�פ��Ф��Ƥۤ������������㤬�����褦�ˡ��Q��ɬ�������������櫓�ǤϤʤ�������������С��Х��������Ȥ���ͤ���ɴ���ͤ����Ȥ��Ƥ⡢����Ϥ�Ϥ�Х��������ȤʤΤǤ��롣
������Ϥʤ��ʤ��ä��ʤ����äˡ���������ؤǤ��륦�����볹���ͻ��ǥ������ݻ����������ϡ������ǡ��ܽ�Ǥϻ��Ĥ���ɸ��Ǥ��롣����ܤϡ��Ծ�������λ��Ȥߤ��������뤳�ȤǤ��롣�������������ǰ�����䤹���ʤ롣�����Ǥϥ��ԥ����ɤ��㤨�äȤ����ʤ��ߤΤ������ȤߤΤʤ����������������������˴�Ϣ�����뤳�Ȥǡ�������ɸ��̤��������ȻפäƤ��롣���ԥ����ɤΤʤ������������������Ǥ�������ȴ�Ϣ�Ť���С�������Τˤʤ�Ϥ�����������٤���ڵ���Ф���ˤ����ʤ��������
���⤷���κǽ����ɸ��̤������Ȥ��Ǥ���С�����ܤ���ɸ�Ǥ������ȻԾ�λ��Ȥߤ˴ؤ���ͤ�����ʱ���Ѥ��뤳�Ȥ�̤������Ȥ��Ǥ��롣
�������ƻ����ܤ���ɸ�ϡ�����μ��˴�Ť�����긭�����Ƚ�Ǥ�����ν�ʬ���μ������뤳�ȤǤ��롣
���ܽ�ϡ���ĤΥ����פ��ɼԤ����ꤷ�ƽ��������Υ����פϸĿ����Ȥǡ��⤦�����Υ����פϥե����ʥ�륢�ɥХ������Ǥ��롣���Υ��ɥХ������ϡ��ܵҤ���ϫ���ƲԤ��������̵�̤ˤ��ƾڷ���Ҥ�ե���ɤ���䤷���ꤹ��Τ��ᡢ���Ԥ��襤��褦��������Ȥ��ˡ��ܽ�Υ��ԥ����ɤ���Ω�ƤƤۤ�����
���ܽ�ϻͤĤ�����ʬ����Ƥ��롣�裱���ϻԾ�������λ��Ȥߤ䡢�ڷ����ʤη�ޤ����䡢�ꥹ��Ĵ����˹⤤�ѥե����ޥ�夲��Τ�����ͳ�ʤɤ���������ˤʤ뤳�Ȥ�տޤ��Ƥ��롣�裲���ϡ��ݡ��ȥե��ꥪ���ۤ���Ȥ��˥����Ȥʤ�Ƚ�Ǥ������ˤʤ롣�裳���ϡ��ʹ֤����������δְ㤤�ˤĤʤ��뤳�Ȥȡ��μ�����Ĥ��Ȥ��ְ㤤�餹�����ˤʤ롣�裴���ϡ����Ԥ��襤������ˤʤ�ƶ����Ҳ𤷤Ƥ��롣
���ܽ���ɤ�С����Ĥ������ά�ϼ¤�ñ��ǡ����ͥ륮���⤢�ޤꤤ��ʤ��Ȥ������Ȥ�ʬ���롣�Ĥޤꡢ������ά�϶���Ū����ɸ��ã�������ǽ�����Ū�˹�������Ǥʤ�������μ�����Ƥ�������40�ϡ��礭���С��ȡˡ������θ������Ȥϡ�����Ū��ʬ�������֥ѥå��ֱ��ѡפΥݡ��ȥե��ꥪ���ۤ��Ƥ��롣�ѥå��ֱ��Ѥ��оݤϥ���ǥå����ե���ɤΤߤ��ȹͤ���ͤ⤤�뤬����Ϥ���ʳ��ˤ�ڵ�ʰո��ǤϤʤ��ˤ˴�Ť���Ʃ�������⤯�������ƥޥƥ��å��ǺƸ���ǽ����ˡ�ǹ��ۤ��줿�ե���ɤ�ޤ�Ƥ��롣�����ǥ����Ȥʤ�Τϥ����ƥޥƥ��å��Ǥ��뤳�Ȥ��������������ƥޥƥ��å��˱��Ѥ����ե���ɤ��㤦���Ȥ������������뤿���ɬ���Ǥ����ʤ�����ʬ���ϡ��Ծ�ΥΥ����䡢�������볹���ͻ��ǥ����Υץ��ѥ�������Ǥ蘆��ʤ�����ͭ��³���뤳�ȤǤ��롣
����ι����ʸ��դˡ��ֶ����⤤�Ȼפ��ʤ�С�̵�ΤˤʤäƤߤ��פ����롣�ܽ���ɤ�ǡ������Ǽ��夲��������꿼���������Ȼפä��ꡢ�μ��������Ȼפä��ꤷ�Ƥ��줿�餦�줷�����⤷�ܽڤ����Ƥ���ˤʤ�ȻפäƤ��줿�ʤ�С�������˴ؤ��ơ��إե��������������١شְ㤤���餱�����ˡ���ӡ١ʥѥ������ˤ������ޤ�ư�Ȭ���������롣�������ܽ�Υơ��ޤ��꿼���Ƥ�������Ǥʤ��������Ǥϼ��夲�뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ��ä���������Τ��Ȥˤ���ڤ��Ƥ��롣
�����ʤߤˡ��ܽ�ǾҲ𤷤����ԥ����ɤΤ����Ĥ��ϡ��إ磻��������٥��ƥ����ᥤ�ɡ�����ץ��Wise Investing Made Simple�٤ˤ�ФƤ��뤬�����٤ƤΥ��ԥ����ɤȥǡ����Ϲ�������Ƥ��롣
�����̳����㤦�ȡ������餷�������ʼ��Υ������뤬���Ĥ��뤫�⤷��ʤ��ˤ��Ỵ�ʷ�̡ʼ��Υ������ˤʤ뤫�⤷��ʤ��ˤȤ�����Ĥβ�ǽ�������롣�������ºݤˤϡ����ȤϤ虜�虜�ꥹ����ȤäƤ��Ỵ�ʷ�̤˽��������Ȥ���ñ��ʬ���Ǥ���ꥹ�����ƤȤäƹ⤤��������Ԥ��Ƥ⡢�Ծ�Ϥ�����Ƥ���ʤ��ˡ��Ĥޤꡢ���̳������ʤ����Ȥ�����Ū����ά�ˤʤ롣��ǰ�ʤ��顢ʿ��Ū�����Ȥϥꥹ����������Τˡ����Τ褦�ˤϹ�ư���ʤ����������ȷи�����ڴ��������ä�ʬ�����뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ��������
��ʬ������ۤ������餫��ͭ���ʤΤˡ����ȤϤʤ��ݡ��ȥե��ꥪ��ʬ�������ʤ��Τ�����������ͳ�ΰ�Ĥˡ��ۤȤ�ɤ����Ȥ����̳��Υꥹ���ι⤵�����Ƥ��ʤ����Ȥ����롣�����μ�������������ˡ������Ĥ���ʸ���Ƥ��������ǽ�ϡ����ܡ��ɡ������åȡ��ޥͥ����Ȥˤ��֥�������ԥ��ꥺ�ࡦ�ǥ����ȥ�ӥ塼������The Capitalism Distribution�ˡפǡ�����ϳ��ξ�̻���������������Ȭ������ϻǯ�ˤ�����Ĵ�٤Ƥ��롣���Ԥ����ϡ���å��뻰�������Υ����ǯΨ����Ȭ��ǡ����ѥ����ϻ��͡�ʤΤ��Ф��ơ����̳��˴ؤ��뼡�Τ褦�ʻ��¤�Ҥ٤Ƥ��롣
�������������ä����Ȥϡ��ܸۤ�ʬ����γ�Ψ�ǻ������оݴ��֤˻Ծ���ϻ��͡�ʾ奢������ѥե����ष����������ѥ���ե�Ψ�ΰ졻����ä��ˡ����ʬ�ΰ�γ�Ψ�����ۤμ��ޡ�ȥ���ե�ʬ�ä������ʤߤˡ���ɸ���ȥѥե����ह��������ֳ�Ψ�ϡ���ʬ�ΰ��Ķ�������٤��ä���
�����٤Ƥγ���ʿ��ǯΨ����ޥ��ʥ��ʤΤˡ��ʤ���å��뻰�������Υ���ץ饹�ʤΤ�����˻פ����⤷��ʤ��������ϡ����λ�ɸ�λ�����ˡ�ˤ��Ȥ������礭������å��뻰�������ϻ������ۤDzýŤ��Ƥ��뤿�ᡢ��Ĵ�dz������徺���Ƥ�����βýŤ��礭���ʤ롣Ʊ�ͤˡ���Ĵ�dz����������äƤ���С��ýŤϾ������ʤ롣����˲ä��ơ�ǯΨ����ޥ��ʥ��γ��Ϲ�Ĵ�γ�����¸³���֤�û���ʤ뤿�ᡢ��ɸ�˥ޥ��ʥ��αƶ���Ϳ������֤�û���ʤ롣
�����̳��Υꥹ���ι⤵�������⤦��ľҲ𤷤褦�����塻ǯ������Ū�ʶ������ǥ�å��뻰��������ǯΨ�켷������Υ�����夲�����ѥ�������Ͱ졻��ˤʤä�����Ʊ�������Υ���ꥫ���強�����Υ����ϥޥ��ʥ����ä������ʤߤˡ�����ϼ¼������ǤϤʤ����Х����ǡ��Ծ��Ͱ졻��ʾ奢������ѥե����ष���ˡ��ޤ������ΰ졻ǯ�����ѥ���ե�Ψ�ϻ������ޡ���ä����ᡢ�¼�Ū��»���ϻ������ޡ��Ķ���Ƥ��������������ξ�Ū�ʿ����Ǥ������ΤǤϤʤ�������Ϥ��δ��֤��̤���¸³���������Τߤ��оݤȤʤäƤ��뤿��ǡ����ο����ˤ��礭����¸�ԥХ������������äƤ��롣
���إ�ɥ�å����٥å���Х����������ʸ�֥ɥ������ȥå��������ȥѥե����ࡦ�ȥ쥸�����ӥ롩��Do Stocks Outperform Treasury Bills?�ˡפ������̳��Υꥹ���ι⤵����������ˤʤ롣��ϰ����ϻ�����ǯ�ΣΣ٣ӣšʥ˥塼�衼���ڷ������ˡ���������ʥ���ꥫ��ڷ������ˡ��ʥ����å��Τ��٤Ƥξ����ˤĤ���Ĵ�٤���̤��Τ褦�˽Ҥ٤Ƥ��롣
����ɡ��ۤȤ�ɤ����̳��ʼ������Τ����������ʾ�ˤϡ����ξ����֤ˣԥӥ�Υ������ȥѥե����ह�뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ��ä����٥å���Х��������Ĵ����̤ϡ��ݥ��ƥ��֥����塼�����ʤ��礭�����Ȥȡ��������Τ褦��ʬ���ˡ����̳��Υ����ˤϥꥹ����ȼ���Ȥ������Ȥ��ä����ޤ����ѥե����ޥǾ��Ȭϻ���������Τλ�ʬ�ΰ��������ʤ��ˤ������Τ����פ�Ⱦʬ�ʾ�����߽Ф��Ƥ����������ơ���̰졻�������������Τλ͡��ˤ��ۤܤ��٤Ƥ����פ����߽Ф��Ƥ������������Ĥ�ζ�ϻ��γ��Υ����ϡ�̵�ꥹ���ΰ쥫��ʪ�ԥӥ��Ʊ�����ä�������Ϥ��������Ȥ����������Ȥˤ��礭�ʥꥹ���ץ�ߥ��ब¸�ߤ�������ǡ�����Ĵ���ǤϤۤȤ�ɤγ��Υץ�ߥ��ब�ޥ��ʥ��ˤʤäƤ���������Ĵ����̤ϡ���Ĥ��������θ�����������äƥꥹ����ȤäƤ�����ʤ����������ɤ�ۤ�¿�������Ƥ��롣�����������Υꥹ����ʬ���ˤ�äƴ��ԥ������뤳�Ȥʤ�����Ǥ��롣
���٥å���Х�������ϡ����Ĵ����̤���ʬ���٤��㤯�ʤ꤬���ʥ����ƥ�����ά��¿�����٥���ޡ���������ѥե����ह����ͳ����������ˤʤ�Ȥ��Ƥ��롣��Ϥ���ˡ������η�̤�ʬ�����ʤ��ȥ٥���ޡ���������ѥե����ह�뤳�Ȥ��Τ�ʤ��顢���������Τ褦�ʡ�̤��ä˰���������Ȥ�ʬ���٤��㤤�ݡ��ȥե��ꥪ�����������뤳�Ȥ˻Ȥ�줫�ͤʤ��Ȥ���äƤ��롣�����ǡ��٥å���Х�������ϡ�������Ū�����αƶ��Υǡ����ǻ�Ŧ���Ƥ��롣���㽽ʬ�̤γ��Τʤ��ǰ쥫��ʪ�ԥӥ�Υ������ȥѥե����ष���ΤϤ鷺�����졦�ޡ���ä��������줬�ǹ⽽ʬ�̤γ��ϸ塦�����ä���
������ޤǸ��Ƥ��������̤ϡ��ݡ��ȥե��ꥪ��ʬ�����뤳�Ȥν��פ����˸������ƤƤ��롣ʬ���ϡ�����ͣ��Υե�����Ǥ��롣����������ǰ�ʤ��顢�ۤȤ�ɤ����Ȥ��ܤ����Τ��������˼��Ф��ʤ����٥å���Х�������ϡ�������Ƥ��롣�֤����η�̤ϡ�ʬ�����Ƥ��ʤ��ݡ��ȥե��ꥪ���٥���ޡ���������ѥե����ह��Τϡ��礭�ʥ��������߽Ф������Ĥ��γ�����äƤ��ʤ����餫�⤷��ʤ��Ȥ������¤��ܤ���������롣���η�̤ϡ��ʤ������ƥ��֥ݡ��ȥե��ꥪ��ά�ʤ����Ƥ��Ϥ��ޤ�ʬ������Ƥ��ʤ��ˤΤۤȤ�ɤ��٥���ޡ���������ѥե����ह����ͳ��������������ˤʤ롣�ѥե����ޥ��㤵���̾�ȥ졼�ɥ����ȡ�����������ˤ�äƤϥޥ��ʥ�������Ȥ�������ư�Х������ˤ��Ȥ���Ƥ��롣�������������ޤǤη�̤ϡ������������Ȥ�������ո��̤Υ�������⡢���ޤ�ʬ������Ƥ��ʤ����ȤΤۤ��������ƥ��ֱ��Ѥ���ѥե����ޥˤ��Ƥ����ǽ�����⤤���Ȥ��Ƥ��롣
���������������ꤹ�뤳�Ȥǡ���ꤦ�ޤ��ꥹ��������Ǥ���Ȥ���ǧ���ϡ��ְ�äƤ��롣
����ư�ե����ʥ�ʬ��餵�����������ȡ����ȤϤ椬�ߤࡣ���ϡ��ѥե����ޥ��㤯�ʤ��ǽ���Τۤ����Ϥ뤫�˹⤯�Ƥ⡢�㤤��Ψ���������Ƽ��Υ������뤫�⤷��ʤ������㤦������������С��������������㤦�褦�ʤĤ�����Ƥ���Τ����⤷���ʤ����ְ㤤���Ȥ����ȼ��Ф����Τʤ顢�����ͤ��äơ����δְ㤤�������Ƥۤ�����
�����ϡ������������������Գμ����ˤ��դ�Ƥ��뤫�����뤳�Ȥν��������������롣���������Ǥϡ��ޥ��ʥ��η�̤�����뤳�ȤϤǤ�������¬���뤳�Ȥ����Ǥ��ʤ����ޤ��������ʷ�̤˽�����ǽ�����θ�������ײ���Ȥ߹���Ǥ���ɬ�פ�������ͳ���������롣�Ǹ�ˡ����ƥ�������ߥ�졼�����������Ω�ĥġ��뤫���������롣
�������١�����Τ�Ԥ��٤��ˡס���Ϸ�ҡ��軰���ϡ�
�������ȡ������ͥ��åȤϡ�Ʊ�Ȥκ�ȤǤ��른�祻�ա��إ顼�ˤĤ��Ƽ��Τ褦�˽Ƥ��롣�֥إ顼�Ȼ�ϥ����륿����Dz���Ĺ�Ԥ��������ѡ��ƥ����˻��ä��Ƥ�������ϥإ顼�ˡإ��硼�����Υѡ��ƥ����μ�żԤ����ξ���إ���å�22�٤�����ޤDzԤ�����ۤ���¿������������DzԤ������Τä���ɤ�ʵ�ʬ�����٤�ʹ���ȡ��फ����ͤ��ब���Ф˻��Ĥ��Ȥ��Ǥ��ʤ���Τ���äƤ����٤Ȥ����������֤äƤ�������ϡؤ���ʤ�Τ�����Τ����٤�ʹ������ϸ��ä����ؤ⤦��ʬ�Ͻ�ʬ���äƤ�����ΤäƤ��뤳�Ȥ���١�
������ǯ����ϣԣɣǣţ�21���롼�ס�Ķ��͵�ؤΤ�������֡ˤ���ߥʡ�����ꤵ�줿�����Υ����֥����Ȥˤϡ��֣ԣɣǣţ�21�Υ��С��ϡ�Ķ��͵�ؤ��ߤ��˳ؤӤʤ����������⤿�餹����ȥ�����б����Ƥ������Ȥ��ǽ�ˤ��뿮�����̩����Υ��ߥ�˥ƥ����ΰ���Ǥ��פȽƤ��롣
�����ߥʡ��ˤĤ�����餫�顢��������ꥹ���ˤĤ��Ƥɤ��ͤ��Ƥ��뤫�ȡ��ɤ��ͤ���٤����ˤĤ����ä��Ƥۤ����Ȥ�����˾�����ä�����ϼ��Τ褦����������
������³������ΤǤʤ������ꡢ��ۤκ�����߽Ф�����Ū����ˡ�ϡ�¿���Υꥹ����Ȥꡢ�����Ƥ��Ϥ����ʬ����ͭ������Ȥ˽��椵���롣�����顢ŵ��Ū����͵�ؤϵ��ȲȤȤ������������ͤ��������Ĥޤꡢ�����ܼ�Ū�˥ꥹ���ƥ������ǡ������и��⤢�롣���Τ��ᡢ���ϥꥹ����Ȥ뤳�Ȥ˼��������ꡢ���줬�ꥹ����Ȥ���ߤˤĤʤ��äƤ��뤳�Ȥ�¿���������⡢���ϵ�ۤλ���äƤ��뤿�ᡢ�ꥹ����Ȥ�ǽ�Ϥ⤢�롣�����Τ��Ȥ��Ȥ߹�蘆�äƤ���Τǡ����ϥꥹ����Ȥ�³���롣
�����������ꥹ����Ȥ�ǽ�ϤȰ��ߤϡ��������ˤ����Ȥ��˹�θ���٤����Ĥ����Τʤ�����ĤǤ����ʤ��������ܤϸ��ᤴ����뤳�Ȥ�¿�������ꥹ����Ȥ�ɬ���������������礤�������ʤΤϡ��ꥹ����Ȥ�ǽ�ϤȰ��ߤ�Ǥ���äƤ���ͤ����������ꥹ����Ȥ�ɬ�פ��Ǥ�ʤ��ͤ����Ǥ⤢�롣
��ɬ�פʤ��Ȥ��Ť��뽽ʬ���٤���Ŀͤ����ϡ�������ˤʤ���ά�ȶ�����ǵ�³���뤿�����ά�Ϥޤä����㤦�Ȥ������Ȥ�����ɬ�פ����롣����Ū�ˡ�������ˤʤ뤿�����ά�ϥꥹ����Ȥ뤳�Ȥǡ������Ƥ��Ϥ����ʬ�λ��ȤǹԤ�����������������ǵ�³���뤿�����ά�ϡ��ꥹ����Ǿ��¤��ޤ����Ȥ�ꥹ����ʬ���������ʻٽФʤ����ȤǤ��롣
����ϣԣɣǣţ�21�Υ��С�����ɸ��������ǵ�³���뤳�ȤǤ��ꡢ������ɸ���Ȥ߹�������������ײ��Ω�Ƥ뤳�Ȥ����פ����ä��������ηײ�ϡ������������˳�ͤ�ž��뤳�ȤϹͤ������ʤ��Ȥ������¤˴�Ť���Ω�Ƥ�٤��Ǥ��롣
��Ŭ�ڤʻ���ʬ�����Ȥ������Ȥ��٤θ³����ѡ��Ĥޤꡢ���¿�����ԥ�����夲�뤿��ˤȤ�ꥹ������٤ơ�����Ū���٤����äˤɤ�����β��ͤ����뤫��ͤ���ɬ�פ����롣���������Ͼ��ʤ�����¿���ۤ����褤�����ۤȤ�ɤοͤϤ�������ǡ����˲�Ŭ�ʥ饤�ե��������ã�����롣�����ʤ�ȡ��������餵��ʤ��٤����뤿��ˤ���ʤ�ꥹ����Ȥ뤳�ȤϤ⤦��̣���ʤ��ʤ롣ͽ�����ʤ�������̤�����Ū�����»���ϡ�����ʤ��٤�������åȤ�Ϥ뤫�˾��뤫�����
�����ȤϤߤ�ʼ�ʬ�θ��Ѷ������ɤο�फ���ʿ�ˤʤꡢ����Ϥ�뤫�ˤ��ɬ�פ����롣���λ�������ϡ�����ʤ���ԥ�������ơ��ɲ�Ū�ʥꥹ����Ȥ���ͳ�ʤɤʤ��ʤ뤫�����¿����͵ʡ�����Ȥ������祻�ա��إ顼����ä��ηä���äƤ���С�����Ū��»�����ñ���뤳�Ȥ��Ǥ����������ʤ��ʤ��ϥޥɥդȤ���̾����Ф��Ƥ�����������ˡ�
���⤦��ʬ���Ȥ����������Τ뤳�Ȥν������ϡ������㤫���ʬ���롣����ǯ�ΤϤ���ˡ���ϼ���Ф����ؤ��Τ��ä������ζ�ͻ�ϻ��������ɥ���ä�������ǯ���ˤϰ컰�������ɥ뤢�ä�����餬����ۤ��礭��»������ä��Τϡ��Τۤܤ��٤Ƥ������ǡ�����⥢��ꥫ���緿��Ĺ�����ä˥ƥ��Υ����������˽��椷�Ƥ���������ä������ˤϤ��δ֡��ե��ʥ�륢�ɥХ����������������������Τ��Ȥϡ��ɤ����ɥХ�����ɬ������⤤�櫓�ǤϤʤ������������ɥХ����Ϥۤ�ɬ���⤯�Ĥ����Ȥ��Ƥ��롣
�������ͤˡ��⤷�ݡ��ȥե��ꥪ�β��ͤ�Ȭ���ǤϤʤ����ܤ���ϻ�������ɥ�ˤʤä��顢����μ����礭���Ѥ�뤫��ʹ���Ƥߤ��������Ϥ��äѤ�֥Ρ��פ��ä����䤬���컰�������ɥ뤬���������ɥ�˸���Τ�Τ����˿ɤ��и����ä��Ϥ��ǡ�̲��ʤ���⤿�����ä��������ȸ����ȡ������礭�����ʤ����������˻�ϡ��������פ�����������礭���Ѥ��ʤ��Τˡ����Ԥ���Ф���ۤɿɤ���̤�����褦�ʥꥹ����ʤ��Ȥä��Τ���ʹ����������ȡ��ʤ��פ�ѥ�����Ƹ��ä����֤�������ä�����ʤ���
���ꥹ���Τʤ��ˤϡ��Ȥ���ͤ��ʤ���Τ⤢�롣�������Ȥϼ�ʬ��ǽ�Ϥ���ߤ�ɬ�פ�Ķ����ꥹ���ϤȤ�ʤ��������ǡ���ʬ���Ȥ��䤦�٤����פʤ��Ȥ����롣���Ǥ˾��äƤ���������ʤΤˡ��ץ졼��³�����̣������Τ���������
��ɬ�פʤ�Τ���˾
�����Ǥ˾��äƤ����������ץ졼��³���Ƥ��ޤ���ͳ�ΰ�Ĥϡ����ĤƤ��ߤ����ä���Ρʿ�����ڤ��ि��ˤ��ä���褤����ɬ�פǤϤʤ���Ρˤ���ɬ�פʤ�Τ��Ѥ�äƤ��ޤ����Ȥˤ��롣�����ʤ�ȡ��Ȥ�٤��ꥹ����������������ʬ��¿���ʤ롣���η�̡���強������強��ǯ������ǯ������ǯ������ǯ����Ȭǯ�����������ʴ����ɴ�����������ǯ�Τ褦�˥ꥹ�������¤ˤʤä��Ȥ������꤬�����뤳�Ȥˤʤ롣
������
���ꥹ����Ȥ�ɬ������ͤ��ʤ��Τ�͵ʡ�ʿͤˤ褯����ְ㤤�ǡ��ä��礭�ʥꥹ����Ȥä��٤��ۤ����ͤˤ��η��������롣������ɬ�װʾ�Υꥹ����Ȥ�ְ㤤���Ȥ��Τϡ�����������ǤϤʤ��������ǡ������餪�⤬����й����ˤʤ��Τ��ȹͤ��ƤߤƤۤ������ۤȤ�ɤοͤϡ����ζ�ۤ��פä����⤺�äȾ��ʤ����Ȥ˶ä��Ȼפ��������ؼԤˤ��ȡ�����ʪ���ȡ������Ȥ��ä�����Ū�ʥˡ�������������ʬ�ʤ����������Ƥ��ޤ��ȡ��������Ƥʡ�٤��Ѳ��Ϥʤ��������Τ��Ȥ����������ȡ��������ɤ����Ȥ�����������ʤ��Ȥ�̵�����¤����㤨�С�����ʿͤȸ�����⤹�롢��ž�֤˾�롢�ܤ��ɤࡢͧ�ͤȥ֥�å��롢�Ҷ���¹��ͷ�֤ʤɤȤ��ä����Ȥˤ��ޤꤪ��Ϥ�����ʤ��������ơ�����Τ��졻�ɥ�Υ磻��Ǥ�졻���ɥ�Υ磻��Ǥ⡢��ͤǿ�����Τ��ޡ��ɥ�Υ쥹�ȥ��Ǥ�ޡ����ɥ�Υ쥹�ȥ��Ǥ⡢����ǹ�ʡ�٤��礭���夬��櫓�ǤϤʤ���
�����ϡ��ѥå��֤ǥ����ƥޥƥ��å���������Ǥ����Ǥ⾡�Ԥ���ά�Ǥ��뤳�Ȥ��������Ƥ�����
����39�ϡ�����Τ�
��Ϣ����
���������ɥ��ߥå���
�ȥ졼����������å� ���ܺ�������ȸ�������Ź
Copyright (C) Pan Rolling, Inc. All Rights Reserved.