
|
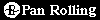
|
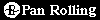 |
 『初心者がすぐに勝ち組になるテクナメンタル投資法』
『初心者がすぐに勝ち組になるテクナメンタル投資法』
2005年10月20日発売
ISBN4-7759-7058-5 C2033
定価本体2,200円+税
A5判 ソフトカバー 248頁
著 者 エリス・トラウブ
訳 者 関本博英
 エリス・トラウブ(Ellis Traub)
エリス・トラウブ(Ellis Traub)
「本書にはすべての投資家に興味のある投資原則が示されているが、特にNAICの投資法を実践している投資家には参考になるだろう。高成長を持続する優良株の長期ポートフォリオを組成するとき、本書が大きな力となる」――バリューライン・パブリッシング社のスティーブ・サンボーン・リサーチ担当取締役
「エリス・トラウブ氏は長期投資家にとってなくてはならぬ存在である」――株式コラムニストのキャンディス・キング氏
「成功の実証に裏付けられた投資法と投資原則をマスターするまでの、ひとりの男の素晴らしい旅の物語である」――トーマス・オハラNAIC理事長
「トラウブは本書のなかで、ファンダメンタルズアプローチで有望株を発掘するというNAICの投資手法を分かりやすく紹介している」――NAICのケネス・ジャンキー社長兼CEO
■目次
訳者まえがき 1 謝辞 5 序文 なぜこの本が必要なのか 9 第1章 私のプロフィール 17 私が犯した間違い 第2章 なぜ株式投資なのか 23 お金とは何か、そしてそれをどのように得るのか/起業/株式の所有/なぜ長期投資なのか/退職しても永遠の長期投資家 第3章 間違った常識を捨てよう 41 だれでも株式投資で成功できる――ピーター・リンチ/NAICもこれを実証 第4章 専門用語を知る 49 知らなければならないこと/株券/損益計算書/バランスシート(貸借対照表)/PER(株価収益率)/「その他の20%」 第5章 企業の成長とは何か 71 売上高の伸び/利益の成長 第6章 投資銘柄を見つける 79 大切な原則/投資信託はどうか/投資銘柄を見つける/どこに目を付けるのか/投資企業をどこで見つけるのか 第7章 企業の質を評価する 101 チャート/企業の成長チャート/成長の分析/実際の応用/成長の条件/すぐにできる 第8章 成長の具体例 123 チャート/実例 第9章 経営陣の成績表 139 売上利益率/実例 第10章 株価を評価する 149 株価評価のプロセス/リターンとリスク/実現可能なリターンの計算/予想成長率/買いか、見送り/妥当な株価 第11章 企業を比較する 177 企業比較ワークシート/比較する企業の選択/結果の分析 第12章 ポートフォリオマネジメント 185 ポートフォリオマネジメントとは何か/ポートフォリオの規模/売り時の決定/ディフェンシブな戦略/攻撃的な戦略 第13章 参考事項 205 特殊な業種のデータ/企業の質の評価/価値の評価 結論 219 付録A 参考指標 221 付録B パソコンユーザー向けの参考資料 226
本書の「テクナメンタル投資法(Technamental Investing)」はこのNAICの投資手法をベースとしたもので、ファンダメンタルズ(fundamentals)のテクニカル分析(technical analysis)という意味合いで名付けられた。その特徴は、①ファンダメンタルズ分析をベースとした気楽な長期投資、②注目するのは企業の業績チャートであって、株価や出来高のチャートではない、③年間15%のリターンを上げ、5年で資金を2倍にする――というものである。
この投資法では「ファンダメンタルズ情報は四半期に1回しか発表されないので、短期的な株価の変動はこうした企業のファンダメンタルズを反映したものではない。株価は利益のトレンドを反映しているので、利益成長の続く優良株に長期投資する」という考え方が基本になっている。こうした考え方にはもちろんテクニカル分析投資家からの反論もあるだろうが、特に投資の初心者にとってはあまり抵抗なく入っていけるオーソドックスなアプローチであろう。
わが国には1400兆円もの個人金融資産があるといわれるが、その多くは相変わらず預貯金に退蔵されている。401kを例に出すまでもなく、個人も自分の資産は自分で運用しなければならない時代に入ったのに、日本ではいまだにリスク=危険=博打といった考え方から抜け出せていない。個人の健全な投資教育の必要性がますます高まっている現在、本書がその一助となれば訳者として望外の喜びである。 投資教育の基礎編テキストともいえる本書の邦訳を決定された後藤康徳(パンローリング)、今回も編集・校正ではいろいろとお世話になった阿部達郎(FGI)の両氏には感謝いたします。
関本博英
こうした状況は投資家たちに大きなショックを与え、株式市場に参加していた多くの投資家は環境悪の前に株式投資に怖気づくようになった。そして大きな損失を被った新しい投資家たちは株式市場という戦場からよろよろと撤退し、もう二度と株なんか買うものかと心に誓っていた。本書の第一版が刊行されてまもなく、私は光栄にも米個人投資家協会(AAII)が主催する株式コンテストに参加するよう要請された。このコンテストは3人の著名なプロを互いに競わせる定例の催しで、各参加者は10万ドルを6カ月間運用してその成績を競い合う。私は参加を要請されたが、①自分は株式のプロではない、②長期投資家の成績を評価するのに6カ月という期間は短すぎる――という理由からあまり気乗りしなかった。しかし、①長期投資のメリットをPRする、②こうした短期投資の成果については保証できない――という隔週ごとのコメントを発表するという条件付きで参加を受諾した。その結果はおもしろいものだった。私は14銘柄に投資して6カ月間ホールドしたところ(そのうちの1銘柄は乗り換えすべきだったかもしれないが、そのままホールドした)、その利益はプロたちの成績ばかりでなく、S&P500のリターンも何と20%以上も上回ったのである。もちろん、これは私がラッキーだったこともある。短期的には大きな評価損が出たこともあった。私は本書に詳述した投資原則に従って優良企業の株式だけを購入・ホールドしたが、プロたちは劣勢を挽回しようと頻繁に売買を繰り返し、結果的には逆効果になってしまった。
私は何も自慢をするためにこうした話をしているのではない。これと逆の結果になる可能性もあったからである。私が言いたいのは、①株式投資で成功するのに何もプロになる必要はない、②第一版と本書刊行の期間中に起こったすべての出来事は、本書で述べられている素晴らしい投資原則を実証している――ということである。株式相場は市場参加者のさまざまな思惑を反映して常に変動しているが、そうした思惑売買をしたり、短期トレードを繰り返している人々はあまり儲けていないようだ。一方、優れた企業は長期的に利益を上げ続けるので、そうした企業の株式を保有するという投資の基本原則を守っていれば、株式市場でどのような事態が起ころうとも、最終的には利益を手にできるだろう。この改訂版でもこの基本原則はまったく変更していない。それは時代を超えた真理であるからだ。この新版では現在の株式市場の状況を反映するように多くの事実を更新するとともに、旧版の刊行以降に起きたさまざまな出来事から得られた教訓を盛り込んだ。
本書にほかの投資本と異なる何か優れた点があるとすれば、それは何だろうか(読者の気を引こうとさまざまな工夫を凝らしている投資本は書店にあふれている)。そのひとつは、皆さんにはあまり耳慣れない「テクナメンタル投資法(Technamental Investing)」というものである。この投資法のユニークさはこの名前からもお分かりであろう。この投資法はほぼ半世紀にわたり、500万人以上の投資家が実践して大きな成功を収めた原則に基づいている。この投資原則はNAICの設立者であるジョージ・A・ニコルソン、トーマス・E・オハラおよびフレデリック・C・ラッセルなどによって考案され、その後も熱心なボランティア会員たちの尽力で今では全米のみならず、全世界にも普及しつつある。 このテクナメンタル投資法は「グロース/バリュー投資法」「長期投資」「ファンダメンタルズ投資法」「バイ・アンド・ホールド」、あるいは単に「NAICの投資法」などとも呼ばれ、NAICでもこの投資法の名称は決めていない。しかし、こうした投資法の名称はこのテクナメンタル投資法の一面を言い表している。私はこの投資法の本質をよく表しているという理由で、「テクナメンタル投資法」という名称を使った。われわれがしていることにはやはり名称が必要であるからだ。
投資界ではファンダメンタルズ分析とテクニカル分析を天と地ほどの差があるとして、この2つをはっきりと区別している。テクニカル分析では株式相場全体と個別銘柄の値動きや出来高をグラフに表し、視覚的に分析する。株式投資で成功しようとする多くの投資家や学者たちはこれまで、過去と将来の値動きに共通する株価と出来高のパターンを探し求め、それらにいろいろな名称を付けてきたが、あまり成功していない。私に言わせると、(ストキャスティクス、モメンタム、移動平均など)数多くのテクニカル手法のどれかが有効であるとすれば、そのなかのひとつだけであるはずだ。
一方、ファンダメンタルズ分析は(業績や財務状態など)企業のファンダメンタルズを分析するもので、売上高、利益、売上利益率などいわば企業の生命力であるこれらのファンダメンタルズが変化すれば、その株価にも大きな影響を及ぼす。これらファンダメンタルズのデータは簡単に入手・分析することができ、将来の株価を占ううえで大きな価値を持つ。テクナメンタル投資法でもチャートと視覚的な分析を使うので、この領域はテクナメンタル投資法のテクニカルな分野とも言えるだろう。チャートは数万語の言葉や数字にも勝るので、ファンダメンタルズ分析にとっても便利である(平均的な投資家にとって、こうした点がテクナメンタル投資法の理解を難しくしているのかもしれない)。本書ではさまざまなファンダメンタルズについて、小学生や老人でも理解できるように分かりやすく説明した。つまり、分かりにくいところを視覚化することでテクナメンタル投資法を説明するように心掛けた。
本書の二番目の特徴は、すでに成功が実証された素晴らしい投資原則を簡単に分かりやすく説明したおそらく最初の本であろうということである。投資(株式市場のお金を儲けること)はまったく危険でも、厄介でもそして多くの時間がかかるものでもない。株式投資とはおもしろいものである。読者の皆さんは本書を楽しく読むことで、株式投資で成功する方法をマスターされるだろう。
1951年に設立された非営利団体のNAICが、自らの活動をあまりPRしないのは世界の七不思議のひとつであるといっても過言ではない(NAIC自身に代わって私がPRしてやろうと思う)。全米に100以上あるNAIC支部のボランティア会員たちは、毎年全国各地で数千回もの催しを開催している。しかもその目的は株式投資を怖がっている人たちに、そんなことはない、自分でちゃんと買うべき株式と保有期間を決められると教えていることである。
株式専門メディアがNAICのこうした献身的な活動について、ほとんど報じないというのはちょっとした驚きである。NAICの投資法やその活動について大々的に報道されると、多くのプロたちは飯が食えなくなるであろうことを考えると、それも分からないではない。ピーター・リンチがベストセラーの『ピーター・リンチの株式投資の法則』(ダイヤモンド社)のなかでNAICの活動について触れたり、ビアーズタウン・レディーズ(イリノイ州の小さな町の女性で作った投資クラブ)が派手にNAICのことをPRしないかぎり、ミシガン州マディソンハイツのNAIC本部の電話が鳴り続けることはほとんどない。NAIC各地支部が無料またはかなりの低料金で毎月実施している催しについて、一般のマスコミが報道することはまずない。
私はテクナメンタル投資法の哲学を知ることができたという点でNAICには深く感謝しているが、NAICがこの投資法に対する私の解釈やアプローチを支持または賛同しているとは思っていない。しかし、NAICがわれわれ(「われわれ」とは私の会社であるインベストウェア(Inve$tWare)社のこと)に公認ソフトの開発とそれによるテクナメンタル投資法の電子的な運用法を委託したことは、NAICが私の投資手法をある程度是認していると解釈している。私は人生に大きな価値を与えてくれたという点でNAICには本当に感謝しており、本書がNAICに対する投資家の関心を集め、ボランティア会員の皆さまの地位向上にお役に立てればと願っている。
テクナメンタル投資法をマスターし、本書に書いてあることを実践するベストの方法は、NAICの会員になることであろう。NAICは株式市場から自分で利益を上げたいと思っている人々には限りない支援を行っている。しかし、私は皆さんが教えられたことをすべて鵜呑みにしてはならないと思う。確かにNAICの投資法を忠実に実行すれば、投資した5銘柄のうち4銘柄は勝ち組銘柄であり、5年で投資資金を2倍にすることができる。これはすでに実証済みの事実であり、NAICの投資パフォーマンスの目安となっている。しかし、私は皆さんが本書に書いてあることを自分の論理と常識に照らしてよく考えてほしいと思う。ここに書いてあることは自分にとって本当に意味のあることなのかと自問してほしい。そうすれば、皆さんの考え方と合わない部分もあるだろう。本書の内容が皆さんの考え方と大きな違いがないことを確認してはじめて、自分でNAICの投資法を実行してほしい。 皆さんは本書から大きな刺激を受けるだろう。第1章では大学をドロップアウトし、株式の専門知識もない私のような者がなぜこのような本を書くまでになったのかという経緯である。第2章からは本論に入り、株式投資の有利さとその理由について説明する。第3章では株式投資はだれにでもできる、すなわちテクナメンタル投資はだれでも実行できること、続く第4章では皆さんが知らなければならない10項目について説明する。第5章ではテクナメンタル投資法のベースである企業の成長とは何かを検討する。第6章では投資銘柄の見つけ方とその選択法、投資銘柄に含める株式と除外する株式について説明する。第一版が刊行されてから現在までに多くの変化が起こり、特にインターネットとデータの入手・利用法は激変した。
第7〜8章では投資する企業はその必要条件を十分に満たしているのか、すなわち投資の条件となる企業の成長について詳述する。第9章では経営陣の成績表、すなわち右肩上がりの業績を維持する経営者の能力について分析する。ただし、投資企業の質を分析することは最も重要であるが、値段が高すぎる株式への投資は避けるべきである。第10章では投資する株式の実現可能なリターンと潜在的リスクの分析、適正な株価などについて述べる。第11章ではポートフォリオに加えるベストの企業の比較分析、第12章ではポートフォリオマネジメントについて説明する。そこで述べる簡単なディフェンシブと攻撃的な戦略を駆使すれば、一部の保有株に不測の事態が起こってもポートフォリオ全体はそれほど大きな打撃を受けず、最大のリターンを得ることができるだろう。最後の第13章では必ず必要というわけではなく、また混乱や誤解を引き起こす恐れがあるという理由から詳しい説明を省略してきた事項について触れる。それらは株式投資のレベルアップに役立つと思うが、それを利用するときは細心の注意が必要である。
参考指標と題する付録Aは第一版に対する読者からの要望に応えたもの、付録Bではテクナメンタル投資法を実行するためのパソコンソフトを紹介した。この種のソフトは旧版の刊行以来急増したが、使用する価値のあるソフトだけについて簡単に解説した。第一版が刊行された当時、自分でパソコンを所有または利用している人もかなりいたが、そうでない人も少なくなかった。しかし、現在ではほとんどの読者がパソコンを使っているだろう。本書で述べた投資法はいまだに鉛筆、定規、電卓しか使えない人々でも実践できるが、こうした投資支援ソフトについてはこれまでほとんど触れなかった(これに関する問い合わせは「etraub@financialiteracy.us」まで)。テクナメンタル投資法に関するこの序文は、皆さんにとって株式投資という楽しく有益な冒険のきっかけになったと思う。皆さんが自分の足でこの冒険の第一歩を踏み出すことを願っている。