
|
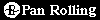
|
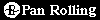 |
著 者 ダニエル・クロスビー
監修者 長岡半太郎
訳 者 井田京子
2020年6月発売/四六判 368頁
定価 本体2,800円+税
ISBN978-4-7759-7266-3 C2033
トレーダーズショップから送料無料でお届け
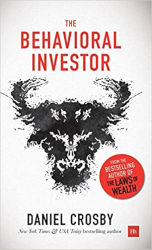 ブリガム・ヤング大学とエモリー大学で学んだ心理学と行動ファイナンスの専門家で、市場心理にかかわる研究を金融商品の開発から証券の選択にまで応用している資産マネジャー兼ノクターン・キャピタルの創設者。行動ファイナンスの最前線で活動し、ハフィントン・ポスト紙やリスク・マネジメント誌に寄稿し、ウエルスマネジメント・ドット・コムやインベストメント・ニュース紙では毎月コラムを執筆している。博士は、モンスター・ドット・コムで「注目すべき12人の思想家」の1人に選ばれたほか、AARPの「読むべき金融ブロガー」やインベストメント・ニュース紙の「40歳未満のトップ40人」にも選出されている。趣味は、映画鑑賞、セントルイス・カージナルスの熱狂的ファン。妻と3人の子供がいる。著書に『ゴールベース資産管理入門』(日本経済新聞出版社)がある。
原題:The Behavioral Investor
ブリガム・ヤング大学とエモリー大学で学んだ心理学と行動ファイナンスの専門家で、市場心理にかかわる研究を金融商品の開発から証券の選択にまで応用している資産マネジャー兼ノクターン・キャピタルの創設者。行動ファイナンスの最前線で活動し、ハフィントン・ポスト紙やリスク・マネジメント誌に寄稿し、ウエルスマネジメント・ドット・コムやインベストメント・ニュース紙では毎月コラムを執筆している。博士は、モンスター・ドット・コムで「注目すべき12人の思想家」の1人に選ばれたほか、AARPの「読むべき金融ブロガー」やインベストメント・ニュース紙の「40歳未満のトップ40人」にも選出されている。趣味は、映画鑑賞、セントルイス・カージナルスの熱狂的ファン。妻と3人の子供がいる。著書に『ゴールベース資産管理入門』(日本経済新聞出版社)がある。
原題:The Behavioral Investor
第1部 行動科学的投資家
第1章 社会学
第2章 投資と脳
第3章 生理学
第2部 投資家心理
第4章 エゴ
第5章 保守主義
第6章 注意
第7章 感情
第3部 行動科学的投資家になる
第8章 行動科学的投資家はエゴを克服する
第9章 行動科学的投資家は保守主義を克服する
第10章 行動科学的投資家は注意バイアスに惑わされない
第11章 行動科学的投資家は感情を制御する
第4部 行動科学的投資ポートフォリオを構築する
第12章 第三の方法で投資する
第13章 行動科学的投資はルールに基づいている
第14章 行動科学的投資はリスクを考慮する
第15章 行動科学的投資には達人はいない
第16章 行動科学的投資の要素の一例
あとがき――成功を手にする
さて、投資戦略選択の際に合理的であろうとすれば、先人の知恵や自己の経験に基づく裏付けがあり、理論的に妥当な説明が可能で、将来にわたって再現性が高いものを選択したいとだれしも思うだろう。そのためには、自身の可謬性や限界を謙虚に認めるとともに、投資エコシステムの構成要素である、①投資対象(企業、発行体、商品等の本質的価値や成長性)、②市場のメカニズムや構造(複雑性、非線形性、ランダム性等)、③取引に参加する主体である人間――を理解することが欠かせない。
これまでの多くの投資関連書籍が前二者については詳しく書いてきたし、すでに広く啓蒙が進み、投資家の理解も深くなってきている。しかし、取引を行う人間そのものの理解に関しては、それを解説した文書もあまりないし、投資やトレードの意思決定過程において人間がかかわることの影響に気づいている人はかなり少ない。
その原因の一つは、人間を理解するための学問領域が多岐にわたり、包括的に説明できる専門家が少ないことにあるが、行動ファイナンスの専門家である著者は人間の行動を体系的に説明しようとする諸科学を使い、社会的な存在である人や、生物(種)としてのヒトの投資における振る舞いを分かりやすく説明することに成功している。本書によって、私たちは投資家としての自己の弱さを克服する方策を見つけることになるだろう。
翻訳にあたっては以下の方々に感謝の意を表したい。まず井田京子氏には読みやすい翻訳をしていただいた。そして阿部達郎氏は丁寧な編集・校正を行っていただいた。また本書が発行の機会を得たのはパンローリング社社長の後藤康徳氏のおかげである。
2020年5月
長岡半太郎
ダニエル・クロスビー博士との付き合いは、二〇一二年に彼が私の会社で「行動アルファ」(顧客が正しい行動をするためのコーチングを受けたこことによって得られた超過パフォーマンス、金融顧問にとって計測が難しい)をとらえるための枠組みを作る手助けをしてくれたことから始まった。この試みが成功したことで、私たちはさらに行動ファイナンスを活用すべくクロスビー博士と提携して、顧客の五〇%が正式な金融アドバイスを受けてもそれを守らないという問題を解決するために、「ザ・センター・フォー・アウトカム」という教育的な取り組みを始めた。結局、アドバイスはきちんと従ってくれなければ良いアドバイスにならないからだ。
本書で紹介するアイデアは、心理学を長年にわたって仕事に応用してきた経験と、心理学の知識に基づく投資に関する文献を包括的に見直すことから生まれた。投資家の最大の敵である自分自身から身を守るためには、理論と実習を組み合わせることが不可欠なのである。
私は、本を読み始めたときの、未知の世界に足を踏み入れる感じが大好きだ。これからどんな新しいことと出合えるのだろうか。それまで後生大事にしてきた考えに疑問を持つことになるのだろうか。自分の生き方を変えるような情報に出合えるだろうか。投資本には、既存のアイデアを焼き直しただけのものが多いが、本書は投資のまったく新しい計画とパラダイムを紹介している。
クロスビー博士がこれから案内してくれる世界は、広くて驚きに満ちていて、時に奇妙に感じるかもしれないが、どのページからも得るものは多いと思う。本書には、サルと金融市場を比較するときも、ドイツの破壊される村と人間の現状肯定の傾向を比較するときも、複雑なことを理解しやすくする工夫がある。博士は、人間の行動という入り組んだ迷路を案内する優れた案内人であり、本書を読めば人について理解しないかぎり、市場を理解することなどできないということを深く知ることになるだろう。
博士は、私たちの脳が比類ない精巧な器官であるにもかかわらず、長期投資には情けないくらい適していないことを科学と歴史の助けを借りて明確に示している。私たちは、地球上で最も進化した種であるにもかかわらず、現代の生活のニーズに対する準備がまったくできていないのだ。しかし、本書を読めば、そう悲観することもないことが分かるだろう。私たち人間の欠陥を紹介しているのは、私たちが簡単に陥る心理的なワナを回避するための解決策を示すためなのである。
本書は、ユーモアと知恵と何よりも情熱を持って、私の財布だけでなく人生を豊かにするたくさんのアイデアを与えてくれる。最高の投資本は、どれも自分自身を正しく知らなければ富を増やすことはできないということを理解したうえで書かれている。そして、本書は金融の世界におけるこの新しくて正しい理解の仕方のモデルと言ってだろう。
本書は、読者に考えさせたり、問いかけたり、時には笑わせたりするまれな金融書である。あなたもきっと私と同じくらいこの本を楽しむとともに、影響を受けるだろう。
ノリーン・D・ビーマン(ブリンカー・キャピタルの最高経営責任者)
この目的を達成するため、本書ではポートフォリオの構築について具体的に書く前に、人間の性質について全体的におさらいしていく。人がなぜこれまでのような判断を下してきたのかを深く理解しなければ、どのように投資すべきかのヒントを得ることなどできないからだ。本書は次の四部で構成されている。
富について真剣に考えると、経済的な幸福だけでなく、それと同じくらい心理的な幸福がかかわっていることが分かる。本書を読むことで、富という言葉を総体的にとらえることを学び、その知識がリターンを改善するだけでなく、パーティーで人気者になる助けにもなればうれしい。
より良いものを求めて
C・ダニエル・クロスビー博士
あなたは今、豪華な旅客機のファーストクラスに座っているとする。もう時機を逸した休暇をとってハワイに向かっているのだ。連日遅くまで休まず働いてきたあなたは、席にもたれて客室乗務員からシャンペングラスを受け取り、首から肩にかけて緊張がほどけていくのを実感している。しかも、隣の席についた魅力的な異性が、最初のありきたりな世間話を飛ばしていきなり真剣な話を始めたため、離陸からの時間はあっという間に過ぎていった。
一時間ほど飛行したところで、飛行機は乱気流に巻き込まれたが、それも悪くない。手すりを握りしめた手が偶然触れ合ったのだ。二人で笑えば恐怖は消えるが、機体の揺れはなかなか止まらない。これは普通の嵐ではないのではないかとあなたは心配になってきた。機内を見回すと、忙しそうに動きまわる乗務員も心なしか心配そうな顔をしている。風や雨はだんだん激しくなり、揺れるたびに吐き気が襲ってきそうになる。経験豊かで安全な飛行を心掛けてきた機長の声も、恐怖に震えている。機体が傾いて振動しめたとき、機長が叫んだ。「頭を下げて衝撃に備えてください」
気がつくと、約一〇〇メートル先に焦げた機体の破片があり、周りを見回しても生存者はだれもいない。最悪の状況だ。あなたは頭を抱えた。何が起こって「これからどうなるのか」について、さまざまなシナリオが頭の中を駆け巡っている。しかし、すぐに聞きなれない音がして、思考は中断された。
キッ、キッーーー、バタン!
新たな状況に目を凝らしていると、騒音の元が分かった。音は「アトランタ動物園所有」と書かれためちゃくちゃに壊れたおりから発していた。しばらくすると、おりの主が分かった。アンゴラコロブスというサルだった。
思考実験を続けよう。捜索隊が飛行機が墜落した手つかずの島を見つけるまでに一八カ月かかったとしよう。唯一生き残ったあなたとサルはそれまで自力で生き延びなければならない。救助隊が到着したときに、あなたとサルのどちらが元気でいるだろうか。自分に正直になれば、何もない場所に投げ出されたとき、あなたや私よりもサルのほうが生き延びる可能性はずっと高いと思う。救助隊が到着したときに、あなたは干からびた骨になっていても、サルは遠足の子供たちにからかわれることもなくなって、力強く幸せに暮らしているかもしれない。
ユヴァル・ノア・ハラリが、TEDxの「天国のバナナ」(二〇一四年)という素晴らしい講演でさらにあり得ないケースについて言及している。仮に飛行機に一〇〇〇人のヒトと一〇〇〇匹のサルが乗っていて、全員が生き残り、孤島で生きていかなければならなければならないとする。一年半後に救助隊が到着したときの結果は同じだろうか。おそらく違うだろう。二つ目のシナリオでは、偉大な社会と機能する資本市場の両方を構築する能力というヒトの強みが発揮されるからだ。これは、柔軟に共同する能力である。
ハラリは、ミチバチやアリのように共同できる動物がほかにもいることはもちろん認めているが、これらの動物は固定的で階層的なことしかできない。ハラリの言葉を借りれば、ミツバチは女王バチを殺してミツバチ共和国を設立したりすることはおそらくしない。ミツバチもアリも偉大な仕事をしているが、認知的柔軟性がないため、食物連鎖の上位に行くことができないのである。一方、サルは知能が高く、複雑な社会構造を持っているが、意味のある交流ができる個体数は限られている。心理学者は、その数をヒトならば一五〇人としている。これは霊長類の兄弟を評価するうえで役立つ基準だ。集団が約一〇〇匹になると、サルは仲間のことを十分理解して相手の行動や性格や意図を判断できなくなるため、サルの文明の規模と複雑さは実質的に制限されることになる。
もしミツバチが先天性の指令によって組織され、密接な社会的相互作用のなかで単純な作業をこなしているのならば、動物界の奇跡とも言えるヒトの優位性は、ソーシャルナラティブ(社会が求めるストーリー)に従って行動する傾向があったおかげと言える。乱暴な言い方をすれば、世界は私たちが作ったストーリーであり、私たちはそれがあたかも現実であるように行動しているのである。ハラリが偉大な著作『サピエンス全史』(河出書房新社)で述べているように、「私たちが知るかぎりで、サピエンスだけが見たことも、触ったことも、臭いをかいだこともない存在について語ることができる」のである。サルは「川の近くにトナカイがいる」ということは伝えられても、「川の近くにいるトナカイはこの町の守護神だ」と伝えることはできないのだ。
この実在しないことを伝えることができる能力によって、ヒトは予想可能な行動を起こし、確実な信頼を育てるさまざまな社会構造を作り上げた。アラバマ州、カトリック教会、アメリカ合衆国憲法、不可譲の公民権などは、どれも厳密に言えば実在しないが、みんなが同じ考えを信じ、それがあたかも現実であるかのように行動することで、相互信頼が浸透した秩序ある文明を生み出しているのである。
このようなフィクションの集合体を形成し、受け入れる能力があるから、「……サピエンスが世界を支配するようになり、アリは私たちの残飯を漁り、チンパンジーは動物園に閉じ込められているのである」。
ヒトが信頼を共有する機能によって種としての支配を勝ち得た私たちの社会において、極め付きのフィクションがお金である。ハラリは容赦しない。「お金は、信頼の共有が生み出した最も普遍的かつ効率的なシステムである」。私たちが日々苦労したり、夢見たり、悩んだりしている紙幣はただの紙切れで、元々の価値はない。お金や資本市場はみんなで共有する幻想で、その価値は物理的というよりも心理的なものである。金融市場はヒトの頭の中で作り上げたものであり、その起源を適切に理解せずに市場を理解しようとするのは極めて愚かなことなのである。ヒトを理解しなければ、市場を理解することはできないということだ。
子供が誕生すれば眠れない夜が続き、お金持ちになれば欲張りな遠い親戚が現れるなど、人生に単純に良いだけのことはあまりない。同じことは、ヒトの偉大な才能についても言える。物語の共有によって株式市場を生み出しても、劣った判断しかできないこともあるからだ。ヒューゴ・マーシアとダン・スペルベル共著『ザ・エニグマ・オブ・リーズン(The Enigma of Reason)』によると、人の動機は厳密に言えば世界において「正しく」あるためではなく、私たちの種が繁栄するための基盤となっている共有の考えを安定させるために進化していった。
この概念をさらによく理解するために、動物とヒトの信念を試したとしよう。ヒトが深く信じていること(例えば、「私が支持する政党の議員は賢くて親切だ」)と逆のことに出くわすと、認知的不協和が生まれて苦しむことになる。そして、大事にしてきた概念に反する証拠は、たとえ客観的で納得しやすいことであっても(政策の失敗、無能なリーダー、党路線が科学的に矛盾するなど)、政治理念はなかなか変わらない。共有の信念はヒトを結束させる接着剤の役目を果たしており、たとえ矛盾に直面しても、これを引きはがすのは簡単ではないのだ。ある政党を熱狂的に支持する人が考えを変えると、大きな社会的コストがかかる。人間関係をなくし、社会的な絆を断ち切り、「自分は間違っていた」という現実に直面せざるを得なくなるといったことだ。この心変わりは、たとえ論理的なことでも、私たちを実際にむしばみ、それこそが私たちをヒトたらしめているのである。
しかし、ガゼルの場合、「この辺りにはライオンはいない」と考えていたとしても、茂みがカサカサ揺れたら、襲われないように即座に逃げ出す。動物は、事実を伝えることしかできないため、判断も二択で――ライオンがいるのかいないのか、逃げて隠れるのか逃げないで食べ続けるのか――文字どおりの意味しかないのだ。
ヒトはより複雑な思考ができるため、かなりの自己欺瞞や不合理なことも受け入れることができる。しかし、もしヒトのような理由付けができるガゼルがいれば、茂みでカサカサ音がしてもライオンがいるわけがない理由をたくさん考えている途中で食べられてしまう。つまり、客観的な理由付けをする能力が不十分だと子孫を残すまで長生きができないため、ガゼルは二択の判断によって個体数を維持しているのである。
しかし、ヒトは違う。集団主義と過度なうぬぼれがむしろ繁殖力を強めているのだ。私たちはグループ内の忠誠を何よりも大切にしているにもかかわらず、自己権力を拡大し、「ほかの人たち」を軽視し、科学を無視するタイプが権力を握る地位に就いて、ほかの人たちの尊敬を得ることもある。先の『ザ・エニグマ・オブ・リーズン』の著者たちも、「『知的』な観点からは奇妙だったり、愚かだったり、ただの愚かに見える脳の癖が、社会的「相互作用」の観点からは、やり手に見える場合がある」と書いている(Elizabeth Kolbert, 'Why facts don't change our minds' The New Yorker [February 27, 2017])。
一九八八年に発行された『ホーキング、宇宙を語る』(早川書房)のなかで、故スティーブン・ホーキング博士は、世界とは何なのかを知りたいという人間の要求と、その探求においてときに偽りの特性を見つけてしまうことを象徴する有名な話について書いている。
「あるとき有名な科学者が、一般向けに天文学の講演を行った。彼は、地球が太陽の周りを回り、その太陽は星の巨大な集合体であるわが銀河の中心を回っていることを説明した。公演が終わると、後ろの席に座っていた小柄な老婦人が立ち上がって言った。『あなたの言うことはバカげてますよ。世界は本当は平たい板のようなもので、それが大きな亀の背中に乗っているのですから』。科学者はとびきりの笑顔を見せてから、『それでは、その亀は何に乗っているのですか』と尋ねた。老婦人は平然と答えた。『若いのに頭がいいわね。亀に乗っているのよ。どこまで行っても亀の下には亀がいるのよ』」
科学者や神父や哲学者は、大昔からさまざまな根源的原因を探し続け、その過程は完璧ではないものの、長期的に見ればいくつかの素晴らしい発見をした。古代の錬金術について考えてみてほしい。今日、私たちはこれを卑金属を金に変えようとする強欲な試みだったと間違って解釈しているが、彼らの本当の目的は「一番下の亀」を探すことだった。ルイス・トーマスは『レート・ナイト・ソーツ・オン・リスニング・トゥ・マーラーズ・ナインス・シンフォニー(Late Night Thoughts on Listening to Mahler's Ninth Symphony)』のなかで次のように書いている。
「錬金術は大昔に、世界が理にかなっているかどうかを知りたいという人間の最も深くて最も古い願いをかなえるために始まった。このときの前提――地球上のすべてのものは一つの根本的な物質からできている――が、すべての原型となる物質を探し出し、それを錬金術師が望む形に加工するという何世紀にもわたる多大な努力につながった。もしそれができれば、人間はすべてを手に入れることができるからだ」
この最も広い意味で金融にかかわっていた人たちは、みんなある意味において錬金術師であり、市場で起こる現象の根源的原因を探し求めていた。
資本市場の永続的な真実の探求は、単なる哲学的な探求ではなく、むしろその逆である。何(この場合はだれ)が市場を構成しているのかを理解することは、よりより投資に必要な最初のステップなのである。初期のころの原子は、小さい玉軸受に似た硬い閉球のようなものだと思われていた。そのあと、これは分割することができないという理解に至ったが、亜原子粒子の存在が分かり始めたときでさえ間違っていた。電子は最初は、太陽系の惑星模型のように正電荷のなかを漂っていると考えられていた。また、宇宙は基本的に小さい宇宙で構成されていると考えられていた。これは、秩序と対称性を求める人間にとって魅力的で美しい考え方だが、説明や予想のためのモデルを構築するには悲しいほど役に立たない。
原子の初期の研究と同様に、金融市場の研究もかつては現実の世界への適用性よりも数学的な美しさを優先して理論を順守しようとする人が多かった。伝統的な金融の枠組みは、市場参加者が「合理的」だという考えに基づいている。この合理性には二つの主な特徴がある。一つ目は、合理的な市場参加者は新しい情報を即座に入手することができ、入手するとすぐに考えが更新されるということで、二つ目は合理的な市場参加者はSEU(主観期待効用)と整合性がある判断を下すということだ。SEUは、L・J・サバージが一九五四年に発表した『ザ・ファウンデーションズ・オブ・スタティスティックス(The Foundation of Statistics)』のなかで説明されている。サバージは、私たちが与えられた選択肢に対する個人的な効用を大きくして、対象の出来事が起こるまたは起こらない確率に合わせてその選択肢を加重しているとしている。
もし新古典派経済理論の例外を守れば、ある種の高貴な人になれると考えると励みになる。そうすれば、長く健康でいられるし、賢くて体にも良い選択をすることができる。例えば、株式市場では、自分の目的とニーズに合わせた長期的な見方を優先し、株式市場の日々の変動を無視するとよい。また、政治家を選ぶときには部族主義や先入観に惑わされずに、最大の利益を目指し、事実や細かい違いに目を向けて語る人に投票するのだ。人類にはそこまで気高くあってほしかった。しかし、人とマーケットのこのモデルは原子を理解するのにそれを小さな惑星に例えた概念と比べても、同じくらい記述的であり予測力を持つという効用がある。そのため、実際の私たちはパニックを起こし大きな群衆となって人間の良いところではなく、最悪の部分を拡大するリーダーを選んでしまうのである。
私たちは、原子そのものを見ることができなければ、原子の力を本当に活用することはできない。市内を明るく照らしたり全体の水準を上げたりできるようになったのは、原子分析のエレガントなモデルを捨てて、より精密なモデルを選んだからなのだ。同様に、市場を動かしている人間の本質を考慮しないで市場を理解しても、あまり役には立たない。原子は物質の基本的な単位で、細胞は生物の基本的な単位で、単語は言語の基本的な単位である。そして、人間は市場の基本的な単位なのである。
次の章では、人間という動物が投資の意思決定を下すことについて、生物的・神経的・心理的観点から見ていく。これを読むと、きっと驚き、面白いと感じると思うが、なかには動揺する人もいるかもしれない。それでも、このような考え方に深くかかわることでのみ、自分自身を知り、富を増やすことができるようになるのである。