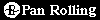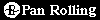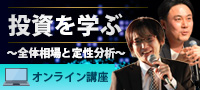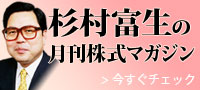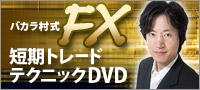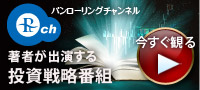|
足立武志
|
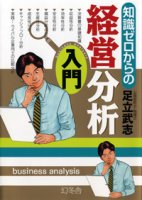 公認会計士、税理士、ファイナンシャル・プランナー(AFP)
公認会計士、税理士、ファイナンシャル・プランナー(AFP)
株式会社マーケットチェカー取締役 1975年生まれ 神奈川県出身
一橋大学商学部経営学科卒業。資産運用に精通した公認会計士として、執筆活
動、セミナー講師等を通じ、個人投資家が資産運用で成功するために必要な知識や情
報の提供に努めている。主な著書に、『知識ゼロからの経営分析入門』(幻冬舎)ほか多数
|
|
|
足立武志の「中長期投資家のための“超・実践的”ヒント集」
|
「木を見て森を見ず」 11月26日
「木を見て森を見ず」という言葉があります。これは、ものごとの一部分だけに目が行ってしまうと、ものごとの全体を見失ってしまう、という意味です。
株式投資の世界でも「木を見て森を見ず」という言葉は良く使います。この場合、「木」とは個別銘柄のことを指し、「森」とはTOPIXや日経平均株価といった、株式市場全体の動きを示す指標を指します。
さながら、株式投資の世界では、個別銘柄の動きばかりにとらわれていると、株式市場全体の大きな流れをつかみ損ねる、といった意味合いでしょうか。
しかし、一概に「木を見て森を見ず」が良くないともいえないのが株式投資の面白いところでもあります。場合によっては「木を見て森を見ず」を実践することによって、将来の注目テーマや、今後上昇が期待できる銘柄・業種が見えてきたりするのです。
例えば、日経平均株価やTOPIXがバブル崩壊後の安値を記録したのは2003年4月でした。しかし、それより前の2002年11月に、非常に多くの中低位株が底入れを果たしていたのです。
現在も、日経平均株価やTOPIXは下落トレンドにありますが、かなりの数の新興市場銘柄や、一部の東証1部上場銘柄は、9月下旬もしくはそれ以前に年初来安値を付けており、すでに底入れを達成した可能性があります。ミクシイやドワンゴ、ぐるなびなどは、底打ち後11月には年初来高値をつけるまでに上昇しています。
もし、今後しばらくの間日経平均株価やTOPIXが下落を続けても、これらの銘柄は今後上昇トレンドになっていくことも十分に考えられるのです。
底打ちの時期が早い銘柄ほど、その後の上昇相場も早く始まります。2003年4月の日経平均株価・TOPIXの底打ち後の相場の中心は、2002年11月に大底を形成した中低位株でした。今回も、日経平均株価やTOPIXに先駆けて、新興市場銘柄や、一部の東証1部銘柄が底打ちしたとなれば、それらの銘柄は、これからのさらなる上昇が期待できます。
個別銘柄が、日経平均株価やTOPIXの値動きと連動しないケースは多々あります。こんなとき、「森」である日経平均株価やTOPIXだけをみて、「木」である個別銘柄に目を向けなければ、個別銘柄を歴史的な安値で買えるチャンスを逃すことにもなりかねません。
まさに「木を見て森を見ず」を実践する必要があるのです。
コメント投稿(0)
安値更新銘柄はまず損切り 11月08日
本日(2007年11月8日)の日本の株式市場は大きく下落し、年初来安値を更新した銘柄もかなりの数に上っています。
個人投資家が株式投資でつまずいてしまう最も多いパターンが「塩漬け株」を作ってしまうことでしょう。買った株の株価が下がっても損切りせずに放置した結果、どうにもならなくなってしまうケースは非常に多く見受けられます。最近でも、2006年初めのライブドアショックに端を発した新興市場株の急落で、買値の10分の1以下にまで下がった塩漬け株を仕方なく保有し続けている個人投資家も多いはずです。
このように、損切りを行い、塩漬け株を作らないことが、株式投資で成功するための必須条件だと思いますが、「安値更新」というのは、損切りをするタイミングとしては非常に分かりやすいものといえます。
「損切り」といっても、いったいどのタイミングで損切りしたらよいのか、なかなか判断できない方も多いでしょう。そこで、安値更新をサインとして、何も考えずにとにかく機械的に損切りしてしまうことも有効な方法の1つです。
株は、下がりだしたらどこまで下がるか全く予測がつきません。特に、安値を更新すると、下落の勢いがさらに加速して、あっという間に何分の1にまで株価が下がってしまうこともよくあります。
確かに、安値更新を合図に損切りしたら、次の日から逆に株価が上がってしまった、という場合もあるでしょう。しかし、そんな時はまた買いなおせばよいのです。損切りした売値より高く買うことになっても、それはそれでよいと思うのです。なぜならそれによって多少損をしても、致命傷にはならないからです。
株式投資で成功するには、致命傷になりうる「大失敗」を避けることが何よりも大事です。損切りしなかった結果、塩漬け株だらけになって、本当のチャンスのときに投資する資金がなく指をくわえてみている、ということだけは何としてでも避けるべきです。
コメント投稿(0)
ついに「円安バブル崩壊」となるか 11月07日
この時間、一気に1ドル=112円台にまで円高が進んできました。円高といえば、8月の急激な円高により、FX取引で大きな損失を被った投資家も多いことでしょう。現在は、そのときの反省から、あまり無謀なポジション(例えばレバレッジ20倍で有り金をすべてつぎ込むなど)をとる人は減ったようです。しかし、相変わらず高い人気は続いてます。
FX取引の落とし穴はなんと言ってもスワップポイントです。この存在により、どうしても円売り・外貨買いのポジション、つまり円安を目指すポジションしか組めない個人投資家が多いのです。確かに、円買い・外貨売りのポジションを組むと、スワップポイントにより金利差相当額を毎日支払わなければならないわけですから、抵抗はあります。
かといって、常に円売り・外貨買いのポジションで万事うまくいくわけではありません。ここ何年かの間、安定的に円安になっていたため、特に投資経験の浅い投資家は、長期的な円高になることもあると実感できていないようです。しかし、長期的な円安局面が今回訪れたのと同様、長期的な円高局面もいつかは訪れるのです。そうなれば、スワップポイントで得た金額など円高で簡単に吹き飛んでしまうでしょう。
主婦がFX取引で得た4億円の所得を脱税していたとか、国税庁の調査で、個人投資家がFX取引で得た所得として計224億円が申告漏れしていたなどという話もあります。個人投資家が大儲けした話が、普段資産運用をしない人まで広まってきたとき、それは「バブル崩壊」の危険信号になります。2006年初めのライブドアショックに端を発した新興市場バブル崩壊のときもそうでした。「新興市場株=儲かる」と多くの人が信じて疑わなくなったとき、その図式が崩壊するのです。
もちろん、将来どうなるかを予測することはできません。しかし、ここまで円安が進み、FX取引で何億円も稼ぐ個人投資家まで現れた現在、「円安バブル崩壊」がいつ訪れてもよいように、とりわけFX取引については厳格なリスク管理が必要なのではないでしょうか。
コメント投稿(0)
↑ページのトップへ
|
|
|
|