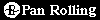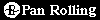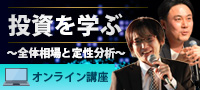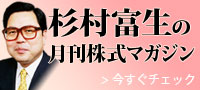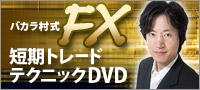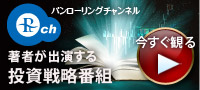|
���� �� �ΡֱѸ���ɤ߲������������ͻ�кѡ�
|
�ޥͥ����Ȥȥ�������åפΰ㤤 2007ǯ08��31��
��Ʊ���䤹���ȿ����Υ��ץ������Ǥ������֥ޥͥ����Ȥȥ�������åפ����Τ˰㤦�פȤ������Ȥ�ؤӤޤ�����
�ޥͥ����Ȥϡ���ʬ����֤ˤ����˵������褯Ư���Ƥ�館�뤫���ݥ���ȡ�
��������������åפϡ�������֤���ʬ���Ƥ⡢���ۤΤ���٤��Ѥ˰���ĥ�äƤ������Ȥ��Ǥ��뤫�ɤ��������ݥ���ȤǤ���
�����褦�ʥ��������Ѹ�Ǥ�������̣����Ȥ�������ȿ�ФǤ���
��ü����Ǥ��������˹Ԥ��Ȥ����Τ���������åס����������Ĥ�Ѥ�������Τ��ޥͥ����ȤȤ��ä��Ȥ����Ǥ��礦��
���������ʤ�ΤǤ���
���������(1)
���٤���ڤζ�ETF 2007ǯ08��29��
���٤���ڤ���ETF����������Ȥ��äƤ��ޤ���
��ڤζ�ETF�ϡ����ơ��ȡ����ȥ�Ȥ����˥˥塼�衼����줷�Ƥ����ƹ�ľ͢���ʤǡ���θ�ʪ�ȸǤ���Ȥ�����ΤǤ���
�ʤ����虜�虜��ڤǤ��줷�Ƥ����ETF��֤Ĥ����Τ���
�����餯����ETF�ν�ʣ��줬��̣����Ȥ����ϡ���ڤ����������ǤϤʤ������ʤ���������������Ω������ˤ�⤯����Ǥ��뤳�ȤǤϤʤ��Ǥ��礦����
������ή��ϡ������ι�ʻ������ŻҲ��Ǥ���
��ڤ�����ڤ�����������ʼ�����...���ȥ��ޥ��ޤ������ȤǤϤʤ������ܤ�ͣ��ΰ�������Ƥʤ��Ȥ��㤢�ʤ����ʡ����ȡ����������㤤�ޤ���
�Ŀ�Ū�ˤϡ��п���������ڥ˥å�ϩ���������ʤΤǤ�����������Ĭή�ϥʥ˥�����������߹��ߤ����������Ǥ���
�Ȥ����ǡ���ETF�ϱ߷��ƤǤ����顢���������Ѥ����������ϲ�ǽ�ʤΤǤ��礦�����Ĥޤꡢ�����Υ���ɥ���ʤ�ȿ�Ǥ�����ڶ�ETF����äơ�NY���ʤ�ȿ�Ǥ�����ڶ�ETF����롢�ʤ�Ƥ����略��
������Ȥϰ�äơ��֥饤��������ǤϤʤ��Ǥ����顢���ε�����褦�ʡ��ʤ��褦�ʡ�����Ȥ⥳���Ȥˤ���ʤ��Τ��ʡ�
�������!
���������(0)
����ե�Ǥ��äƤ�ǥե�Ǥ��äƤ� 2007ǯ08��28��
���ع�6ǯ���μ��ˤ����֥���ե�äƲ����ס��֥ǥե�äƲ����פ�ʹ���Ƥ��ޤ��������ͽ����˺ܤäƤ����褦�Ǥ���
��������ʤ����֥���ե�Ȥ�ʪ�����ʤ��夬�äƹԤ����ȡס��֥ǥե�ϡ�ʪ�����ʤ������äƤ������ȡפȲ�����
�ܿͤϡ��ʤ�Ȥʤ�ʬ���ä��褦�Ǥ������֤Ƥ��Ȥϡ��ǥե���ȵ����Ⲽ���äơ��ߤ����˳�ˤʤ�äƤ��ȡ��פȥĥå���Ǥ��ޤ������ʤ��ޤ��ޤ��Ȥϻפ������������䡣��
�դȡ������ǻ�β������ڤ�ޤ���
�ǥե�Ǥ��äƤ⡢ɬ��������ϲ�����ʤ��������夬��ͤ⤤�롣��˳�ˤʤ뤫�ɤ�����ʬ����ʤ���
����ե���äơ��ϥ��ѡ��Ǥʤ���Ф��ۤ�����ǤϤʤ���
���ʽ������ɤ���ˤ��Ф��������ϡ������餯���֤����̤ꡣ�ǥե�ϥ���ե���Ⱝ�����פȲ������뤫�⤷��ޤ���
���ۤΤ��������⤷��ޤ�������ե��ǥե�Τ褦��ήưŪ�ʷк�Ū�Ҳ���ݤ��ˡ֤����ס֤�뤤�פȥǥ�����˶����Ƥ��ޤ��ȡ������ǰ����������ơ��Ҳ����ǤΥ��Х��Х��Ϥ�å�äƤ��ޤ����⤷��ޤ���
�����ꡢ�Ǥ���ʹ֤ϡ��Ҳɤ����졢�Ǥ���ʹ֤Ǥ���͡�
����ե�Ǥ��������ǥե�Ǥ����������Ҷ�ã�ˤϿ��äƤ���ˡ��õ��ǽ�Ϥ�ȤˤĤ����������ȹͤ��Ƥ��ޤ���
���������(0)
��ͻ���ʼ��ˡ�б����� 2007ǯ08��27��
���������п�ʹ��32�̡ʼ��Է��ǡˤˡ����潻ͧ��Ԥ��ɥ������Х�ͥ����ȡɤȤ�������������̹�����ǤäƤ��ޤ���
���������´����ޤ���Ǥ�������
����������β�Ⱦʬ�������ѡפȡ֥ꥹ���פ���������䤵�졢�ե���ȿ���16���餤���礭�ʻ��ǽ�Ƥ��ޤ���
��������Ⱦʬ�δο���������α����оݤϡ��ֿ���Ĺ��Ծ�פȤ��������ǡ��ۤȤ�ɥ����Ǥ���
���ι���Ƶ��Ť����ΤǤ����������ѡפȡ֥ꥹ���פ����������礭�ʥե���Ȥǽ��Ȥ����ǡ�ʸ�����礭����������Ω�äơ��������Ƥ����äƤ��ޤ���Ƭ�˻Ĥ�ޤ���
�����롢�ֶ�ͻ���ʼ��ˡ�б�����פʤΤǤ��礦�����������ȤˤȤäƤϤޤ��ޤ���������������Ƥ��褯ʬ����ʤ���ΤˤʤäƤ��ޤ��ޤ�����
�ºݡ�����Ǥϡ����ι��𤬾��ʤ�ǧ�Τ�����εեȥꥬ���ˤʤäƤ��ޤ��ޤ���
�դˡ��ȳ��ͤˤȤäƽ�����Τϡ�������η����ο�ʹ����������ι���Ρɥ٥���ޡ����ɤˤʤä��äƤ��ȤǤ��͡�
����������̣�ǡ����潻ͧ��Ԥȥ�����ɥޥ��å���AM�����Ū�ȸ����뤫�⤷��ޤ���
���������(0)
�Ŀ����Ȥθ�ΨŪ�ʺķ��ե�������ˡ 2007ǯ08��25��
���������ꥨ���ȡ����ߥ�˥ƥ��Υ��С��������������ޤ�����
�Ŀ����Ȥξ�硢�ʲ��ζ�ͻ���ʤ��ΨŪ�˱��Ѥ��Ƥ����ˤϤɤ������餤�������Ȥ�������Ǥ���
����Ū�ˡ��ķ������;夬��פϸ¤��Ƥ��ޤ����顢�����˹⤤�����ݥ����Ū�����뤳�Ȥ��Ǥ��뤫���ݥ���ȤǤ��� �������������ǡ������ξ��ʤ�Ƥ���Ƥߤޤ��礦��
������ķ����պġ����������ݥ��
���պĤ⥼�������ݥ�Ĥ⡢���δ��ֶ��������뤳�Ȥ�Ʊ���Ǥ��� â�������պĤ�Ⱦǯ�˰�����ʧ��������ޤ����顢�����Τ��ѻ��Ǥ��� ���ۤ����ҤǤ��ȡ�������Ǥ��ޤ���
���������������ݥ�Ĥξ�����ʧ���Ϥʤ��Ǥ��������պĤȤ��������ۤʤ�ޤ������������ݥ�Ĥ������塢��������Ǥ��͡�
�߷��Ƥξ��ȳ��Ĥξ��Ȥϡ�������ΰ������ۤʤ�ޤ��Τǡ������դ���������
���ķ�ETF(iShares LEHMAN AGGREGATE BOND/AGG����
�פ���ˡ��ķ��ե���ɤ�ETF�ǤǤ����ݥ���Ȥϡ���������ߤޤꤷ�Ƥ���Ȥ����㤨���Ǥ��� ����ꥫ��Ĺ������������ʾ�夬��ʤ���Ƨ��ΤǤ���С���Ƥ⤤���ΤǤϤʤ��Ǥ��礦����
��������ETF�ξ�硢�ķ������ETF�ξ�硢�����ϳ�����Ʊ�������ˤʤ�ΤǤϤʤ����Ȼפ��ޤ���
��ڤζ�ETF�ϡ�����ʤ�Ϣư����ķ�����Ƥ��ޤ����������ϳ���Ʊ���Ǥ���
������ķ�����ǥå����ե����
�����������̤Ȥ��Ƥϭ����Ѥ��Ϥ���ޤ��� ������ĥե���ɤϤ�������μ��ब����ޤ��Τǡ��ե���ɤˤ�äơ��ѥե����ޥϰۤʤ�ޤ���
�ޤ��ޤ��������ݥ���ȤǤ����������꿮�γ���ķ�����ǥå����ե���ɤϡ���ǰ�ʤ��������Ʊ�������Ǥ���
�ʤ��Τ����꤬�����ܤξڷ������Υ������ʤȤ�������
*************
��ɡ��ķ��ե���ɤ�ɤ��Ȥ����ʤ��Ƥ������Ȥ����Τϡ������������Ƿ�ޤ�Ȥ��äƤ����ǤϤ���ޤ���
������ķ��Ȥ��äƤ⡢���֥��Ĥ��顢�Һġ��ϥ�������ɺĤޤǿ����Ϥ��ۤʤ��Τ�¿������Τǡ������դ�⽽ʬ��Ƥ����ɬ�פ�����ޤ���
����ˤ��Ƥ⡢�ڷ��������ġʤ��Ӥġˤ������Ȥ��ʤ�ޤ��͡���
���������ǹͤ���ȡ�������ͭ���ʳ��ĥե���ɤϤ����餯̵ʬ�۷�������Һ��꿮�ʸ��ߤ������Ǥ���ѱ�����ǡˤǤ��͡�
��¼��������¼�ڷ��Ǽ�갷�äƤ��ޤ��衣
���������(0)
̾�Ų���ĥ���� 2007ǯ08��22��
�轵������˰���³����������̾�Ų��ǹֱ�Ǥ���
����Υ������Х롦�ޡ����åȤ�ư�����ɤ��ʤ뤫���Ȥ��ä�����Ǥ��ä����Ƥ��������ޤ�����
�ݥ���Ȥϡ�
�� �����кѤϥ��ޡ����������Ĺ�˰���ĥ���Ƥ��롣
�� ��ʹ����Ĺ�ϥޥ���ɤʤ�⡢��ͻ�Ծ�ϥϥ��ƥ�����ʣ�������뤿�ᡢ�ܥ�ƥ��� �ƥ��ʳ�������ưΨ�ˤϹ⤯�ʤ롣
�� ������Ѥ���ˤϡ��ʸĿ͡����Ȥ⤽������ʤ���Фʤ�ʤ���
�Ȥ��ä���å��������Ϥ����ޤ�����
�Ǥ��Τǡ����Ǥ���������������Ǥ������������ʤǤ����������ꥹ�����ǧ�����ʤ��顢�ꥹ���������������Ǥ���Ȥ������Ȥ������������ä��Ȥ����櫓�Ǥ���
��ľ��dz���Ƥ��ޤ��ޤ���(^��^)
���������(0)
���������Ǯ 2007ǯ08��21��
�轵��������������˹ԤäƤ��ޤ���������֤ۤɡ������кѤȻԾ�θ��̤����ä��Ƥ���Ȥ������å�����ꡢ�����ǹֱ�Ǥ���
���üԤ϶�ͻ���شط��ԤǤ���������Ϥ�ݥ���Ȥϥ��֥ץ饤��ȥ������Х롦�������ȥ졼�ɤδط����褯ʬ����ʤ��ȤΤ��ȡ����Ȥ���¤�λ����ǡ�����Ū�ʻ��εղ�ž���������ޤ�����
��äѤꡢ��ʹ�ˤ�����Ƥ��äƤ⡢�ֻդ��ä�ʹ���ʤ����Ȥˤ�����ˤϷ�ӤĤ��ʤ��褦�Ǥ���
������Ƥ�����դۤɡ���ɴ�ɤϰ�ʹ�ˤ������פǤ��͡�
���������(0)
����� ��ETF���������Ѥ���� 2007ǯ08��19��
�ѥ���������Υ��ޥ�����ǥ�������Ƥ��������ޤ�����
��ʸ��������������������͡�
����ꥫ�Ǥϴ��ˡ��ֳ˥��ͥ륮��ETF�פ���ֶ�������Ǥ���
���������(0)
�֥ץ��פ�ϵ�� 2007ǯ08��17��
�Фä��㤤�ޤ�����������ǥץ��ȸ����Ƥ����ͻ�ط��Ԥ⡢����˽��˥ӥӥäƤ��ޤ���
�֤ɤ��ʤäƤ������� �� �ֲ��Ȥ��������� �� �֤��ꤤ����������ơ���...��
���ۤ��㤦�����ȻפäƤ��ޤ��ޤ����ä��ơ����п�ʹ��ͥåȤǤ�泰��Ф��������ʤ���������ʳ��Υʥ˥�ΤǤ�ʤ�����
�����ä������Τʤ顢�夬�ä������ȸ��������Ǥ���
����������ϡ����Ȥߤ��褯ʬ����ʤ���̳ô�ݾڷ��μ���������ä��Τǡ����Ȥ������ŵ��ˤʤä������Ǥ���
�ʹ֤ϲ���Ʊ���и���Хѥ˥���ʤ��ΤǤ��礦����
��ɡ����Ͽ�����100��ʤΤǤ��͡�
���������(0)
���ҥ祦���и� 2007ǯ08��16��
���䤤�䡣
��ǯ�ϥҥ��ɤ����������ҥ祦���о����Ƥ��ޤ��ޤ�����
���ҥ祦�����夲��Ȥ��ϡ���ͤ�Ф뤽���Ǥ���������3��ȥ�ˤ�ʤ붯��ʥ��쥤�ο��̤Ǥ���
�ޡ��ǥ�����ʪ�����夲��ݤˤϡ�����ʤ�Υꥹ������ʤ��ȥ����ʥ��Ȥ������ȤǤ��͡�
���������(0)
��ͧ�ζ줷�� 2007ǯ08��15��
����ϴ�Ȥ���ɽŪ�ʼ�����Ȥ��Ʋ����夲�Ƥ��륦����ޡ��Ȥ�������줿��ͧ�Ǥ�������äѤꡢ�ޤ����á��ȿ��̲��Ǥ��襤��³���Ƥ��ޤ� ��
���֥�������ޥ��Ǽ��夲�ޤ���������ǯ���äƤ��꤯���äƤ��ʤ��褦�Ǥ���
�䤬�פ��ˡ���꤯�����ʤ���ͳ�ϡ�EDLP�䥷���ƥब��꤯������ʤ�����ǤϤʤ���������ޡ���¦�����ܤξ�ʸ����ͻ�������Ǥ��ʤ�������Ȼפ��ޤ���
��ɤϡ����ߥ�˥��������꤯���äƤ��ʤ��ΤǤ��礦�͡�
���ܤ������ǡ����礬�Ұ���ȥ����뤹��о�꤯�����Ȥ������ۤϡ������ܤˤ�����M&A�����ä��ꤷ�ʤ��Τ�Ʊ���Ǥ���
����ʳ�����äƤ��Ƥ⡢ʸ�����ɤ�֤��ˤä��٤���ˤϡ�¿������Ϥ�Ǧ�Ѥ�ɬ�פʤΤǤ���
����Х졪 ��ͧ
���������(2)
�����Ͻ��ﵭǰ�� 2007ǯ08��14��
�����������ơ��ޤǤ����������Ͻ��ﵭǰ���Ǥ���
���Ĥơ����ܤΤ���˽�������Ф��ݤ졢�ޤ���Ф�������Ӥ�줿��ã�˷ɰդ�ʧ�������Ȼפ��ޤ���
�������������ϡ�������������κ���Ȥʤ�ޤ����������ʤ��Ȥ˿�ǯ�塢������˵��Ԥ��뤳�Ȥ��Ǥ����ΤǤ���
�ִ��ɤ���פ��Τ�Τ������Ǥ��� ��ƻ���졪�Ȥ������ä�������������ä��Ǥ������ӥ��äȶڤ��̤äƤ��ޤ�����
��Ϥ����������Τ��Ȥ���ʹ�Ǥ����Τ�ޤ����Τ����ܿͤˤ������˥��åĤ����ä��Ȼפ��ޤ���
�ֻ����Ǿ�������뤳�Ȥ��Ծ�����
����ʤ��Ȥ�פ��С��ޡ����åȤ�ư���ơ������������ѡ������»����ä��äƤʤ�Ƥ��ȤϤ���ޤ���
�����Ƥ���ΤǤ����顣
���������(0)
���٤��뤳�Ȥϻ��٤��롧ABS�ϥ֥졼���ǤϤʤ� 2007ǯ08��13��
���֥ץ饤�������֥����������Τ�ޤ���ABS�ʻ�ô�ݾڷ��˷ϱ��ѤΤ�������ǡ��줬�Ӥ��Τ�и�����ΤϤ��줬3���ܤǤ���
����ܤ�2001ǯ��9��11ľ�塣���ɥȥ졼�ɥ���������оݤΤ�CMBS�ʾ�����ư��ô�ݥ�����ڷ��ˤ�������80�餤�Ͳ����ꤷ��������Ȥ�����Ƥ���������δ����ۤ�5��ʾ岼����ޤ�����
����ܤϡ�2003ǯ�Τʤ��Ф����Ρ��Ҷ�����Զ����Ҷ�������ĸ���ô�ݤˤ���ABS�ʻ�ô�ݾڷ��ˤ����Ǥǡ�United���ݻ����ޤ����������Ե�������Ǥ���ΤǤ�������
���ΤȤ��⡢������Ȥ�����Ƥ�����Libor+1�餤������������������ޤ�����
�Ȥ������Ȥǡ�����ϥ��֥ץ饤�����ꡣ
�ʤ����֥ץ饤��ABS����꤯�����ʤ��ä���ʬ����ޤ���
����ϡ��֥ꥹ���Τ����ѥå������ˤ����ڤ���ꤹ��С��ꥹ��������ȡפȤ��������륹�ȡ������ݤߤ����ꡢ�����ͤ����ꥹ���ᤴ�����Ȥ����뤫��Ǥ���
�ѥå������ˤ��褦�����ޤ�������ɥꥹ���Τ����Τϥꥹ��������ΤǤ���
���Ȥߤ����Ȥ�����Ƥ���ޤ������Ƥ����Τϡ�����ʥꥹ�����ФʤΤǤ���
���������(0)
Ǯ�������� 2007ǯ08��11��
�������ݻ�36�٤Τʤ��������⸵���˥ƥ˥��Ǥ���
���䤢�����뤫�ä���
���Ϥ��ʤ괨�������Ǥ��������Ϥ��äƤο����Ǥ����顢���ν뤵��ڤ���Ǥ��ޤ��ޤ�����
�Ǹ�����ϡ��������������ޤ��������Ȥꤢ�������ˤ����ե��˥��塣�����Ⱦ�ץ졼����2��åȥ�ο������ޤ��������νŤ�2kg����ޤ�����
�Թ硢4��åȥ뤯�餤�ο�ʬ����Ƥ��ޤ���
��줬�ɤ�ʤ�����Ƥ⡢2��åȥ���ϰ���ޤ������ͤ���ȡ��Ծ�β���ʤ���礷�����ȤǤϤʤ��Ǥ��͡�
������ī7������ƥ˥��Ǥ���
���������(0)
�Ʋ����ˤ��ήư���ζ��� 2007ǯ08��10��
����ꥫ��FRB�Ȳ��������Ԥ����Ծ��ήư���뤷�ޤ��������֥ץ饤������������ü��ȯ�������ߥˡ����쥸�åȥ�������ä�������Ū�ǤϤʤ����ȹͤ��Ƥ��ޤ���
�����β���Ϥ��ξ����Ǥ��פ����ʤ��Τǡ��ŴѤ�����ޤ���
�ष�����乥���㤤��ɤǤ���
�����ԤˤȤäƤϡ��������٤�shake�Ǥ��������װ��ˤ�����ʤ���������ȤƼ�ʬ����������ȥ����뤹��û������������������Ϣư�ˤ��ɾ���ˡɾ夬��Τϸ��ᤴ���ʤ����Ȥ��ä����Ȥ��������ήư������ˤĤʤ��ä��Ȼפ��ޤ���
��������Ĥ���̤������ǤϤʤ������줬���ä��������ϤΤʤ���ͻ���ء��ä��澮�ζ�Ԥ˿����¤��Ф����Х����Ȥ����Τ��طʤǤ���
��ηи��Ǥϡ����Ф餯������Ծ�����ﲽ���Ϥޤ�ޤ����ޤ��ϡ����¿���
���������(0)
�������ܥ饿����ʻ���... 2007ǯ08��08��
��������������㤤���饹����ͭ����Ȥ����ͤ���������ޤ���
���������֡������γ����Ծ�ϲ���ޤ�����������ʤ��������ʤȤ��ä����ʲ��ʡʥ���ǥ��ƥ��ˤϤष�����徺���Ƥ��Ƥ��ޤ���
����Ū�ˤϡ������ȥ���ǥ��ƥ���������äƤ���Ф褤���Ȥ������Ȥˤʤ�ޤ��������Ͼ����㤨�Ƥ⡢����ǥ��ƥ��Ϥ�����ñ�ǤϤ���ޤ���
�б���ˡ�ϡ���Ϥ�ե���ɡ�������ˤ�ETF���Ȥ߹�碌�Ƥ��������ʤ������Ǥ���
������ѥե����ޥϳ������������⡢�ޥ���ɤˤϤʤ�ޤ�����
���������(0)
5.2�ܡ�8.0�ܡ�3.7�ܡ�2.8�� 2007ǯ08��07��
�����ο����Ϥʤ����ʬ����ޤ�����
���ϤΥ��å��ǤϤ���ޤ��ʾС�
�����BRICs�ƹ����ɽŪ�ʳ����ؿ��β��5ǯ�֤ξ徺�ܿ��Ǥ���
�Ĥޤꡢ2002ǯ7���2007ǯ��7��ޤǡ��֥饸��ʥܥ٥��ѻؿ��ˤ�5.2�ܡ���������RTS�ؿ��ˤ�8.0�ܡ�����ɡ�NIFTY�ؿ��ˤ�3.7�ܡ����ʾ峤����ؿ��ˤ�2.8�ܤˤʤä��Ȥ������ȤǤ���
�����ˤ������徺�Ǥ��͡�
���ܤι��ٷкѻ����1970-1975ǯ�Ǥ���������ʿ�ѳ�����2000�����夫��4000�������2�ܤˤʤä��˲�ޤ���
������ñ�����Ӥ��뤳�ȤϤǤ��ޤ����������Х벽�αƶ��dz����Ծ��ή������ޥ͡����̤������㤤�ʤΤǤ��礦���������äơ��ܥ�ƥ���ƥ����ޤ�Τϼ����ʤ��ȤǤ���
��̤Ȥ��ơ�����ꥫ�Υ�������ʹ�������ʡ�֥ץ饤�ࡦ������ˤ������ζ�ͻ�Ծ��������������Ȥ����̤��Ƥ���Ȥ����櫓�Ǥ��͡�
���⥤��ե�ΰ��� 2007ǯ08��05��
����ꥫ�Υߥͥ������ǹ�®ƻϩ�ˤ����붶�������¿���λ�Ԥ��Ǥޤ�����
�����˥塼�衼���ˤ褯��ĥ���Ƥ��������顢����ꥫ��ƻϩ�䶶�ϥܥ��ܥ����ʤ����ȻפäƤ��ޤ���������Ϥ������ʾ��Ϸ�ಽ���ʤ�Ǥ���褦�Ǥ���
���ܤ�Ʊ�ͤǡ�����ƻϩ�Υ���ե�ϡ����äƤ����Фɤ�ɤ��ʤ�Ф���Ǥ���
���Τ褦���طʤ����ä����ɤ����Ϥ狼��ޤ����轵�����¶ȳ��ΰ�Ѥ��㤤�����äƤ��ޤ�����
�ߤʤ���ȿ���������Ǥ��͡�
�����⸵���˥ƥ˥��Ǥ� 2007ǯ08��04��
������ī���鵤�����夬�ꡢ�Ϥ11����Ϥ��֤�30�٤�Ķ���Ƥ����Ǥ��礦��
�ϡ��ɥ����ȤǤ������顢�����Ⱦ��35��6�٤ˤʤäƤ������⤷��ޤ���
�������ˡ��Ȥ����λ���ȴ�����Τ������ơ��Դ���褯ư���Ƥ����Τ��������ϥե������Хå��Ȥ�ޤ��ޤ��Ǥ�����
�����֤��Ⱦ�褯�ʤꡢ���Ȥ���ʬ�褯�����ޤ����͡�
���Ĥⵤ�Ť��ΤǤ�������̤�ΤƤ�Ȥ�������åȤ��ǤƤ�ΤǤ���
æ�� �� ��̤�ΤƤ� �� �ڤ��� �� �褤��̡� ���Ĥ⤳�ν۴ĤǹԤ�������ΤǤ���
****************
NY�Ծ줬��ä������äơ����Τ������ޤ��� ���å��������Ԥ��ޤ��礦��
���ͳ������ 2007ǯ08��03��
��������ܤ�Ф����ä����ˤʤä��丵���פ���
�Ȥκ��Ʋ�˽��ʤ��ޤ�����
�����ǡ������륹�����ߥ�˥����������뤳�Ȥ�ӥ��ͥ��ˤ���Ƥ������ͳ���������Τ�礤�ˤʤä��ΤǤ���
�������顢���ߥʡ��ǤϤ����������Ƥ���ΤǤ������ºݤˤ��ä�����ΤϽ��ơ��¤�������Х�Ф�δ����ͤǡ����椫��ͥ��ƥ���Ʊ�Τβ��äȤʤäƤ��ޤä��ΤǤ���
Ʊ����Ǥ��Τǡ��礤�˱��礷�����Ȼפ��ޤ���
�ä˽�������������Ĥ��ʤ��� �����Υ��ߥ�˥���������������ɤ�ǤߤƤ���������
������Ǯ�� 2007ǯ08��01��
���ƥ����ѥ��γ�������Ĵ���桢�������������ư�����Ƥ��ޤ���
�طʤϡ���Ĵ�ʴ�ȶ��Ӥȸ��Ѥ����á�����Ψ���㲼�ʤɤˤ���ޤ����ä˼���Ψ��6.9��������㲼������ǯƱ����1��ݥ���Ȳ����
�ä��ơ��桼�������첤���������ޤdz��礷�Ƥ��ꡢ���������̲���ư��������͢������ե��͢���Կ����鳫������ĤĤ����ϰ褬�����Ƥ���ΤǤ��礦�͡�
���ơ����줫�顢��������ECB�����ɤΤ褦�ʥ����ߥ����夲�Ƥ�����������ΤǤ���
���ߡ�ECB�����������4.0���ĤƤκǹ��ͤ�4.75��Ǥ����顢�ޤ��Τ��夬����ޤ���
�����������夬��ȡ��Ƥӥ桼���⡢��������Ȥʤ뤫�⤷��ޤ���
���������Τϲ����Ծ�Ǥ���
���ڡ����Υȥåפ�
|
|
|
|