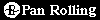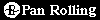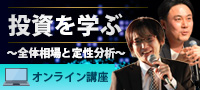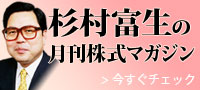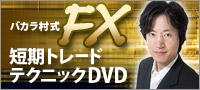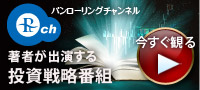|
����������Υȥ졼��������
|
�ȥ��״��Ǥ���Ӥ졢Ĺ�籢���ǵ���� 02��28��
�������ƹ�������������������DJIA -193.62 @43,239.50, NASDAQ -530.84 @18,544.42, S&P500 -94.49 @5,861.57�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�150������Ⱦ��������߰¥ɥ����Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤ϲ�����������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������312���Ф��ơ�������������1,283�Ȥʤä���ƭ��쥷����98.42%����ڥץ饤�����������6��2109���ߡ�
TOPIX -54 @2,682
����ʿ�� -1,101�� @37,156��
�ƹ�Ǥϡ��ȥ��������Τ�1����ֱ�������Х��ʥ��ȥᥭ�������Ф���25%��͢�����Ǥ�ͽ���̤�3��4����ȯư���������Ф��Ƥ�10%���ɲô��Ǥ�ݤ���ȯɽ�����������EU���Ф��Ƥ�25%�ι���Ǥ�ݤ���ȯɽ�����������δ��Ǥ�������ȯư�����С��⤤͢�����Ǥˤ���ƹ���Υ���ե찵�Ϥ���ޤꡢ�Ŀ;�����व���뤳�Ȥˤ���ƷкѤ����ह��Ȥη�ǰ����ޤä������̥ӥǥ�����3%��夲�ƻϤޤä��������θ�����˲������8%Ķ���������ʵ���ɸ�Ǥϡ����������ݸ����������ͽ�۰ʾ�����ä��������Ʒʵ����������Ƥ���ȼ����ߤ��줿������餹�٤Ƥΰ������ˤ�����3�����ؿ����礭�����������ե���ǥ�ե���ȾƳ�γ��ؿ���SOX�ˤ�6.09%������������Υ�������Ȥ������˰���������
����2��28��������Ծ�Ǥϡ��ƹ�Ǥγ��¡��ä˥ϥ��ƥ����¤�ή��������ȾƳ�δ�Ϣ�������濴�ˤ��礭�����줿������˥ȥ��������δ�����������Ʃ�����ˤ�꼫ư�ֳ����礭�����줿��
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ�Ĺ�籢���ǵ������ǯ10���ܤ���³���Ƥ����ݤ��礤���β��¤����Τ˳�����Dz�ȴ�����������37,000�ߤ���ͤ��ˤäƲ���������礷��36,840�ߤޤDz���������ưʿ�����ϲ�������֤�10����25����60���γư�ưʿ���������äƤ��뤬�����٤Ƥΰ�ưʿ�����ϲ�������ž���Ƥ��ꡢ�����Ϥ���餹�٤Ƥΰ�ưʿ�����β������߹���Ǥ��롣�����������뭦����¤ʲ�����̡ˤǤ��롣��ǯ9��9�����դ���35,247�ߤ����β��ͻٻ����Ȥ��Ƥ��ռ�����롣������������ȡ���Χȿȯ�������㤤������䤹���ʤꡢ�ƹ���β�������ö�Ǥ�ߤޤ�С��轵���ˤ����ˤˤ�ȿȯ�����ǽ���Ϲ⤤�����������쵤�˸��ο��ޤ��᤹���ȤϤۤȤ�ɤʤ����夤���ξ��ϲ�������3ʬ��1�ᤷ��ʿ��Ū�ˤ�Ⱦ���ᤷ���餤�����Ӥ˸��Ƥ���������
33�ȼ���29�ȼ郎������������Ψ�ȥå�5�ϡ���Ŵ��°��1�̡ˡ�������2�̡ˡ��ŵ������3�̡ˡ�͢���ѵ����4�̡ˡ������ӥ���5�̡ˤȤʤä���
���������
���̥ӥǥ�������Ĺ�߲��������ȤʤäƤ����Τǡ����� 02��28��
�������ƹ�������Ϲ�¤ޤ��ޤ��Ȥʤä���DJIA -188.04 @43,433.12, NASDAQ +48.87 @19,075.26, S&P500 +0.81 @5,956.06�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�149������Ⱦ�Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤Ͼ夲��������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������1,222���Ф��ơ�������������380�Ȥʤä���ƭ��쥷����106.16%����ڥץ饤�����������4��3399���ߡ�
TOPIX +20 @2,739
����ʿ�� +114�� @38,256��
�ƹ�Ǥϡ��ȥ��������Τ�EU���Ф���͢�����Ǥ�ݤ��ײ��յĤǼ��������ᡢ�������νŤ��Ȥʤä������Ǥʤ����Ʒʵ��ΰ�����ǰ������10ǯ��������������4.298%����4.256%���㲼������
�������2024ǯ11���1����軻��ȯɽ�������̥ӥǥ�������������ס�EPS��0.89�ɥ��ͽ��0.85�ɥ�ˤϻԾ�ͽ�ۤ���ä���25ǯ2��4��ͽ�����⸫�̤�����ǯƱ����65%����430���ɥ������ͽ��421���ɥ�ˡ�����������ȵ��Ϥ��礭���ʤä�������Ĺ���߲����ޡ�����ϰ�������Ȥη�ǰ�ˤ������ϻ��ֳ�������������ʤ��岼������
����AI���Ф������Ȥδ��Ԥ��߲����ĤĤ���褦�������̥ӥǥ���������Ψ��1ǯ���ˤ�250%��Ķ���Ƥ����������Ǥ���ǯƱ����78%��4Ⱦ��Ϣ³���߲����������Ȥδ��Ԥ��㲼�����Ƽ���Τ�ͽ��PER���Ѳ��Ǥ��롣2021ǯ�Υԡ������ˤ�60�ܤ�Ķ���Ƥ����������Ǥ�30�ܤ�����ߡ�������ޡ��Ȥ�36�ܤ����㤯�ʤä������DeepSeek���о�ǥ��̥ӥǥ������Ф�����ԤϤ���˲����ä�������AI�γ�ȯ�ˤϹ����GPU���Բķ���ȿ������Ƥ����������Ρֿ��áפ�����Ϥ�������
�����ǯ��ظ����ơ�����AI�����濴��ȾƳ����¤�ʥ��̥ӥǥ�����AMD�ˤ��顢�ץ�åȥե����ޡ�������ե�ʥ���ե��٥åȡ��ޥ��������եȤʤɡˤء�����˥����ӥ������եȥ������ʥ��ޥ���ˤذܹԤ��ƹԤ��Ȥθ��������롣�ޤ�����ۤ�AI����Ū�ˤϻפä��ۤ����̤�Ф���������ޤ��Ĥ����褿���Ԥ����Ǥ˰쵤���Ѥ��ָ��Ǥ�ë�פȤʤ��ǽ����˺��ƤϤ����ʤ���
�ƺķ��Ծ�Ǥϡ���̳�ʾڷ���TB��3����ʪ����꤬10ǯ�����������ֵե�����ɡפ���2����֤��ȯ���������ᡢ�Ʒʵ��θ�®������ǰ����롣�ե�����ɤϡ�ú�ۤΥ��ʥ��פΤ褦�˷ʵ���������̤������ȯ�����뤳�Ȥ�¿������Ǥ��롣
����2��27��������Ծ�Ǥϡ�����ȸ��ä��㤤�����Ϥʤ��桢��Χȿȯ�������㤤�����ꡢ����ʿ�Ѥξ夲���ϰ��200�ߤ�Ķ���������������Ʒʵ��θ�®��ǰ��߹�߰¿ʹԤ��طʤ˾��ͤ��ޤ���줿��
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ������ݤ��礤���β��¤ޤ��Ϥ�����ġ�����Ĺ�����Ҥ���������Ʊ�����Ȥʤ�������ȿȯ��ż����Ƥ������������Ϥ����̤��ư���Ȥʤä���������Ĺ�����Ҥ���������������Ȥʤꡢ���㡼�Ȥ�����Ƚ�Ǥ���С�������⤯�ʤ��ǽ�����⤤��������������ư�������Ϥ϶��Ӹ��̤�����ư�Ǥ��ꡢ����ˤ��ζ��Ӹ��̤�����ư���ƹ�кѡ������кѤθ��̤����Ф������Ȥδ��Ԥ��Ѳ��ˤ�������������롣���δο��������кѤθ��̤����ȥ��״��Ǥˤ���礭���ɤ�ư���Ƥ��뤿�ᡢ��Ԥ���Ʃ������������
33�ȼ���27�ȼ郎�夲�����徺Ψ�ȥå�5�ϡ���Ŵ��°��1�̡ˡ��ݸ���2�̡ˡ�͢���ѵ����3�̡ˡ�����¾���ʡ�4�̡ˡ��Ҹˡ���͢��5�̡ˤȤʤä���
���������
�������ˤ�ư�������ʤ��Ȥ������Ρְջספ��� 02��27��
�������ƹ�������Ϲ�¤ޤ��ޤ��Ȥʤä���DJIA+159.95 @43,621.16, NASDAQ -260.54 @19,026.39, S&P500 -28.00 @5,955.25�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�149����Ⱦ�ФǤ�ư�����ä������������ܳ����̤ϲ������������������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������619���Ф��ơ�������������948�Ȥʤä���ƭ��쥷����103.43%����ڥץ饤�����������4��5360���ߡ�
TOPIX -8 @2,716
����ʿ�� -95�� @38,142��
�ƹ�Ǥϡ��ȥ��������ι���������ˤ���ǰ���������кѤ��ƹ�кѤ�̾�������Ȥη�ǰ���������桢2�����Կ��괶�ؿ���ͽ�۰ʾ�˼夫�ä���98.3��ͽ��102.5������ʬ105.3�ˡ�����ˤ���Ʒʵ�������ǰ�����ޤꡢ�ϥ��ƥ�����ꡦ�ǥ��ե��ֳ��㤤��ή��Ȥʤä�����Ĺ��������������4.393%������4.283%�ޤ��㲼�����塢4.296%�ǽ�������
����2��26��������Ծ�Ǥϡ��ȥ�������������ȾƳ�ε���������Ȥδ�¬���طʤ��ƹ�Ծ�ǤΥϥ��ƥ�������ή�������ơ�������쥯�ȥ����ǥ������ʤ��ͤ���ȾƳ���������濴�����줿������ˡ���Ĺ���������㲼�ˤ����1�ɥ��148����ޤǤα߹�ɥ�¤��ʹԤ�������꤬��®��������ʿ�Ѥβ������ϰ��500�ߤ�Ķ�����������Ū�����ܤȤʤ�38,000�ߤ�����������������������ˤ����ơ������ؿ���ʪ�����ᤷ�����ꡢ����ʿ�Ѥϲ�������̾����ƽ�������26���˲�������ȾƳ�������ƥ��̥ӥǥ������軻ȯɽ�뤿�ᡢ����AI��Ϣ�˶����������濴�˷ٲ�������ޤä������DeepSeek���²�������AI��ȯ���ư��衢AI����ȾƳ�Τ��絬�����������ɬ�פʤΤ��Ȥ������䤬ͯ���Ƥ��Ƥ��롣���̥ӥǥ�������ĹΨ�ο��Ӥ��߲����٤ˤ������𤬤��뤫�⤷��ʤ������̥ӥǥ����η軻�Ȥ������٥�Ȥ�̵����̲᤹��С�����ȴ�������Ф뤿�ᡢ��˿���䤹���ʤ롣
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ�����Фǰ��37,743�ߤޤDz����ơ���ǯ10���ܤ����Ȥ����ݤ��礤���β��¤ޤDz����������ο��϶������ͻٻ����Ǥ��ꡢ�����ΤȤ��������Τ��Ƥ��֤��줿������û����Ҥ�������Ĺ�����Ҥ�����������Ʊ�����Ȥʤꡢ�������ˤ�ư�������ʤ��Ȥ������Ρְջספ���������Τ������ƹ�Ǥ�ۤ��礭�ʰ��������ФƤ��ʤ��¤ꡢ�����δ���դ��Ϲ⤯�Ϥޤ�ȸ��Ƥ��롣
33�ȼ���17�ȼ郎�夲�����徺Ψ�ȥå�5�ϡ���ư����1�̡ˡ������ʡ�2�̡ˡ�������3�̡ˡ�Φ����4�̡ˡ������ʡ�5�̡ˤȤʤä���
���������
�ƤӥХե��åȻ�Υ��ʥ����ȸ��̤����뤫�� 02��25��
�кѻ�ɸ���������ƹ���������轵���������礭���������DJIA -748.63 @43,428.63, NASDAQ -438.36 @19,524.01, S&P500 -104.39 @6,013.13�˸塢���ܤ������Τ���پ���ä������Ⲽ�����DJIA +33.19 @43,461.21, NASDAQ -237.08 @19,286.93, S&P500 -29.88 @5,983.25 �ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�149�����Ⱦ��������߹���Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤ϲ���������������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������725���Ф��ơ�������������845�Ȥʤä���ƭ��쥷����110.53�Ȥʤä�����ڥץ饤�����������4��8611���ߡ�
TOPIX -11.83 @2,725
����ʿ�� -539�� @38,238��
�ƹ�Ǥϡ��꼡���夤�ʵ���ɸ��ȯɽ�ˤ�ꡢ�轵�������ˤϼ���3�����ؿ����礭���������������ϼ�Χȿȯ���ƻϤޤä������ȥ����������Τ�1����ȯư�������Ƥ����Х��ʥ����ᥭ���������͢�����Ǥ�ȯư�˸��ڤ������ȤǺƤ���ꥻ������Ȥ˷�������
����2��25��������Ծ�Ǥϡ����̥ӥǥ�����Ϥ���Ȥ����ƥϥ��ƥ����¤�ή��˲ä��ơ��ȥ����������������ȾƳ�ε���������Τȴ�¬�ˤ�ꡢ�����ؿ��Υ������Ȥ��⤤������쥯�ȥ���䥢�ɥХ�ƥ��ȡ��������ʤ�ȾƳ�δ�Ϣ���������¤Ȥʤä�������AI���������μ��פ��礭���ȴ��Ԥ���Ƥ����������Υե����������Ź����礭�����줿������ˤ����Τ���ͳ�����롣�轵��21�����������TD��������ݡ��Ȥ�ȯɽ�����ƥޥ��������եȤ��־��ʤ��Ȥ�ǡ����������ȼ�2�ҤȤη�����������פȻ�Ŧ���������줬AI�����ǡ���������������ˤʤäƤ���ΤǤϤʤ����Ȥ��¤���������������ޤ������ٻԾ�DZ���줬1�ɥ��149�����Ⱦ�α߹�ɥ�������ؿ��줿�����η�̡�����ʿ�Ѥβ������ϰ��600�ߤ�Ķ������
�������������������Ф���Ǥ�ʤ��ä�����������Хե��åȻ22���˸�ɽ�����ֳ���ؤμ��פ����ܤ����羦�ҳ����Ф���������۰��ߤ���������ޤ�10%̤���Ȥ��Ƥ������־�¤�Ŭ�٤˴��¤��뤳�Ȥ�5�ҤϹ�դ����פ��������������������ơ���ɩ��������ƣ�顢����ʪ���ʤ����羦�Ҥϸ��¤��㤤����������������Ȥʤä������羦�ҳ��Ϥ��ʤ�Ĵ�����ʤ�Ǥ��ꡢ��´������ޤäƤ������Хե��åȻ�Υ��ʥ����ȸ��̤�2023ǯ�դΤ褦�˺Ƥ����ܳ����Τ��夲�뤫�ɤ�����
�����ܤ���������Ф���������ħ����Ƥ���Ƥ���ȸ�ɽ�������Ȥǡ����ܤγ�����Ҥ��Ф�����פ����ä���Ȥδ��Ԥ��龦������ʤɤ���곤���������줿��
�ƹ�Ǥ����Ǽ夤�ʵ���ɸ���꼡���Ǥ��ꡢ�Ʒʵ��θ�®��ǰ�����ޤäƤ��롣24���˥��饹Ϣ�䤬��ɽ����2����¤�ȷʶ����ؿ���������礭����������21����S&P�������Х뤬ȯɽ����2���ƹ���ô���Էʵ��ؿ���PMI��®���ͤǤ�1ǯ5����֤����Ȥʤä���������ȿ�Ǥ���Ĺ�������Ͻ����˲����Ƥ��뤿�ᡢ���ƶ��������̾����Ƥ��롣���η�̡��߹�ɥ�������ؿ���䤹���ʤäƤ��롣
����Ĺ�������ʡῷȯ1ǯʪ��������ˤˤĤ��ơ��轵�ϰ��1.455%��2009ǯ11�����15ǯ3����֤�ι���ˤޤǾ徺���Ƥ������������ϰ��1.365%�ޤǵ��㲼������21���ν��ı�ͽ���Ѱ��������ο������ۤ�ȯ����Ĺ�����������������ȥޡ����åȤ���ᤷ����������ɲ����夲�Ͼ�����Τ����⤷��ʤ����������������Ȥ��ƤϾ夷���ʤ��ȸ��Ƥ��롣
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ�����åץ����ƻϤޤꤵ��˲���������礷�Ʊ����ǽ���������ǯ10���ܤ���³���Ƥ����ݤ��礤��β��¡�37,800���դ�ˤˤ���ܶᤷ����
�Ŀ�Ū�ˤ�UFJ��Ԥο������̤������㤤�ֺѤ���2��19��������ڤä��㤤�̤٤��㤤�ᤷ�ޤ�������ɩ�������ƣ��ʤ����羦�ҳ��⤷�ä����㤤�ޤ�����
33�ȼ���21�ȼ郎������������Ψ�ȥå�5�ϡ���Ŵ��°��1�̡ˡ���������ú��2�̡ˡ��ŵ������3�̡ˡ������ӥ���4�̡ˡ�������5�̡ˤȤʤä���
���������
�����ΤȤ����ϡֿ��ĥץåȡפdz����β����ϻߤޤä� 02��21��
�������ƹ������������ȿ�����DJIA -450.94 @44,176.65, NASDAQ -93.89 @19,962.36, S&P500 -26.63 @6,117.52�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�150����Ⱦ�Ф�������߰¿��Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤ϲ�����������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������556���Ф��ơ�������������1,031�Ȥʤä���ƭ��쥷����110.07%����ڥץ饤�����������4��3160���ߡ�
TOPIX +2 @2,737
����ʿ�� +99�� @38,777��
�ƹ�Ǥϡ��軻���Ƥ��夫�ä�������ޡ��Ȥ�����������¡�7%�¡ˤȤʤä���2024ǯ��4��Ⱦ����ͽ�ۤ���ä���ΤΡ�2025ǯ��2026ǯ�ζ��Ӹ��̤����Ծ�ͽ�ۤ�ä�������ˤ���ƹ�ξ������Τ���������Ȥη�ǰ������꤬¾�����ˤ���礷�����ȥ����������Τ��䤷�ʤ�����������ϰ��Ū�˹���Ȥΰ����ˤȤäƥץ饹�ˤʤ뤫�⤷��ʤ��������Ū�ˤϾ����ʪ�����夲������Ԥι�����ߤ��व���뤿��˾����Ȥ����夲�ϸ�������ȤηбĿؤ���ľ�ʸ��̤������������ޥ����2��¤Ȥʤä���͢�����Ǥΰ����夲�о��ʤϴ���ȯɽ����Ƥ�����ư�֤�����ʤ˲ä����ں�����ꤽ��������ƻ���줿���Ʒʵ��θ�®���ǰ���ƶ�ͻ��Ϣ�����ˤ���꤬�ȵڤ���������ɥޥ��å�����JP��륬���������Ϥ��줾��4%����������ΤޤޤǤ��ƷкѤϥ���ե줬���ޤ�ʤ��ޤʵ�������̤κǽ����̤����뤫�⤷��ʤ������ΤȤ���������AI�֡���dzڴ�Ū�ǤϤ��뤬���⤷�����ʤ�ȡ���������Ĭ�ܤϾ夲Ĭ�������Ĭ�˵�ž������ΤǷٲ����դ�ʤ���
����ˡ����������ݸ����������21.9���͡ʡ�ͽ��21.5���͡ˤȰ�������1��ʵ���Իؿ���������-0.3%�ʡ�ͽ�ۤ��������Ѥ�餺�ˤȰ�����������ޡ����åȥ�������Ȥϰ����������夤�кѻؿ�������ơ���10ǯ������꤬������4.535%����4.507%���㲼�������������ȳ�30��ʿ�Ѥϰ����������677�ɥ�ޤdz��礹����̤⤢�ꡢ�����ޤ�2��Ϣ³�Ǽ��������Ƚ��ͥ١����ǻ˾�ǹ��ͤ����Ƥ���S&P500�Ⲽ������
����2��21��������Ծ�Ǥϡ�Ĺ��������15ǯ3����֤�ι���ʡ�1.455%�ˤ��դ����������ƹ���¤�ή�������ơ�����ʿ�Ѥ������沼���ƻϤޤꡢ�������ϰ��200�ߤ�Ķ�����������������溢������ο����������ۤ����ı�ͽ���Ѱ���ǡ������������˾徺����褦�ʾ����Ǥϡֵ�ưŪ�˹���㤤��������ۤʤɤ�פ�ȯ�������������Ĺ��������1.405%�ص���������������ơ��������Ǥϱ�����ī����149������Ⱦ���ä���Τ�150����Ⱦ�Фα߰¥ɥ�������˿��졢�������㤤�ᤵ�������ʿ�Ѥ�100��Ķ�夲����̤⤢�ä��������β����ߤ�ֿ��ĥץåȡפȤǤ�ɽ��������������Ǥ�3Ϣ�٤��Ƥ��뤿�ᡢ�Ѷ�Ū�˾��ͤ��ɤ�ư���ϸ¤�줿��
Ĺ�������ξ徺��Ĵ�ˤ��ᥬ�Хʤɶ�Գ��ξ徺��Ĵ�������Ǥ��롣���������ᥬ�Хʾ��ȿ�����Ƥ���Τ���ŷ��ԡ�24ǯ����32%��ˤ佻��SBI�ͥåȶ�ԡ�Ʊ17%��ˤʤɥͥåȶ�ԤǤ��롣ʪ��Ū��Ź���֤�����ʤ���������¤��ޤ���졢��ΨŪ���¶��뤳�Ȥ��Ǥ����⤤����Ψ�����ԤǤ��뤫�����
3�������ȵ������Ȥ���Х����Ū������Ф��Ƥ���Ϥ��Ǥ��롣����Ĺ���������徺��Ĵ�ˤ��뤿�����ĤΥ������Ȥ��㲼���Ƥ��롣���Τ���ƥ����åȥ��饹����Ψ�����ͤ��᤹����˹���Ĥ��㤤�����ܳ��ΰ�������뤳�Ȥˤ����Ƥ���ݡ��ȥե��ꥪ�λ�������᤹����Ԥ������������β����ǡ����Ӹ��̤��˴ط��ʤ��ɤ�����������Ƴ����ϰ��Ū�˲����롣�������㤤�Υ���Ȥʤ롣
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ������α������Ф��Ʋ������������в�Ƭ�ˤ֤Ĥ���褦�ʷ��Ρֽв����פȤʤä������η��ϲ�������ư����ߤ�Ȳ�ᤵ��롣���������3Ϣ�٤δ֤˥ȥ����������Τ���������Ф�������ǡ��ۤܤ��������̤��ư���ˤʤ뤫�������Ϥ������Фʤɿ���֤褦��ư���뤫����ޤ��������
���㡼�ȡ���ǥ������Ω�Ĥ���������ư�����Τϥ��㡼�ȤǤϤʤ����Ȥ�˺��ƤϤ����ʤ��������ξ夲�����ϡָ��ݡפǤ��ꡢ���Ƥθ��ݤˤ�ɬ�����Ρ���ͳ�פ����롣������ͳ�ˤϤޤ��֤��β�����ͳ�פ����롣�����顢���������㲻�Ǥ�����������طʤ��Ѳ��������Ƥ���ɬ�פ����롣��������Фɤ���Ѳ��夬��������Ǥ��Ƥ�Ƥ뤳�Ȥʤ�Ŭ�ڤ��н�Ǥ��롣
33�ȼ���19�ȼ郎�夲�����徺Ψ�ȥå�5�ϡ������ʡ�1�̡ˡ��������ʡ�2�̡ˡ��ݸ���3�̡ˡ��������4�̡ˡ������5�̡ˤȤʤä���
���������
�߹�ȥȥ��״��Ǥ���Ŷ� 02��20��
�������ƹ�������Ͼ���³��������DJIA +71.25 @44,627.59, NASDAQ +14.99 @20,056.25, S&P500 +14.57 @6,144.15�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�150������Ⱦ��������߹�ɥ�¿��Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤ϲ�����������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������249���Ф��ơ�������������1,344�Ȥʤä���ƭ��쥷����110.73%����ڥץ饤�����������4��4888���ߡ�
TOPIX -33 @2,735
����ʿ�� -487�� @38,678��
�ƹ�Ǥϡ��ȥ��������Τδ�����������Ϣˮ�����Ծ�Ѱ����FOMC�˵Ļ�Ͽ������Ƭ���ޤ������ɲ��������Τ���ˤϤ���ʤ�ʪ��������夭��ɬ�פ��Ȥ����ˤ���10ǯ������꤬�㲼������������4.544%����4.534%�ءˤ��Ȥ��������ɤ����Ȥʤä���ȾƳ�γ��ϸ��¤߷�Ĵ�ǥե���ǥ�ե���ȾƳ�γ��ؿ���SOX�ˤ�1.18%�夲�����ȥ��������Τϡ���ư�֡�ȾƳ�Ρ������ʤ��Ф���25%��͢�����Ǥ�ݤ����ˤ������������оݹɤ��ˤʤ뤫�ϼ�������ȯư����Ƥ�4��2���ˤʤ�Ȥ�����
����2��20��������Ծ�Ǥϡ��������륦���饤�ʾ����ʥȥ����������Τȥ�����������饤�������Τ�ȿ�ܡˤ���Ϣˮ���������������FRB�ˤ����̡�QT�ˤ���ߤޤ��ϸ�®����ʡ�Ĺ�������ˤ��㲼���ϡˤȤδ�¬�˲ä��ơ�������ɲ����夲��¬�ˤ�곰�ٻԾ��1�ɥ��149����α߹�ɥ�¤��ʤ��������ο����������ۤ���20������˼��괱š�������м���Ȳ��̤����������Ĥ��Ф��Ƥϡ��ֶ�ͻ���кѤ��Ф������Ū�ʰո����פȽҤ٤������ޡ����åȤ��ɲ����夲�Τ���κ����ä��ΤǤϤʤ����ȴ����ä���
���η�̡��ȥ西��ư�֤ʤ�͢�д�Ϣ�������濴����꤬ͥ���Ȥʤꡢ�������������ȵڤ���������ʿ�Ѥβ������ϰ��700�ߤ�Ķ�������ޤ������������Ѥ��������ô���礭���ʤ�ȹ�����ߤ������뤿�����夲����������Ȥȸ�Ω�Ƥ��顢������ư���ʤ���ư��������������Ω�ä����줿�����Ǿ夲��Ĵ���ä��ɱҴ�Ϣ������ȾƳ�δ�Ϣ��������Ĵ���ä����̾�ʤ�߹�ɥ�¤��ɤ����Ȥʤ�Ϥ��Υ˥ȥ�ޤ����졢�����Ĺ�������徺��1.440%�ءˤ���������礫������Ȥʤ�Ϥ��ζ�Ԥ����줿�������徺���ʵ��ι����ޤꡢͻ��Ĺ�������ƶ�Ԥμ��פ��������ͤʤ��Ȥη�ǰ�������ʤä��褦����
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ���ǯ10���ܤ���³���Ƥ����ݤ��礤��ο������դ꤫�鲼�����礭��ư���������¤�37,600���դ�ʤΤǤޤ�1,000�ߤۤɤΥޡ�����Ϥ��롣��������ǯ8���ܤλ��Τ褦�˲������Ƥߤ��դ���û���֤ǤӤä��ꤹ��ۤɵ���뤳�Ȥ⤢��Τǡ��ٲ��Ǥ��롣
�Ŀ�Ū�ˤϻ�ɩUFJ��Ϥ���Ȥ����㤤�̤Ϻ���������������ꤷ���Τǡ��������̤������̤Ϥʤ��Ǥ����㤤�᤹�����ߥפ�äƤ��ޤ���
33�ȼ���28�ȼ郎������������Ψ�ȥå�5�ϡ����ߡ�1�̡ˡ�����¾���ʡ�2�̡ˡ���Ŵ��°��3�̡ˡ������ӥ���4�̡ˡ���̩�����5�̡ˤȤʤä���
���������
��ɩUFJ�����㤤�̤������������ǰ�ö������ 02��19��
�������ƹ�������Ͼ����徺������DJIA +10.26 @+44,556.34, NASDAQ +14.49 @20,041.26, S&P500 +14.95 @6,129.58�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�151�����Ⱦ�Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤ϲ�����������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������596���Ф��ơ�������������994�Ȥʤä���ƭ��쥷����118.00%����ڥץ饤�����������4��5866���ߡ�
TOPIX -8 @2,767
����ʿ�� -106�� @39,165��
�ƹ�Ǥϡ�����ƥ뤬16%�徺���ƶ����AMD��ȾƳ����¤���֤Υ��ץ饤�ɥޥƥꥢ�륺��徺����������Ǥ����������ΤȤ��ƤϾ��ͤ��Ť��ä��������Ǥ���ʪ���徺���ϤϤޤ�����ʤΤˡ��ȥ��������Ϲ����������䤷�ʤ�褦�Ȥ��Ƥ��롣����ե줬���Τ˼�«���ʤ�����Ϣˮ���������������FRB�ˤ��ɲ��������ˤϤʤ��ʤ�Ƨ���ڤ�ʤ������η�̡����������夲�륨�ͥ륮�����ϳ餷����롣���äȤ�����ɤߤ���������
����2��19��������Ծ�Ǥϡ�����ι����Ͽ��İ���19���εܺ긩��ͻ���̲�Ƕ�ͻ���ﲽ���Ѷ�Ū�ʡ֥����ɡפ��Ȥ��ơ����ٻԾ�Ǥϱ߹�ɥ�������˿��졢�������Ǥ���꤬ͥ���Ȥʤä����ȥ����������Τδ��Ƕ��������Ф���ٲ����⤢�ꡢ����ʿ�Ѥβ������ϰ��300�ߤ�Ķ�������ƹ��͢�����Ǥ��⤯�ʤ�Сʸ�ĤΤ����ñ�ʤ붼���Υ����ɤβ�ǽ����ˤ���˰��ƶ�������륻�������ϼ�ư�֤Ǥ��뤿�Ἣư�ִ�Ϣ���ϲ�����������Ĺ�������ʿ�ȯ10ǯ�������ˤ�1.435%�ޤǾ徺����Ĺ�������徺�β��ä�������Գ��Ϸ�Ĵ���ä�����ɩUFJ��Ϣ���Ǿ������ͤ�������
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ����Ҥ��������û�����ʺ����Ͼ�Ҥ��������û�����ˤȤʤꡢ������Ȥ����˲������㤤�����ä�����ˤⲼ�ˤ��礭����ư���ʤ�������ȤʤäƤ����������֤�Ĺ���ʤ�ۤɡ����ͥ륮�������Ѥ����ΤDz����Τ��ä��������줿��硢���������ؤ�ư����®���ʤ롣
�Ŀ�Ū�ˤ�������ɩUFJ�����㤤�̤������������ǰ�ö�������ޤ�����������в����ߤޤä��Ȥ��������ᤷ���夲��ʤ�ǹ��ͤ������Ȥ����Ǥޤ��㤤ľ�������Ǥ��������ø���ȷ����֤������Ǥ���â������˳������������㲻���ɤΤ褦���Ѳ����Ƥ��뤫�����뤷�Ƥ��ޤ�������ˤ����ά���Ѥ�뤫��Ǥ���
33�ȼ���16�ȼ郎�夲�����徺Ψ�ȥå�5�ϡ��ѥ�ס����1�̡ˡ���°���ʡ�2�̡ˡ�����¾���ʡ�3�̡ˡ����饹�����С�4�̡ˡ��ڷ���5�̡ˤȤʤä���
���������
Ĺ�������ξ徺��Ĵ�������ʤΤǶ�Գ�������줬������ 02��18��
�������ƹ�����Ծ�ϥץ쥸�ǥ�ȥǥ��ν����ǵپ���ä����ɥ�߰��إ졼�Ȥ�151�����Ⱦ��������߰¥ɥ����Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤��;夬���������������Ͳ�����������������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������930���Ф��ơ�������������664�Ȥʤä���ƭ��쥷����113.98%����ڥץ饤�����������4��3533���ߡ�
TOPIX +9 @2,776
����ʿ�� +96�� @39,270��
�����Ǥϡ�2��16���ޤDz��������ƥߥ��إ�����ݾ��Ĥ���17���ˤϥѥ�ǥ����饤�ʾ����˴ؤ���۵�礬���Ť��줿�������Ǥ��ɱ��϶����Τ���˷����ٽФ����ä���������Ф������������ƥɥ��Ĥ��ɱ������饤�������14%��ƭ�����������Ծ�ǤϷ����������ʤ�Ȥθ�Ω�Ƥ����ɱҴ�Ϣ���������줿���Ȥ��ݤ���ˡ�����2��18��������Ծ�Ǥ����Ź���IHI����ɩ�Ź����������ݽ�ʤɤ��ɱҴ�Ϣ�������夲����
Ĺ�������ξ徺�������ˤʤäƤ���ʰ��1.430%��2009ǯ11�����15ǯ3����֤�ˤΤǻ�ɩUFJ�ʤɶ�Գ������³�����줿���ޤ����߹�ɥ�¤�ư�������������ΤǼ�ư�ֳ������줿������ʿ�Ѥξ夲���ϰ��300�ߤ�Ķ������17����ȯɽ���줿2024ǯ10��12���������������GDP�ˤϻԾ�ͽ�ۤ�Ķ���Ƥ��ꡢĹ�������ξ徺���Ƥߤ��դ�����
2022ǯ�˥������������饤�ʤط��������Ϥ��ư��衢����Ū�˹�ʪ���ʤ丶�����ʤ��徺�����褿������˱߰¥ɥ���ä�ꡢ����ȯ��ʪ���⤬������ȵڤ��볰��Ū��͢������ե줬�����äƤ��롣�������������ˤ��ƾ��ҹ��Ȥ�����¤Ū�ʸ����������ͼ����������ȯ������Ū����ե��ŤʤäƤ������ޤ����Ծ줬�ɤ����٤Υ���ե�����Ǥ���Τ����֥졼���������֥���ե�Ψ��BEI�ˤ�2020ǯ�ϥޥ��ʥ������ä��Τ˺���1.6%��ޤǾ徺���Ƥ��롣���䤬��ɽ������륮��åפϲ���ǯ�ϥޥ��ʥ����ä������ͼ����ʤɤ�ϫƯ���֤����äʤɤ��̣���Ʒ�����ȡ����륮��åפ�2022ǯ�ƺ�����ץ饹��ž���Ƥ����Ȥ�����Ŧ��Ф��褿���ˤ⤫����餺���¼����������Τ˥ޥ��ʥ��������߹�����ޤޤǤ��롣ɹ�����ɻ����������ۤ�1��30���ιֱ�ǡּ¼��������Ϥä���ȥޥ��ʥ��ξ��֤����ä�³���Ȥ����Τ����̤λѤȤϤ��ʤ��פȽҤ٤����ȥ����������Τ���ᥭ������Ϥ���Ȥ��볰��Ȥ�����Ū���ǰ��ֻ�������뤷�Ƥ��ꡢ���Ǥ�����夲���ƹ�ؤ�͢�����������褦���Ƥ��롣���ܤ⤽���оݹ�Ǥ��롣���������إ졼�Ȥˤ����뤷�Ƥ��롣���ΤȤ�����Ĺ�������ξ徺��ٲ����ƥɥ�����ǧ���Ƥ��뤬���ܲ��ϥɥ�¤ޤ���Ϥ��Ǥ��롣�ʤ��ʤ顢�ɥ����ƹ��͢�Ф�岡�������ƹ�ؤ�͢�����������뤫������������äơ����䤬�ɲ����夲��»ܤƱ߹�ɥ�¤ˤʤ뤳�Ȥ��ä˰۵ĤϾ����ʤ������������Τ褦�˳��٤��塹����ޤꡢ���䤬�ɲ����夲���䤹���Ķ��������ĤĤ��롣
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ�����³����������Ĺ����Ҥ��������û�����ǽ����������ͤǤ϶�����갵�Ϥˤ�겡���ᤵ�줿���Ȥ��̣���롣10����25����60����260���Τ��٤Ƥΰ�ưʿ�����ξ�ǿ�ܤ��Ƥ��ꡢ�夤�����Ϥ��ʤ�������ǯ10���ܤ���³���Ƥ����ݤ��礤���������˾�����Ǥ������ʤۤɤޤ������Ϥʤ���
33�ȼ���18�ȼ郎�夲�����徺Ψ�ȥå�5�ϡ���ԡ�1�̡ˡ��ŵ���������2�̡ˡ�������3�̡ˡ�Φ����4�̡ˡ��۶ȡ�5�̡ˤȤʤä���
���������
����Ĺ��������15ǯ�֤�ι���ȤʤäƤ����Τǡ����� 02��17��
�轵���������ƹ�������Ϲ�¤ޤ��ޤ��Ȥʤä���DJIA -163.35 @44,456.08, NASDAQ +81.12 @20,026.77, S&P500 -0.44 @6,114.63�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�151�����Ⱦ���轵����߹�ɥ�¿��Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤��Ͳ�������������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������589���Ф��ơ�������������1,000�Ȥʤä���ƭ��쥷����108.58%����ڥץ饤�����������4��3941���ߡ�
TOPIX +8 @2,767
����ʿ�� +25�� @39,174��
�轵���������ƹ�Ǥϡ����������ˤϥȥ�����������ߴ��Ǥ�¨��ȯ�Ԥ��������Ƥ����Ȥ����ء���1�������⤬ͽ�۰ʾ�˰�������������-0.9%��ͽ��-0.1%�ˡ����������Ԥ��Ƥӹ�ޤä������Τ�����10ǯ������꤬������4.525%����4.478%���㲼����������Ǥ�����ؿ��Ϲ�¤ޤ��ޤ��Ȥʤä���2��17���ϥץ쥸�ǥ�ȥǥ��ν����dz����Ծ�ϵپ�Ȥʤ롣
����2��17��������Ծ�Ǥϡ�����դ�����ȯɽ���줿2024ǯ10��12����ι�����������GDP��®���ͤ��Ծ�ͽ�ۤ���ä���������ǯΨ2.8%�ˡ����������������͢�Ф���Ĵ���ä������������ơ�����Ĺ���������徺����1.375%��2010ǯ4�����15ǯ�֤�ι���ˡ�������������ǻ�ɩUFJ���������ʤɶ�Գ����ݸ���������ƾ徺������
¾������������徺�ϱ߹�ɥ�¤�ʹԤ����뤳�ȤȤʤꡢ��ư�ֳ���Ϥ���Ȥ���͢�д�Ϣ���������ͥ���Ȥʤ겼��������ư�ֳ��ˤϤ⤦��ļ��������롣����ϥȥ��������ΤΡָ�����פǤ��롣�ȥ��������Τ�͢����ư�֤��Ф��붯���������֤�4��2����ȯɽ�������ˤ�Ҥ٤����ᡢ�����ư���ȤʤäƤ��롣
������������Ȥ��ơ��ե��ʥå��䥭���������줿��2025ǯ3������Ӹ��̤���徺����������������������夲������ꥪ�ϥ��ȥå�ޤ����줿����������Ȥ���Ĵ�Ƕ��Ӹ��̤���徺�����������ˡ����롼�פ�����Ƴ����Ͼ������ͤ�Ϣ���ǹ����������ޤ����������Ф������Ǥϡ����������ΰ����夲�ȼ��ҳ��㤤�ʺ���3,000���ߡˤ�ȯɽ�����֥�¥��ȥ�����줿����2025ǯ3����������̤������������������ѥ������줿��2024ǯ12����軻���ֻ��Ȥʤä����̥��롼�פ��礭�����줿��
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ��Ϥ��˾徺����10��25��60����ưʿ�����ξ��α�ޤäƤ��뤬����ǯ10���ܰ���Υ�������Ǥ�ư���˲�ʤ�����˼����뤿��ˤϴ��Ǥ�����Ʃ���������Τ˸��ह��ɬ�פ����롣
33�ȼ���17�ȼ郎�夲�����徺Ψ�ȥå�5�ϡ��������ʡ�1�̡ˡ���������ú��2�̡ˡ�����¾���ʡ�3�̡ˡ��ŵ������4�̡ˡ���ԡ�5�̡ˤȤʤä���
���������
�ȥ��������ΤΡ���ߴ��ǡ��������夲�������礭�ʺ��� 02��15��
����2��13���Ͻ����������Υ�졢��������˿��ȴۼ�ŤΥѡ��ƥ����˻��ä��Ƥ��Ƥ��������ͽ�꤬�ͤޤäƤ��ꡢ����˻�����ä����ᡢ�֥����ι����٤ߤ��ޤ���������21:00��˵��𤷤ޤ�����
���ơ��������ƹ������ȿȯ������DJIA +342.87 @44,711.43, NASDAQ +295.70 @19,945.65, S&P500 +63.10 @6,115.07�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�152������Ⱦ�Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤ϲ�����������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������473���Ф��ơ�������������1,116�Ȥʤä���ƭ��쥷����105.69%����ڥץ饤�����������4��9570���ߡ�
TOPIX -6 @2,759
����ʿ�� -312�� @39,149��
�ƹ�Ǥϡ��ƥȥ��������Τ���ߴ��Ǥ�Ƴ����ո���������¨���¹Ԥ��ʤ����Ȥ�Ƚ���������ƹ�Ȥδ��Ǥ�ܺ٤�Ĵ�پ夲��4��1���ʹߤ���ߴ���Ƴ�������ȤΤ��Ȥ��������δ֤�������Ф��ƾ����������ά�Ȥ�ͤ����롣���ܤ��Ф��Ƥϼ�ư�֤��濴������Ǿ��ɡ�NTB�ˤ�����˼��夲���ɤ��֤�������Ϥ�������1��������ʪ���ؿ���PPI�ˤ������ƶ�����̤Ȥʤä�����ǯ��+3.5%��ͽ��+3.2%, ������+0.4%��ͽ��+0.3%�ˤ�����10ǯ��������������4.637%����4.530%���㲼������������ȯɽ���줿�ƾ����ʪ���ؿ���CPI�ˤ������ä��ˤ⤫������餺�Ǥ��롣��Ϣˮ���������������FRB�ˤ��Ż뤹��Ŀ;���ٽС�PCE�˲��ʻؿ����㲼�����Ƥȼ����ߤ��줿����Ǥ��롣
����2��14��������Ծ�Ǥϡ��ȥ����������ΤΡ���ߴ��ǡפ�¨���¹ԤȤϤʤ餤�ʤ����Ȥ������㤤ͥ���Ȥʤä�����ߴ��Ǥ�¨���»ܤ�������ˤʤꡢ����ʬ�������Ǥˤ�륤��ե�ʹԤ��٤�뤿�ᡢ��Ĺ�������ξ徺�Υڡ������٤��Ϥ����Ȥ������Ȥ����ƶ��������̾�����Τǡ��߹�ɥ�¤ˤʤ�ȤΥ��ʥꥪ����ή���ä���������͢�д�Ϣ�����ΰ�Ѥ����줿��2025ǯ3����軻���̤��ξ���������ȯɽ�������ˡ����롼�פ�������Ȥʤä���
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ������������������α������ۤܤ��٤��Ǥ��ä����������25����ưʿ�����ξ��α�ޤäƤϤ��뤬��10����25���Ϥ�䲼�����ʤΤǡ��ɤ��餫�Ȳ��˿���䤹������������ǯ10���ܤ����Ȥ����ݤ��礤�����Ǥξ岼ư��³���Ƥ��롣
33�ȼ���27�ȼ郎������������Ψ�ȥå�5�ϡ���Ŵ��°��1�̡ˡ������ʡ�2�̡ˡ��������ʡ�3�̡ˡ��ѥ�ס����4�̡ˡ�������5�̡ˤȤʤä���
���������
�ȥ��״��ǤȤ��αƶ��Ȥ��Ƥ�Ĺ�������ξ徺 02��12��
�������ƹ�������Ͼ徺������DJIA +123.24 @44,470.41-70.41 @19,643.86, S&P500 +2.06 @6,068.50�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�153����Ⱦ�Ф��轵����߰¥ɥ����Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤Ϲ�¤ޤ��ޤ��Ȥʤä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������851���Ф��ơ�������������743�Ȥʤä���ƭ��쥷����100.21%����ڥץ饤�����������5��4101���ߡ�
TOPIX ��0 @2,733
����ʿ�� +163�� @38,964��
�ƹ�Ǥϡ��ѥ�����FRB��Ĺ���ƾ屡��Ѱ���ǡ��ƷкѤϰ����Ȥ��ƹ�Ĵ�Ǥ��ꡢ����������Ĵ����ޤ�ɬ�פϤʤ��פȾڸ�����������ȯ���ϳ������ˤϽŤ��Ȥʤä����ѥ�����FRB��Ĺ�Υ�����ȯ���˲ä��ơ��ȥ��������Τι����������Ŵ�ݡ�����ߥ˥����͢���ʤ�25%�δ��Ǥ�ݤ�������ϼ�ư�֡�ȾƳ�Ρ������ʤˤ�����Ƥ��ˤˤ��͢��ʪ�����徺���ƺƤ��ƹ�кѤΥ���ե줬��dz����Ȥη�ǰ���顢��10ǯ��������������4.495%����4.437%�ؾ徺��������Ĺ�������ξ徺��ȿ�Ǥ��ơ����ٻԾ�Ǥϱ߰¥ɥ�⤬�ʤ���������Ͽ������ˤ�1������ʪ���ؿ���CPI�ˡ��������ˤ�1��������ʪ���ؿ���PPI�ˤ�ȯɽ�����ꡢʪ��ư���˥ޡ����åȤδؿ������ޤ롣
����2��12��������Ծ�Ǥϡ��ե������ȥ�ƥ���䥽�եȥХ��롼�פʤɤ��Ϳ��������ƾ徺�����������ƥȥ��������Τι���������������кѤν̾����ǰ����������������Ȥη�ǰ����ȥ西��ư�֤�ۥ����Ϥ���Ȥ��뼫ư�ֳ��ϸ��¤����줿����컰���ʤɰ����ʤ����줿����ƣ�Ƽ��кѻ������12���γյĸ�ε��Բǡ��ƹ�Ŭ�Ѥ���Ŵ�ݡ�����ߥ˥���ؤ�25%���ɲô��ǤˤĤ��ơ��������ܤ������оݤ������ܴ�Ȥ��������褦�˿������줿�פȽҤ٤������������ο������줬ʹ�������뤫�ɤ�����̤�ο��Ǥ��롣���ǥꥹ���αƶ������ܳ��ˤޤ���ʬ������ޤ�ƤϤ��ʤ���
��Ĺ�������ξ徺�����ܤκķ��Ծ�ˤ��ȵڤ��Ƥ��롣10ǯʪ��ȯ��Ĥ�������1.340%�ؾ徺�����褿�������2011ǯ4�����14�֤�ι⤤���Ǥ��롣���䤬�������ꤵ�Ƥ��������ᤤ�����ߥ��ɲ����夲��»ܤ������Ǥ���Ȥ�����¬�����������κǽ���ã���ʥ����ߥʥ롦�졼�ȡˤ��ڤ�夬�ꤽ�����Ȥ�����Ω�Ƥ��طʤˤ��롣
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ�ȿȯ���ƻϤޤä��������ᤵ��Ƥޤ������ǽ���������ư���ϰ����Ȥ���2��3����4���α������ϰ���Ǥ��롣�����Ǥ��Ф��Ƥ���ȥ��״��ǤȤ��αƶ����ɤ��ڤ줺�����ư�����ޤ����Ф餯³����������
33�ȼ���16�ȼ郎�夲�����徺Ψ�ȥå�5�ϡ���Ŵ��°��1�̡ˡ��۶ȡ�2�̡ˡ�������3�̡ˡ����饹�����С�4�̡ˡ��建�����ӡ�5�̡ˤȤʤä���
���������
�����м�����ƥȥ��������Τβ��̤�̵����̲� 02��10��
�轵���������ƹ���������礭���������DJIA -444.23 @44,303.40, NASDAQ -268.59 @19,523.40, S&P500 -57.58 @6,025.99�ˡ� �ɥ�߰��إ졼�Ȥ�152������Ⱦ�Ǥ�ư�����ä���ƭ��쥷����95.31%����ڥץ饤�����������4��2299���ߡ�
TOPIX -4 @2,733
����ʿ�� +14�� @38,801��
�ƹ�Ǥϡ���1��������פη�̤���ɽ���줿��������������ѼԿ���ͽ�ۤ�ä���14.3��������ͽ��17������������ʬ30.7�������ˡ�����Ψ�ϲ�������4.0%������ʬ4.1%�ˡ�ʿ���¶��������+0.5%��ǯ���4.1%��ͽ��+0.3%, +3.8%�ˤϾ徺������2��ߥ�������ؾ���Կ��괶�ؿ�®���ͤϼ夤��̡�67.8%��71.1%�ˤȤʤä�����1ǯ����ԥ���ե�Ψ®���ͤ��礭���徺������4.3%������ʬ3.3%�ˡ��к�����ɸ��ȯɽ������ơ���10ǯ��������������4.438%������4.515%�ؾ徺�������Ȥǡ��ɲ����������Ԥ����ष�����ȥ��������Τ������ʴ����������Ǥ��Ф����Ȥ��Ф���ٲ�����Ťʤꡢ����3�����ؿ���·�ä�ȿ�����
����2��10��������Ծ�Ǥϡ��ƹ���¤�ή������������ʿ�Ѥϲ����ƻϤޤä��������θ���ڤ��֤��ƾ�����ǽ������������м�����ƥȥ��������Τβ��̤�̵����̲ᤷ���Ȥθ�������ή�Ȥʤꡢ���٥���̲�ˤ�ꡢͽ�������ƤƤ�������ʪ�������㤤�ᤷ��������Ͷ�š��ǥ������̥��������ӡ��ե�����ʤɹ�������������ľ�������������Ȥʤä�������������ʿ�ѤǤϾ��ͤ��㤤�夬�����Ȥ���ư����˳�����������طʤˤϡ��ȥ��������Τδ����������ƹ�͢������Ŵ�ݡ�����ߤ��Ф���25%�δ��Ǥ�ݤ��������ƹ����ʤ˲ݤ��Ƥ���Τ�Ʊ����Ψ��ݤ�����ߴ��ǡסˤ��Ф���ٲ��������ꡢ����ˡ����ܸ�ͭ�λ���Ȥ��ơ�������ɲ����夲�����ꤹ�뤫�Τ褦�˶��������露��Ⱦ徺���Ƥ��뤳�Ȥ����롣����ķ��Ծ�Ǥϡ�10ǯʪ��ȯ�������꤬���1.32%��2011ǯ4�����13ǯ10����֤�ι���ˤޤǾ徺������
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ������ƻϤޤä��塢�ڤ��֤���û�����ǽ���������2��3����4���α�����������Ǥ�ư�����ޤ���³���Ƥ��롣
33�ȼ���18�ȼ郎�夲�����徺Ψ�ȥå�5�ϡ��ѥ�ס����1�̡ˡ��۶ȡ�2�̡ˡ���Ŵ��°��3�̡ˡ���������ú��4�̡ˡ�������5�̡ˤȤʤä���
���������
���軻ȯɽ�Ƥ�����롧���Τ����Ƥ��뤫�� 02��08��
�������ƹ�������Ϲ�¤ޤ��ޤ��Ȥʤä���DJIA -125.65 @44,747.63, NASDAQ +99.66 @19,791.99, S&P500 +22.09 @6,083.57�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�152������Ⱦ�Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤ϲ������������������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������751���Ф��ơ�������������827�Ȥʤä���ƭ��쥷����93.65%����ڥץ饤�����������4��5765���ߡ�
TOPIX -15 @2,737
����ʿ�� -280�� @38,787��
�ƹ�Ǥϡ��ȥ��״��Ǥ���ߤĤĤ��ꡢ�����������Ф���ٲ������¤餤�Ǥ������������ϳ����ˤȤäƤ��ɤ����ȤǤ��롣�кѻ�ɸ�Ǥϡ����������ݸ�����������夤��̡�21.9���������ʬ20.8����ˤȤʤä�����������1��θ������ס�FRB���ɲ�����������뤫�ɤ����ν��פʥǡ����ˤ�ȯɽ���Ƥ��뤿�ᡢ�ٲ����Τ�����10ǯ��������������4.420%����4.436%�ؾ夲���������Ϲ�¤ޤ��ޤ��Ȥʤä���
����2��7��������Ծ�Ǥϡ������˹��軻��ȯɽ��2024ǯ4~12���Ϣ������פ�68%����4011���ߡˤ���������쥯�ȥ���4��Ⲽ�������̾�ʤ��㤤�����������Ϥ��������ƥȥ��������Τδ������������ա�������Ω��㲽�����������������쥯�ȥ�������夲���������������ǽ�����⤤�Ȥθ�Ω�Ƥ�������
�軻�β����ɤ��Ȥ��ơ����������Τ�̤��ζ��Ӥ��ɤ������Ǥ��롣����η軻ȯɽ�Ǥ϶��Ӹ��̤�������֤������Ȥ�ޡ����åȤ���Ԥ����Ф���ٲ������������ˡ�2025ǯ����ǯ�ˤ���������������¤���֡�WFE�ˤλԾ쵬�ϸ��̤���1,100���ɥ����٤ȿ����֤�����������쥯�ȥ���1��������������ʿ�Ѥ�106�߲���������������ˡ��߹�ɥ�¤��ʤߡ���ư�ֳ��ʤ�͢�д�Ϣ���������줿��2��7���ˤ������м��꤬�ƥȥ��������ΤȽ�μ�Ǿ���̤롣���κݤˡ��ȥ��������Τ��ֱߤϰ¤�����פȤǤ�����С��߹⤬��®�����ͤʤ���
����ķ��Ծ�Ǥ�Ĺ�������ξ徺��³���Ƥ��롣��ȯ10ǯ�������ϰ����1.30%�˾徺������2��5��ȯɽ��2024ǯ12������ϫ����Ĵ���Ǥϡ�ʪ����ưʬ��������¼��¶⤬��ǯ�������0.6%�徺��������������夲��������ΰ�ĤȤ����¶�徺��Ż뤷�Ƥ��롣���η�̡�����μ���кѺ����������꤬�����ϥ���ե�ξ��֤ǡ��������ˤ�ǧ���������Ϥʤ��ȡҤ١�������ɲ����夲����ͷ⤷��������������6���ˤϡ���¼ľ�����İѰ�����ͻ�кѺ��̲�ǡ�25ǯ��Ⱦ�ˤϾ��ʤ��Ȥ�1�����٤ޤ�û��������夲�Ƥ������Ȥ�ɬ�פ��פȤιͤ����������Ĥޤꡢ���ܤ�������ɲ����夲��Ĵ���Ƥܷۤ��Ƥ���ȸ����롣���줬Ĺ���������徺��Ĵ��³���Ƥ����طʤǤ��롣�����ơ��桹�Ŀ����Ȥϲ���ɤ����٤��������Τ褦��̤��Υ��ʥꥪ�ǡ��ɤ��������㤤�ɤ����������٤���������Ū�˹ͤ��Ƥ������ȤǤ��롣
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ�û������ȿ����ޤ�2��3������³���Ƥ����ݤ��礤�����¶�ǤΤ�꾮������������Ǥ�ư������ä����������פ�ȯɽ��ȴ���Ф�����
33�ȼ���23�ȼ郎������������Ψ�ȥå�5�ϡ����饹�����С�1�̡ˡ���̩�����2�̡ˡ���ư����3�̡ˡ�����¾���ʡ�4�̡ˡ�͢���ѵ����5�̡ˤȤʤä���
���������
ľ����3Ϣ³�������������ȴ���Ƥ��ʤ��������� 02��06��
�������ƹ��������³��������DJIA +317.24 @44,873.28, NASDAQ +38.31 @19,692.33, S&P500 +23.60 @6,061.48�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�152������Ⱦ�Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤Ͼ夲��������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������1,192���Ф��ơ�������������394�Ȥʤä���ƭ��쥷����99.41%����ڥץ饤�����������4��5201���ߡ�
TOPIX +7 @2,752
����ʿ�� +235�� @39,067��
�ƹ�ǤϤɤ����ޡ����åȤϥȥ��������δ�������������������褦�Ǥ��롣��10ǯ������꤬�㲼�������̥ӥǥ�����������Ȥʤä����кѻ�ɸ�Ǥϡ�1��ADP̱��������ѼԿ��ʡ�18.3���͡�ͽ�ۡ�15.0���͡ˤ�������̤Ȥʤä�������1��ISM����¤��PMI�ϼ夫�ä���52.8��ͽ��54.3���������54.0�ˡ����������Ρַʵ��θ�®�פ�������10ǯ��������������4.513%����4.426%���㲼�������4.400%��2024ǯ12��18������ο��ޤDz�����������3�����ؿ���·�ä�³��������
����2��6��������Ծ�Ǥϡ��ƹ�����ή�������ơ������굡�ڼ�Ƴ�dz����ؿ���ʪ���㤤����������ʿ�ѤϾ徺�������ƹ�Ǥϥϥ��ƥ����濴�Υʥ����å��ȥե���ǥ�ե���ȾƳ�γ��ؿ���SOX�ˤ��夲��ή��������������쥯�ȥ���䥢�ɥХ�ƥ��Ȥʤɤ��ͤ���ȾƳ�δ�Ϣ���������������ʿ�Ѥ��夲��������ʿ�Ѥξ夲���ϰ��300�ߤ�Ķ������
�������¼ľ�����İѰ���6������ͻ�кѺ��̲�ǡ�����������0.75%�ذ����夲���Ȥ��Ƥ⡢����³���¼������������˥ޥ��ʥ��ǡ��кѤ�����������ˤϤޤ���Υ������פȽҤ٤�������ȯ��������ơ��ɲ����夲�β��Ϥ�����˸Ǥޤä��ȸ��ơ������ϰ��151����ޤǾ徺������
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ�3Ϣ³�������ݤ��礤��β��¶�Ǥ⤿�⤿���Ƥ�������������û�����Ǿ夲�ơ��������ؤ��Ƥߤ��դ�����������ľ����3Ϣ³�������������ȴ���ƤϤ��餺�������ʹߡ�������뤫�ɤ������ܤ��Ƥ��롣
33�ȼ���27�ȼ郎�夲�����徺Ψ�ȥå�5�ϡ�������1�̡ˡ�����¾���ʡ�2�̡ˡ��ڷ���3�̡ˡ����饹�����С�4�̡ˡ���̩�����5�̡ˤȤʤä���
���������
����AI���Υ�����������Ϥޤä��� 02��05��
�������ƹ��������ȿȯ������DJIA +134.13 @44,556.04, NASDAQ +262.06 @19,654.02, S&P500 +43.31 @6,037.88�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�152�����Ⱦ��������߹���Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤Ͼ夲��������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������940���Ф��ơ�������������645�Ȥʤä���ƭ��쥷����100.41%����ڥץ饤�����������4��7836���ߡ�
TOPIX +7 @2,745
����ʿ�� +33�� @38,831��
�ƹ�Ǥϡ��ȥ����������Хᥭ���������ʥ����Ф���25%�δ���ȯư��30���ֱ�������������������ɲô���10%��ȯư������������������ȯư��10������Ŭ�ѡ���ú���ղ�ŷ����15%�����������ȵ�����10%�ˤ�ȯɽ������12��JOLTS��ͷ�����夫�ä���760�����ͽ��800����ˤ��Ȥ˲ä���12����¤�ȿ��������Ⱝ�������������桾0.9%��ͽ�ۡ�0.7%�ˡ����η�̡���10ǯ������꤬������4.54%����4.51%���㲼����������3�����ؿ���·�ä�ȿȯ������
����2��5��������Ծ�Ǥϡ��ƹ�ϥ��ƥ����ξ徺��ή�������ơ����եȥХ��롼�פ�ȾƳ�δ�Ϣ�����ΰ�Ѥ����줿���ȥ西��ư�֤�25ǯ3�����Ϣ��������̤������������������ǯ��28%����3��5700���ߤ���9��4��5200���ߤء��߰¸��̤�5400���ߡˤ��Ȥ���������Ƶ��������������ۥ���Ȥηб�����˸��������ܹ�ս��MOU�ˤ�ű�����ˤ��������ȥۥ����8%��ȵ�������
����ϫƯ�ʤ�5����ȯɽ����2024ǯ12�������ϫ����Ĵ���ǡ��¼��¶⤬��ǯƱ����0.6%�徺���������2����Ϣ³�ξ徺�Ȥʤä������ηкѻ�ɸ�����䤬���夲��ݤ˽��뤹���ɸ�ΰ�ĤǤ��롣�кѻ�ɸ���¶�ο��Ӥ���ǧ���줿���Ȥǡ�������ɲ����夲�β�ǽ���⤯�ʤä��Ȳ�ᤵ�줿�����η�̡��߹�ɥ�¤��ʤ��������ķ��Ծ�Ǥϡ�10ǯʪ��ȯ��Ĥ������ϰ��1.295%��2011ǯ4�������ơˤޤǾ徺������
�����������γ�νȯ����߹�ɥ�¤�¥�ʤ���������μ���кѺ����������꤬5�������ν��ı�ͽ���Ѱ���ǡ����ϥ���ե�ξ��֤ǿ����������ۤ�ǧ�����ä������Ϥʤ��פȽҤ٤������������ˤ����������ܤ���⤪���դ�����ä����Ȥˤʤꡢ�ɲ����夲��»ܤ��䤹���ʤä��ȸ����롣
���DeepSeek��ɽ����ؤ��о�ϥ���������Ȥʤ뤫�⤷��ʤ������礦�����Ǥμ���1����ɴ���ߤ⤹��ǿ�����Ʈ������1��5~10���ߤ��㤨��ɥ�������Ѥä��褦�ˡ��ǿ��Ƕ���GPU������Ǥ��ʤ��ʤ顢���եȥ��������䤦���ȤDz��Ȥ��ʤ�������椬�����դ�����DeepSeek�о�����1��24��������2��5���δ֤γ������Ѳ��ˤ��Υ�������������ꤷ�����Τ褦��ư�������롣���ɥХ�ƥ��Ȥ�16%�¡��ե������14%�¤Ȥʤä��ʥǡ���������������������¤���ּ��פ��㲼����Ȥ��ɤߡˤ���AI�����ӥ��˶���NEC��17%�⡢��¼������15%���AI��Ȥ����եȥ������ؼ�����ư����Ȥθ�Ω�ơˤȤʤäƤ��롣
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ����ͤǤϾ�����Ȥʤä���3Ϣ³�����Ǥ��ꡢ�褷�ƶ����Ϥʤ�������Ǥ�������¤��Ȥ���ʤ���㤤�����äƤ���Τǡ���ۤ��礭�ʰ������Ǥ����ӽФ�����ʤ����10���ܤ����³���Ƥ����ݤ��礤���β��¤˶��դ��ۤ��㤤�������Ʋ����ߤޤ꤫�餢�����٤�ȿȯ��ư���ˤʤ�ȸ��Ƥ��롣�ȥ��������δ����������ޤ����˻볦���ɤʤ��ᡢ���ܳ��������ư������ʬ�δ�³����������
33�ȼ���16�ȼ郎�夲�����徺Ψ�ȥå�5�ϡ�������1�̡ˡ�����¾���ʡ�2�̡ˡ�͢���ѵ����3�̡ˡ������̿���4�̡ˡ��Ҹˡ���͢��5�̡ˤȤʤä���
���������
���Ǥ����ˤ����֥ȥ���ˤ�פ˿����� 02��04��
�������ƹ�������Ϥ�����³��ǻϤޤä��塢��������̾����ƽ�������DJIA -122.75 @44,421.91, NASDAQ -235.48 @19,391.96, S&P500 -45,96 @5,994.57�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�155������Ⱦ�Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤Ͼ徺�����������������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������858���Ф��ơ�������������721�Ȥʤä���ƭ��쥷����99.61%����ڥץ饤�����������4��8961���ߡ�
TOPIX +18 @2,738
����ʿ�� +278�� @38,798��
�ƹ�Ǥϡ��ƥȥ��������Τ������˥ᥭ�����ȥ��ʥ������͢���ʤ�25%�δ��Ǥ�ݤ�������͢���ʤ�10%���ɲô��Ǥ�ݤ���ȯɽ�����������кѤν̾����ƹ����ʪ���徺��ǰ����ޤꡢ�������ȳ�30��ʿ�Ѥϰ��660�ɥ����������ᥭ���������⤷�ƥᥭ�������Ф������ȯư��1�������ߤ�����ȯɽ���줿���ᥭ�������ƹ�ؤΰ�ˡ��ʪ�ʹ��������ե��˥�ˤ��ƹ�ή������ˡ��̱�ɻ��к��Ȥ���1���͵��Ϥη������ɸ�����ȹ�դ�������Ǥ��롣���٤ʷٲ������¤餮������3�����ؿ��ϲ�������̾����ƽ�������������ˤʤä��������ʥ�������ζ�������«�������ʥ����Ф������ȯư��30���ֱ����������ƻ���줿�����ǤϤ�Ϥ�ȥ���ή�Ρ֥ǥ�����פμ��ʤΤ褦����
����2��4��������Ծ�Ǥϡ��ƹ�ȯɽ���Ƥ����ᥭ���������ʥ����Ф������ȯư���������ȯɽ�������Ȥǡ������кѤؤΰ�����ǰ���¤餮������ʿ�Ѥ�ȿȯ����������ʿ�Ѥξ夲���ϰ��600�ߤ�Ķ������â�����ƹ���������Ǥ�ͽ���̤�����夲�������������Ȥ��������ƹΰ������ʡʸ�������ú���ղ�ŷ�����������ȵ����ʤɡˤ��Ф��ƴ��Ǥ�����夲���ȯɽ�������ޤ�����������ػ�ˡ�����ʤ����ɤ������ꥰ���륰���Ф���Ĵ���Ⳬ�Ϥ����ȯɽ���������η�̡�������Ω�㲽���ǰ��������ʿ�Ѥξ夲���ϵ�®�˽̾�������¾����Ĺ���������徺��Ĵ�ˤ��뤿�ᡢ��ɩUFJ�����ն�ԡ��դ�����FG�ʤɶ�Գ������Ū��Ĵ��ư�����ä���
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ��������籢�����Ф����������籢���Ȥʤä��������ͤǤ��ڤ�夬�ä������Ȥ��Ƥ�Ϣ³�����Ǿ徺����Ȥ�������ʾ夲���Ȥʤä������������Ԥ����¤������Ȥ����礭�����Ȥ��������Ϻ����β��������μ�Χȿȯ�˲�ʤ����������ƹ���Хᥭ���������ʥ��δ���ȯư��30���ֱ�����줿�ˤ��������ˤ������ޤ��ޤ���ž��ž�����ǽ�������뤳�Ȥ�ޡ����åȤϽ�ʬ���Τ��Ƥ��뤫�����
33�ȼ���20�ȼ�夲�����徺Ψ�ȥå�5�ϡ���Ŵ��°��1�̡ˡ��������ʡ�2�̡ˡ��ŵ������3�̡ˡ�͢���ѵ����4�̡ˡ�����¾���ʡ�5�̡ˤȤʤä���
���������
�֥ȥ��״���ˤ�פϵ����ͤ���ʮ������ 02��04��
�轵���������ƹ�������������������DJIA -337.47 @44,544.66, NASDAQ -54.31 @19,627.44, S&P500 -30.64 @6,040.53�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�155���Ⱦ���轵����߰¥ɥ����Ǥ�ư�������������ܳ����̤ϲ���������ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������154���Ф��ơ�������������1,470�Ȥʤä���ƭ��쥷����98.56%����ڥץ饤�����������5��5629���ߡ�
TOPIX -68 @2,720
����ʿ�� -1,052�� @38,520��
�轵���������ƹ�Ǥϡ��ȥ����������Τ����ʥ���25%�ˡ��ᥭ������25%�ˡ�����10%���ɲáˤ��Ф���2��4��������Ǥ�ݤ�����ƻ�����ȡ�����դ����餽��ޤǾ夲�Ƥ�����������ȿ�������10ǯ��������������4.512%����4.544%�ؾ徺��������������Ϣˮ���������������FRB�ˤ�����ե��ɸ�Ȥ��ƽŻ뤹�륳��PCE���ʻؿ���ͽ�ۤȰ��פ�����
����2��3��������Ծ�Ǥϡ��ƹ�ι���������������кѤ�Ϳ���밭�ƶ�����ǰ���졢�ȥ西��ư�֤�Ϥ���Ȥ��뼫ư�֤��濴�����������������줿������ʿ�Ѥβ������ϰ��1,100�ߤ�Ķ���������Ǥ�ȯư�Ϥޤ���Τ��Ȥ�������������¾��Ȥθ�ĺ����ǥ֥�դ˲�ʤ��ȹ���äƤ����Ȥ����ˡ֥ȥ��״���ˤ�פϵ����ͤ���ʮ���������ʥ��ȥᥭ�������������ǤDZ���������Ǥ��롣
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ�����åץ�����ǻϤޤä��塢�籢���ǵ����10��25��60��260���Τ��٤Ƥΰ�ưʿ��������������10���ܤ����Ȥ���³���Ƥ����ݤ��礤��β��¡�@37,800���դ�ˤ˶��դ��Ƥ�����
33�ȼ���32�ȼ郎������������Ψ�ȥå�5�ϡ�͢���ѵ����1�̡ˡ���̩�����2�̡ˡ��ѥ�ס����3�̡ˡ�������4�̡ˡ���Ŵ��°��5�̡ˤȤʤä���
���������
Ĺ��������1.5~2�餤�ޤǾ夬�뤫�� 02��01��
�������ƹ��������ȿȯ������DJIA +168.61 @44,882.13, NASDAQ +49.43 @19,681.75, S&P500 +31.86 @6,071.17�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�154�����Ⱦ�Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤ϲ���������������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������606���Ф��ơ�������������976�Ȥʤä���ƭ��쥷����109.52%����ڥץ饤�����������4��6090���ߡ�
TOPIX +7 @2,789
����ʿ�� +59�� @39,572��
�ƹ�Ǥϡ��夤�кѻ�ɸ���������10ǯ������꤬���4.48%�ޤDz�������������٤������ޤ��������˷軻ȯɽ����IBM���ƥ���ȥ���ץ�åȥե����ब�徺���������������ȥ����������Τ����ʥ��ȥᥭ���������͢���ʤ��Ф���2��1������25%�δ��Ǥ�ݤ����ˤ�����ɽ�����������Τ��ᡢ�������ȳ�30��ʿ�Ѥϰ��295�ɥ��ޤǾ徺���Ƥ��������徺����̾�������168.61�ɥ��ǽ�����������ˡ��ȥ����������Τ�BRICS�ʤɤο������ƥɥ�ʳ��������̲ߤ��Ϻ������100%�δ��Ǥ�ݤ��Ȥ����������
����1��31��������Ծ�Ǥϡ��������ƹ�Ծ�Ǽ���3�����ؿ���·�äƾ夲�����Ȥ�����ơ�����ǽ��AI�˴�Ϣ���ͤ���ȾƳ�δ�Ϣ�����ΰ�Ѥ����줿���������ȥ����������Τδ��Ƕ����������Ф���ٲ�������������Ƭ���ޤ�����
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ�������������10����ưʿ������������25����ưʿ������������60����ưʿ�����ȤʤäƤ��ꡢ�Ƥӳ����������뭣����¤ʾ徺���̡ˤȤʤä���â�����⤦����Ĺ�����ּ��Ǹ���Ⱥ�ǯ10���ܤ����Ȥ����ֶ����쥯����פȤ����ݤ��礤���Υ����Ǥ�ư���Ǥ⤢�롣�������������Ф���ʤ����Ȥ���ˡ�������ξ�¤Ǥ���40,250���դ�ޤǤ�ȿȯ���뤳�ȤϽ�ʬ�ˤ������롣�����������㡼�ȡ���ǥ��������Ƥ����Τϡ��������Ǥ�ï���Τ�ʤ����礭�ʹ�������������ФƤ��ʤ��ʤ餳�Τ褦��ư���Τ����ФǤ���פȤ������ȤޤǤǤ��롣
���㡼�Ȥ����Ω�Ĥ��տ����Ƥ⤤���ʤ������㡼�ȡ���ǥ�����������ʬ�ϳ����θ�����§�ˤ�����Ū�˿������롣����Ǥ���ʤ���ʬ�����롣������ʬ�Ϸ���������������ɬ�פ����ꡢ������ʬ�ϡ��μ��פǤʤ��ֵ�ǽ�פʤΤǡ����ο�����ʬ���θ����и��ˤ��Ƽ�����ʬ��������ʤ��������ơ��ֵ�ǽ�פ�ˤ�ƹԤ��Ȥ��Ĥ��ϡַݽѡפˤʤ롣�����ַݽѤζ��ϡפ��ܻؤ������ʤ��ޤ��礦��
Ĺ�������ξ徺;�ϤϤޤ����ʤꤢ�ꤽ���������������������ۤ��������ּ¼������������ʥޥ��ʥ��Ƕˤ���㤤���ס֡ʷʵ���Ǯ������䤷�⤷�ʤ�����Ω�����ˤϤޤ�����ε�Υ������פȽҤ٤����ᡢ�ޡ����åȤ����夲ͽ�ۤϤ�����������0.5��0.75%���Ǥ��ߤ�ǤϤʤ�1%�ʾ���ڤ�夬�ä����⤷����������1��ޤǾ夬��Ȥ���С�Ĺ��������1.5~2�餤�ޤǾ夬��Ϥ��ȿȹ����Ϥ��
33�ȼ���17�ȼ郎�夲�����徺Ψ�ȥå�5�ϡ��ڷ���1�̡ˡ���Ŵ��°�ˡ�2�̡ˡ�������3�̡ˡ��ŵ������4�̡ˡ���°���ʡ�5�̡ˤȤʤä���
���������
���ڡ����Υȥåפ�
|
|