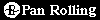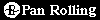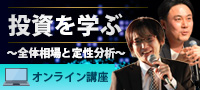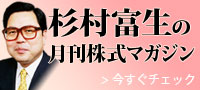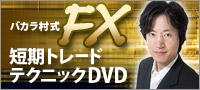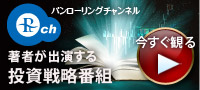|
����������Υȥ졼��������
|
���ץ��٥�Ȥ�������������꤬���ͥ���Ȥʤä� 10��31��
�������ƹ��������ȿ�����DJIA -91.51 @42,141.52, NASDQ -104.82 @18,607.93, S&P500 -19.25 @5,813.67�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�152�����Ⱦ��������߹�ɥ�¿��Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤Ͼ夲��������¿���ä����������ؿ��Ͼ夲������ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������1,136���Ф��ơ��������������458�Ȥʤä���ƭ��쥷����94.36%����ڥץ饤�����������4��9740�����ߡ�
TOPIX -8 @2,696
����ʿ�� -196�� @39,081��
�ƹ�Ǥϡ�7��9���GDP®���ͤ�ͽ�ۤ�ä�����10��ADP̱��������ѼԿ���ͽ�ۤ���붯����̤Ȥʤꡢ�����������ä���11��5�������������������Ʃ���������νŤ��Ȥʤꡢ����3�����ؿ���·�ä�ȿ������ե���ǥ�ե���ȾƳ�γ��ؿ���SOX�ˤ�3��¤Ȥʤä���11��1���ˤ�10���Ƹ������ס��轵�ˤ���������������곫ɼ����Ϣˮ�����Ծ�Ѱ����FOMC�ˤγ��Ťʤɽ��ץ��٥�Ȥ��Ƥ��ꡢ����˿��ŤˤʤäƤ���褦����
����10��31��������Ծ�Ǥϡ��ƹ�Ծ�Ǥ�ȾƳ�γ��¤�ή��������������쥯�ȥ����SCREEN�ʤ�ȾƳ�δ�Ϣ�����ΰ�Ѥ����줿������Ʊ��ȾƳ�δ�Ϣ�����Ǥ⡢���軻��ȯɽ�������ɥХ�ƥ��Ȥ�6�徺���ơ�����1��������������ʿ�Ѥ���145�߲����夲����10��23�����衢ʪ���������Ȥ���ͭ̾�ʥ��ե��å��⡦����ԥ��롦�ޥͥ����Ȥ�����������������Ȥ������Ȥʤ�������褿���˥��ߥΥ륿�Ϸ�����56%��Ȥʤä���������10��30��������ͤ��Ť��ʤäƤ������ޤ�������줬�߹�ɥ�¤˿��줿���Ȥⳤ��û���ڤˤ������ؿ���ʪ������Ͷ��������ʿ�Ѥβ������ϰ��400�ߤ�Ķ����������������ʿ�Ѥ�ľ����3�Ķ�������1,300�߾夲�Ƥ����Τǡ����׳�����꤬�Ф�Τϼ����ʤ��ȤǤ��롣31���ޤdz���������ζ�ͻ����������Ǥ����������ο����֤������ꤵ�줿���������Υޡ����åȤ�ͽ���̤���ä��Τdz����Ծ�Ǥ�ȿ���ϸ¤�줿��
���ܤ�Ĺ�������ˤϾ徺���Ϥ�����˹�ޤ�ȸ��롣�������Dz�Ⱦ�����Ȥʤä�Ϳ�ޤϺ�����ĥ�������ĥ�������ޤȤ�Ϣ�Ȥ����뤿�ᡢ��ʤ��⸻���Ĥ���ȯ���Ť����Ȥˤʤ롣ĶĹ����40ǯ�Ĥ������ϰ��2.555%��16ǯ�֤�ι���ˤޤǾ徺������10ǯ��������2019ǯ8������˾徺��Ĵ�Ǥ��롣�����Ǥ����������Ĺ��Ū����������������˰����夲�褦�Ȥ��Ƥ���Ȥ����ء�Ĺ������������ΰ������ޤ�ˤ�ꡢ�夬�ꤽ���Ǥ��롣�Ȥ������Ȥǡ�����³�������׳��礬���ԤǤ���ᥬ�Х����ݸ��������ܤ�������
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ�Ĺ�����Ҥ��������û������ȿ������ޤ������Ȥ��ƾ������25����ưʿ�����ξ�ǿ�ܤ��Ƥ���Τǡ����������ϤϷ�³���Ƥ��뤬����������꤬ͥ���Ȥʤ�Ĵ�����뤳�Ȥ����ꤷ�Ƥ����������������ȥ졼�ɤʤ龯���ǤⲼ���Ϥ�顢��ö���¤鷺¨�������ꤷ�����׳��ꤹ�٤��Ǥ��롣�����ߤޤ꤫��ȿž���Ϥ��ޤ��㤤�᤻���ɤ��������ä���
33�ȼ���21�ȼ郎�夲�����徺Ψ�ȥå�5�ϡ���°���ʡ�1�̡ˡ�������2�̡ˡ�Φ����3�̡ˡ���Ŵ��°��4�̡ˡ��۶ȡ�5�̡ˤȤʤä���
���������
��������������25����ưʿ�����ξ�˺���夷�Ƥ���Τǡ����� 10��30��
�������ƹ�������Ϲ�¤ޤ��ޤ��Ȥʤä���DJIA -154.52 @42,233.05, NASDAQ +145.56 @18,712.75, S&P500 +9.40 @5,832.92�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�153������Ⱦ��������߰¥ɥ����Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤Ͼ夲��������������䤬¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������907���Ф��ơ�������������677�Ȥʤä���ƭ��쥷����91.36%��
TOPIX +22 @2,704
����ʿ�� +374�� @39,277��
�ƹ�Ǥϡ�1���ָ������������������桢��10ǯ�������ϰ��4.33%�ޤǾ徺�������ᡢ�ʵ��Ҵ������濴�����������������줿��9��θ���ư��Ĵ����JOLTS �ˤǤ�����������ε�ͷ�����Ծ�ͽ�۰ʲ��ȤʤꡢϫƯ���뤬�ˤ�Ǥ��뤳�Ȥ��������Ȥ��顢�ʵ�����Ԥ����ߤ�ȸ������Ȥ������Ϣ������ʵ��Ҵ������ΰ�������ä������η�̡��������ȳ�30��ʿ�Ѥϲ�������¾�����ϥ��ƥ��������졢�ʥ����å���3����Ⱦ�֤�˻˾�ǹ��ͤ�������
����10��30��������Ծ�Ǥϡ��ƹ�Ծ�ǤΥϥ��ƥ������ή�������ơ�ȾƳ�δ�Ϣ�������濴������ƾ徺������������ʿ�Ѥξ夲���ϰ��500�ߤ�Ķ�������ޤ����ƹ��Ĺ�������ξ徺�������������Ȥ�ȿ�����ƹ����Ĺ�������ξ徺���㲼�������Ȥ�����٤������������10��31���ޤǶ�ͻ������������Ƥ��뤬���ޡ����åȤ����������������ο����֤���ͽ�ۤ��Ƥ��롣�������塢����������ᤷ��ȿȯ������ơ������ϥϥ��ƥ����ξ徺�����Τ������Ȥʤä���
11��5�����鸽ʪ�����μ�����֤����ߤ�15:00����15:30�ر�Ĺ�����ΤǻȤ����꤬�ɤ��ʤ롣�������˥塼�衼���ڷ�������NYSE�ˤϼ�����֤�1��22���֤˱�Ĺ�����ȯɽ���Ƥ���Τǡ��������٤�ȸ����ꤹ�뤬��
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ�����åץ��åפ��ƻϤޤä��塢����˾夲��û�����ǽ���������������������25����ưʿ�����ξ�˺���夷�Ƥ��ꡢ10��15����������@40,257�ߤ���ɸ�ͤȤ��ưռ�����롣��������������������������Ȥ���4ǯ�˰��٤��祤�٥�Ȥ��̲ᤷ�ʤ��ƤϤʤ�ʤ������γƼ�����Ĵ���Ǥϥȥ����������Τ�ͥ���Ȥ���Ƥ��뤬�������㤫��Ƚ�Ǥ���Ȥ���ۤ����Ƥˤʤ�ʤ����㤨�С�2016ǯ������������Ǥ���ɼ��ľ���ޤǤۤȤ�ɤ�����Ĵ���Ǥϥҥ������ȥ�ͥ���ȤʤäƤ��������ºݤˤϥȥ������������
33�ȼ���26�ȼ郎�夲�����徺Ψ�ȥå�5�ϡ��ŵ���������1�̡ˡ���Ŵ��°��2�̡ˡ�������3�̡ˡ���̩�����4�̡ˡ����饹�����С�5�̡ˤȤʤä���
���������
�֥��٥���̲���̤ȡ������Ѳ����̤���³�� 10��30��
�������ƹ�������Ͼ徺������DJIA +273.17 @42,387.57, NASDAQ +48.58 @18,567.19, S&P500 +15.40 @5,823.52�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�152�����Ⱦ��������߹�ɥ�¿��Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤Ͼ夲��������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������1,275���Ф��ơ�������������323�Ȥʤä���ƭ��쥷����91.06%����ڥץ饤�����������3��5920���ߡ�
TOPIX +24 @2,682
����ʿ�� +298�� @38,904��
�ƹ�Ǥϡ������10��������פ�ȯɽ���뤬����������������ؤηٲ������¤餤�Ǥ���ʥ����饨��ϥ����������ߥ����빶���Ԥä�����������Ϣ���ߤȳ˻��ߤϹ����оݳ��Ȥ��Ƽ��������ˡ������ȿ�Ǥ��Ƹ�����줬�礭�������1�Х���70�ɥ�����Τ˳�������褿���ʵ��Ҵ����Ǥ����ͻ���ξ徺����Ω�ä����������������Ԥ����ह���桢�ե�å����������ե����ʥ��ʵ�NYCB�ˤʤ��϶�ΰ�Ѥ��ֻ��軻�Ȥʤä���
����10��29��������Ծ�Ǥϡ��������Ȥ����ܤ����������괶����ޤ�ȸ�����ʪ��������Ǥ����������ץ��٥�Ȥ��̲ᤷ�����Ȥ����᤹ư����������³�����������³���������Ƥ�Ĺ���������徺���Ƥ��뤳�Ȥ��顢��������硦���׳������Ԥ��ƻ�ɩUFJFG�仰�潻ͧFG�ʤɥᥬ�Х��������̿HD���������ʤɤ��ݸ�������Ω�ä����줿�������������ɱ��϶����Ȥ������ˤۤ��ƾ徺���Ƥ�����ɩ�Ź��ʤɽŹ������ɱ����Ǥβ�ǽ���������ä����ȤǤ��ΤȤ��������ͥ�����ä����������Ͼ徺��ž������
���ɤ��Ѳ�������ξ徺��¥������Ϳ�ޡʼ�̱�ޡ������ޡˤϽ����������Ԥ��Ʋ�Ⱦ�����Ȥʤä����ᡢ���̹��Ǥμ����̾����˾��Ĥ���ˤ⡢��̱̱���ޤΤʤ����ޤΰ����Ȥ�Ϣ�Ȥ��Ϻ����뤷������Ū����ˡ���ʤ�����̱̱���ޤζ�����ɽ�ϡ��������Ȥ��ɤ���Τˤ϶��Ϥ������ܤʤ�Τˤ����ܤ��ȸ����פȽҤ١��Ʒ老�Ȥ�Ϳ���ޤ����Ϥ�����ʬϢ��β�ǽ���˸��ڤ���������ν������ǵ��ʿ���4�ܤ����䤷����̱̱���ޤ��Ǥ��������ϸ��Ǥ�Ҳ��ݸ����ηڸ��ˤ���̱�μ���ۤ����䤹���ȤǤ��롣Ϳ�ޤ���̱̱���ޤζ��Ϥ����褦�Ȥ���ʤ�С���ġ���ǯ�Ƥλ������Ǿ������褦�Ȥ���ʤ�С����������˶�Ť������ʤ�������������ϳ����װ��Ȥʤ롣����ˡ�Ϳ�ޤ���Ⱦ���������Ǥ��뺣����ͻ�������Ƕ����Τ褦�ʳ�������դʤǤ���褦�������Ԥ��뤳�Ȥ����ʤä��������������˥ץ饹�װ��Ȥ���Ư����
��Ĺ�����������ޤߤ����ˤĤ��ơ�11��5�����ƹ�����������Ǥ��緿���Ǥ��Ĺ���뤳�Ȥ�Ǥ��Ƥ��붦���ޤΥȥ����������Τ������������Ȥ�����ƻ���������褿�������������Ĺ���������徺���Ƥ��롣�緿���Ǥ��ºݤ˼»ܤ����С�����ե줬�Ʋ�®����Ϣˮ���ܤκ����ֻ������礹�뤳�Ȥˤ�ꤽ������᤹�뤿����ƹ�Ĥ���ȯ����롣���η�̡�Ĺ�������ˤϾ徺���Ϥ������롣���Τ褦�ʥ����å�������10ǯ�������ϰ��4.30%�ޤǾ徺��������Ĺ����������ߤޤꤹ��С�����ϱ߰¥ɥ���¥���ϤȤʤ롣����϶�ԡ��ݸ����ȼ�ư�֤ʤɤ�͢�д�Ϣ���ˤ��ɤ����Ȥʤ뤬�����ܥ����Ȥξ徺���̤��ơ�����˴��Ԥ������¿���Υ���å���ե������⤤����������Ū�����ȤʤäƤ���ϥ��ƥ���Ĺ�������������������뤳�Ȥˤʤ�Τǡ�ȾƳ�δ�Ϣ�����ˤϲ������ϤȤʤ롣
10��30~31���ˤ�����ζ�ͻ���������礬���Ť���롣8��μ¼��¶⤬��ǯƱ����0.8%���Ȥʤä��������֤�ȡ��¼��¶⤬��25ǯ�֤ܾۤ夬�餺���Ѥ��ʤ�������Ǥϡ��¶��ʪ���ι��۴ġפ��ܻؤ�����Ȥ��Ƥ��ɲ����夲�褦�Ȥ���Ķ���������������ϫƯ���������¶�徺�ˤĤ��ơ��к������Ǥϡ�ϫƯ�������ʸ��Ѽ��������μ¼��ղò��͡��Ĥޤꡢ��Ȥμ¼������סˤ��⤯�ʤ��ϫƯ�Ԥ˻�ʧ�����¶��⤯�ʤ�Ȥ���Ƥ��롣�����������٤Ƥι�����ƤϤޤ�櫓�ǤϤʤ������Ǥ��롣BNP�ѥ�оڷ��β���ζ��Ϻ���Ĵ���ˤ��С�1998��2023ǯ�δ��֤Ǹ���ȡ����ܤλ�����������������3�䶯�徺�����ˤ⤫����餺��Ʊ�����֤μ¼��¶�ϲ��Ф����ä����Ȥ�������Ʊ���֤��ƹ����������5�䶯�徺�����¼��¶��3������ä��������ܤǤϡ����ȡʡ��ͻ��������ܶ�10���߰ʾ�δ�ȡˤ�ϫƯʬ��Ψ��2023ǯ�٤�48.2%��54ǯ�֤���㤵�Ȥʤä������դ˸������¾夲��;�Ϥ��⤤�ȸ����롣¾�����澮��ȡʡ���ܶ�1����̤���δ�ȡˤ�ϫƯʬ��Ψ��80%����ǹ�ߤޤꤷ�Ƥ��ꡢ����ʾ���¶��ʧ���ΤϺ���Ǥ��롣��ǯ�Ǥ����Ȥ��Ѳ����ĤĤ��뤬�����ܴ�Ȥ��¶��Ĺ���֤�ǯ���������ˤˤ��ǯ������β������ܤ�������������ʧ���Ȥ���ȯ�ۤ�����ˤ��ꡢ��ġ���Ȥ���ȯŪ�ʤ��Ȥ����äƤ��ݻ����ˤ����褦������α�ݤ���뤳�Ȥ��ɤ����ȤǤ���Ȥ���ȯ�ۤ⺬�������������äơ�Ʊ�����Ҥ�ʿ�ѼҰ���3�ܤ����夲��ã�����Ƥ��Ƥ⡢��館�������3��¿���ʤ�Ȥ������ȤϤʤ������Ƥδ�ȤǤ��¤ߤμҰ���3�ܲԤ��С��¤ߤ���3�ܤ���ԤǤ���ΤȤ��о�Ū�Ǥ��롣
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ�������³�����Ʋ�������10����ưʿ�������������25����ưʿ�����ξ�˺���夷����������������Ⱥ������ޤǤϷ�Ĵ������ư���Ǥ��롣��������������������η�̼���ǡ����ʤ��Ȥ�û��Ū�˳����Ծ줬���𤹤��ǽ����ǰƬ���֤��Ƥ����������ä˥ϥꥹ��Ϻ��Ǿ����������ϡ��餱��ǧ��ʤ��ȥ����������Τ��ٻ��Ԥ�ޤ����뤳�ȤǺ��𤬳��礹���ǽ�����⤤��
33�ȼ���30�ȼ郎�夲�����徺Ψ�ȥå�5�ϡ���ԡ�1�̡ˡ��ڷ���2�̡ˡ�����¾��ͻ��3�̡ˡ��۶ȡ�4�̡ˡ���Ŵ��°��5�̡ˤȤʤä���
���������
��������Ϳ�����Ԥ�֥��٥���̲���̤⤢������ 10��28��
�轵���������ƹ�������Ϲ�¤ޤ��ޤ��Ȥʤä���DJIA -259.96 @42,114.40, NASDAQ +103.11 @18,518.60, S&P500 -1.74 @5,808.12�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�153����Ⱦ�Ф��轵��������߰¥ɥ����Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤ϲ����ƻϤޤä����������ڤ��֤��Ϥ�Ƹ����ƾ夲��������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������1,504���Ф��ơ�������������123�Ȥʤä���ƭ��쥷����89.34%����ڥץ饤�����������3��8858���ߡ�
TOPIX +39 @2,658
����ʿ�� +692�� @38,601��
�ƹ�Ǥϡ�9�����ѵ�����ۤ�������0.8%����ͽ�ۤ�1.0%���ˤȤʤä����Ծ�ͽ�ۤ����ɤ��ä���10��ߥ���������ƾ�������ٻؿ���70.5��ͽ��69.0�ˤ��ƷкѤι�Ĵ���դ����̤Ȥʤä����ᡢ��Ĺ��������������4.215%����4.242%�ؾ����徺���������ͷٲ������ޤäƤ��뤿�ᡢ��������갵�Ϥ���ޤäƤ�����
����10��28��������Ծ�Ǥϡ��������ν������곫ɼ�Ǽ�̱�ޤ����Ԥ������Ȥ�����ơ�����դ���������ͽ�ۤɤ���˲����ƻϤޤä�����̱�ޡ�������פβ�Ⱦ������2009ǯ����15ǯ�֤�Ȥʤä�����ǯ8���ܤΤ褦������ʿ�Ѥ�1000���餤�ε�����äƤ��ԻĤǤϤʤ��ȥޡ����åȤϿȹ����Ƥ�������������Ϳ�ޤ���Ⱦ�����Ȥʤ뤳�Ȥϳ�ɼ���ޤǤ���ƻ�Ǵ���ͽ�ۤ���Ƥ������Ȥ⤢�ꡢǫ���֥��٥���̲�פˤ�곥��ȴ���������ᤷ��ͥ���Ȥʤä����������ʪ�Ƕ�����ųݤ��Ƥ����إå��ե���ɤ����׳���Τ�������ᤷ��ž�����ȸ����롣
��Ĺ�������ξ徺��Ϳ�ޤ����Ԥ������Ȥ���θ����������ɲ����夲���ˤ����ʤ�������Ȥδ�¬�ˤ��߰¥ɥ����Ǥ�ư������ȾƳ�δ�Ϣ�������徺�����ʥե���ǥ�ե���ȾƳ�γ��ؿ��ξ徺�ˤ��Ȥ����ܳ����㤤��٤��������η�̡�����ʿ�Ѥξ夲���ϰ��800�ߤ�Ķ�������߰¥ɥ���ư����ȿ�����ơ��ȥ西��ư�֤�ۥ���ʤɤμ�ư�ֳ��Ͼ夲��������˥ȥ�HD��˥��쥤�ʤ�͢����Ϣ�����ϲ�������
�ޤ�����̱�ޡ������ޤϺ�����ĥŪ�ʹ�̱̱���ޡʸ��ǤȼҲ��ݸ����ηڸ��ʤɡˤȤ�ϢΩ���Ȥ�ΤǤϤʤ����������Ǥ���夷�ơ�����ˤ��ʵ����ȸ��̤���Ԥ������㤤��Ͷ�ä��Ȥ��������⤢�롣��̱̱���ޤϸ������϶Ϥ�7���ʤ��ä����������Ƥߤ��4�ܤ�28���ʤ˵���������̱�ޡ�191�ˡ������ޡ�24�ˡ���̱̱���ޡ�28�ˤ�ϢΩ������Ϣ�礹���243���ʤȤʤ�233���ʤ�Ķ�����Ⱦ����롣����ˡ������������Ԥˤ������������Ȥʤä������ɱ������ۤκ⸻�Ȥʤ빱�����Ǥ����ʤꡢ��ǯ�Ƥλ�������ޤ������ꤵ���Ȥδ�¬�����γ��㤤��٤��롣��������̱̱���ޤζ�����ɽ�ϼ�̱�ޤȤ�ϢΩ�β�ǽ�������ꤷ�Ƥ��롣����Ǥ��������Ȥ������Ƕ��Ϥ��뤳�ȤϤ�������Ȥ���äƤ��롣�Ȥ������Ȥϡ��������Ĥ�����ˤʤ뤳�Ȥ��̣������Ĺ��Ū�ʳ����ˤϥޥ��ʥ��ˤʤ롣
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ��轵�������ν��ͤ������ǻϤޤä������������ڤ��֤��ƾ徺���Ϥᡢ��ɡ�Ķ�������ǽ��������嵭�˽��͡����װ����������ä���̡�Ϳ�����ԤȤ����礭�ʳ��º����������ऱ�ơ�Ĺ�������Ǥ�ȿȯ�Ȥʤä�����������礭�ʳ��º�������ۤ�������ˤϡ����ʤ��Ȥ���ʬ�δ֤��轵�������Υ���а���@37,713�ߤ�����ळ�ȤϤʤ��������������ơ�11��5�������������������ȡ����ץ��٥���̲�ˤ��������ϰ��경����ȸ��롣������ϴ�ȶ��Ӹ��̤������������
33�ȼ���29�ȼ郎�夲�����徺Ψ�ȥå�5�ϡ�͢���ѵ����1�̡ˡ������ʡ�2�̡ˡ�������3�̡ˡ��ڷ���4�̡ˡ��ŵ������5�̡ˤȤʤä���
���������
�������ɤ���Ԥ���Ʃ�������⤤���ᡦ���� 10��26��
�������ƹ�������Ϲ�¤ޤ��ޤ��Ȥʤä���DJIA -140.59 @42,374.36, NASDAQ +138.83 @18,415.49, S&P500 +12.44 @5,809.86�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�151�����Ⱦ��������߹�ɥ�¿��Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤ϲ�����������¿���ä��� ��ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������216���Ф��ơ�������������1,398�Ȥʤä���ƭ��쥷����88.00%����ڥץ饤�����������3��1579���ߡ�
TOPIX -17 @2,618
����ʿ�� -229�� @37,914��
�ƹ�Ǥϡ�ͽ�۰ʾ�ι��軻�ȶ��Ӹ��̤���ȯɽ�����ƥ��餬22%��Ȥʤꡢ�ʥ����å���S&P500�ξ徺���������¾�����軻��̤������ä�IBM�ȥϥͥ����롦�����ʥ���ʥ�������¤Ȥʤꡢ�������¾夲�����ϫƯ�ԤΥ��ȥ饤����Ĺ�����Ƥ���ܡ�����ʻ���������3���������ǥ������ȳ�30��ʿ�Ѥ���180�ɥ벡�������������������ݸ����������10��S&P500�������Х���¤�ȡ������ӥ���PMI®���ͤ�������̤Ȥʤä�������10ǯ�������Ͽ�������Ԥ��ƾ夲�Ƥ������Ȥ⤢�ꡢ������4.242%����4.215%���㲼�������������������������Ĵ���Ǥ�ξ����λٻ�Ψ���ɹ����Ƥ��ꡢ�����̤����ꤹ��ޤǤ��̾�����֤������뤫�⤷��ʤ�������ʬ��������������ˤʤ롣
����10��25��������Ծ�Ǥϡ����줫�����ͥ���ǿ�ܤ����������ϰ��430�ߤ�Ķ���������ٻԾ�DZ߹�ɥ�������˿��줿���Ȥ䡢��̱��������ξ��פ���Ⱦ����줹��Ȥδ�¬���齰��������ɼ��ɼ��̤����ˤʤä��㤤���פϰ��ù������
���ܤ���Ƥ�����������㤤�פȤ��ˡ����������ϳ���ˤʤ�פȤ���Ⱦ������ͭ�����ä����ʥޥ�����줿�����ɤ���Ԥ���Ʃ�������顢����������ʿ�ѽ���@37,913�ߤϽ�������10��9������������3��¤Ȥʤä���1963ǯ�ʹߡ������2021ǯ�ޤ�19��Ϣ³������ʿ�Ѥϲ���������������ɼ��ľ���αĶ����ޤǤϾ徺������1976ǯ��Ǥ����λ�Ͻ����ˤ�������ϲ�������
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ�Ϣ³�����ε�Ͽ�ϡ��������������Ф�11Ϣ³�����ǻߤޤä������������夤����Ĵ���Ѥ�äƤ��餺�������Ϥޤ���������1990ǯ�ʹߤDZ�����Ϣ³��Ĺ��Ͽ��2012ǯ4��25����5��16����13Ϣ³�������ä������κ��ϲ�����̳�¤�1�ɥ��100�ߤ�Ķ����Ķ�߹�ɥ�´�Ĵ���طʤˤ��ä���2���ܤκ�Ĺ��Ͽ��2008ǯ9��26����10��10����11Ϣ³�����ʺ���ε�Ͽ��2�̥����ˤǡ������طʤˤϥ�ޥ�å����������ͻ����������Ū�ʷʵ����������ä��������11Ϣ³�������طʤϽ�������Ϳ�ޤ���Ⱦ�����Ȥʤꤽ���Ǥ���Ȥ������ܤ����ɤ���Ʃ������������������Ƕ����ޤΥȥ����̱���ޤΥϥꥹ�����ȤʤäƤ��ꡢ����������ɤ���Ʃ�������������ȤǤ��롣
33�ȼ��椹�٤Ƥζȼ郎������������Ψ�ȥå�5�ϡ�������1�̡ˡ��������ʡ�2�̡ˡ���������ú��3�̡ˡ��Ҹˡ���͢��4�̡ˡ������ӥ���5�̡ˤȤʤä���
���������
����ʿ�ѡ��ֽв����פǰ�ö�����ߤޤä��������� 10��25��
�������ƹ�������������������DJIA -409.94 @42,514.95, NASDAQ -296.48 @18,276.85, S&P500 -53.78 @5,797.42�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�152������Ⱦ�Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤ϲ���������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������596���Ф��ơ�������������980�Ȥʤä���ƭ��쥷����97.09%����ڥץ饤�����������3��7099���ߡ�
TOPIX -1 @2,636
����ʿ�� +38�� @38,143��
�ƹ�Ǥϡ��ɲ����������Ԥ����ष��������������ǥȥ����������Τ����Ƥк������������˿ʤ�Ȥη�ǰ������10ǯ������꤬���4.26%�ޤǾ徺������FRB��4ǯȾ�֤����������Ƨ���ڤä�9��18���ˤ�3.7%������ä��ˡ��ä˷ٲ�����Ƥ���Τ����������Ρ��屡�������Τ��٤Ƥ����ޤ�����֥ȥ�ץ롦��åɡפǤ��롣���ξ�硢�ȥ���θ����̤�����ܻٽФ�³����ȸ�����10ǯ�֤�7.5���ɥ���ֻ��װ��Ȥʤ�ȸ��Ѥ���Ƥ��롣������Ф��ƥϥꥹ��������Ǥ�3.5���ɥ���ֻ��װ��Ȥʤ롣������ˤ����礭�ʺ����ֻ�����줺�����Τ����ֻ������뤿��˹����ȯ����줺��Ĺ�������ˤϾ徺���Ϥ��ä�ꡢ����������������������������ơ�����3�����ؿ���·�ä��礭�������������̥ӥǥ�����3��������ե���ǥ�ե���ȾƳ�γ��ؿ���SOX�ˤ�1.14%�¤Ȥʤ�2��³�����
����10��24��������Ծ�Ǥϡ��ƹ���¤�ή�������ơ�����ʿ�Ѥ������Ԥǰ¤�����դ����������θ塢û���굡�ڤˤ�뼫Χȿȯ��������ʪ���㤤�ᤷ�������ơ�����9��Ⱦ��������ڤ��֤��������ξ�����ǰ�����������ʿ�Ѥξ夲���ϰ��200�ߤ�Ķ���������������������ˤϽ��������Ƥ��뤳�Ȥȡ���Ĺ���������夲�Ƥ��뤳�Ȥ��顢�����ɤ��ˤϿ��Ť��ä���
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ�����åץ����ƻϤޤä��塢�֤�ʤ��ڤ��֤��Ϥ�������Ǿ�����Ȥʤäƽ��������Ҥ�����ʬ��̵�뤷�Ƹ���ȡ������α����ν��ͤ��Ф��������������ν��ͤ��ۤ�Ʊ���ͤȤʤ�ֽв����פȤʤꡢ���������������ߤޤä����Ȥ�ż����Ƥ��롣�������ޤ����������������������礭����Ʃ���װ��Ȥ��ƻĤäƤ��뤿�ᡢ���Τޤ�ȿȯ����ľ�˷�³���뤳�ȤϤʤ��ȸ��롣
33�ȼ���23�ȼ郎������������Ψ�ȥå�5�ϡ��ŵ���������1�̡ˡ��������ʡ�2�̡ˡ�������3�̡ˡ�Ŵ�ݡ�4�̡ˡ�͢���ѵ����5�̡ˤȤʤä���
���������
�������������������η�̼���Ǥ���Ӥ�ˤʤ뤳�Ȥ⡦���� 10��24��
�������ƹ�������Ϲ�¤ޤ��ޤ��Ȥʤä���DJIA -6.71 @42,924.89, NASDAQ +33.12 @18,573.13, S&P500 -2.78 @5,851.20�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�152������Ⱦ��������߰¥ɥ����Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤ϲ�����������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������260���Ф��ơ�������������1,351�Ȥʤä���ƭ��쥷����100.62%����ڥץ饤�����������3��5155���ߡ�
TOPIX -15 @2,637
����ʿ�� -307�� @38,105��
�ƹ�Ǥϡ��ƷкѤΥ��եȥ��ǥ����Ԥ���ޤꡢ���������������ͽ�ۤ���ڡ������٤��ʤꤽ�����Ȥδ�¬����ή�ȤʤäƤ����������������������Ǻ�����ĥ�����ȡֽ����Ǥ��ˤ���פȸ���ȥ����������Τ��������������Ȥ���ǧ�������ޤä������Τ褦�ʤ��Ȥ��طʤ���10ǯ������꤬���4.22%����3����֤�ι��ͤؾ徺���Ƴ������νŤ��Ȥʤä����������ȳ�30��ʿ�Ѥϰ��200�ɥ벼������̤����ä��������ͤǤ��ƷкѤ���������طʤ˲�������̾�������
����10��23��������Ծ�Ǥϡ���Ĺ�������ξ徺��10��27���ν�������ɼ��̤�ٲ���������ʿ�Ѥ�³�������ʿ�Ѥβ����������400�ߤ�Ķ������¾�������ش����٤����ܤ����ʬ����פ����Ǥ⤢�ä�����Ĺ�������ξ徺�ϳ��ٻԾ�DZ߰¥ɥ���ʹԤ����������1�ɥ��153����ˤʤä��������ȿ�����ƥȥ西��ư�֤ʤɼ�ư�ֳ����濴��͢�д�Ϣ�����줿���о�Ū��͢����¸�٤��⤤�˥ȥ�HD�ϲ���������������ڥץ饤��������ȥ���������줷������������1,200�ߤ��Ф���1,630�ߤǽ��ͤ��դ����������1,739�ߤȤʤä����������ۤ�1���ߤ�Ķ������
����̲ߴ���IMF�ˤ�10��22���˸�ɽ�����кѸ��̤��Ǥϡ��ƹ�ηк���ĹΨ��2024ǯ��2025ǯ�Ȥ�˾������������������ܤ�2024ǯ�ٷк���ĹΨ�ϲ����������줿���������Ȥ����ܳ��λ�����餹��ǽ�����⤯�ʤäƤ�����
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ�11��Ϣ³�DZ����Ȥʤä�������Ϣ³������Ͽ��2012ǯ4��25����5��16����13��Ϣ³�����˰���ε�ϿŪĹ���Ǥ��롣������³��³��ƾ������25����ưʿ�������ͥ١����Ǵ����˳���������ۤܲ�������60����ưʿ������37,600����������äƤ��ꡢ���줬����β��ͻٻ����ȸ��Ƥ��롣���������������������������η�̼���Ǥ���Ӥ�ˤʤ뤳�Ȥ����ꤷ�Ƥ���ɬ�פ����롣�⤷���ޤ�˽��뤳�Ȥ�����С������������ˤȤäƤ��������ݥ���������äƤ��ʤ��ͤˤȤäƤ��礭�ʥ���Ȥʤ롣
33�ȼ���29�ȼ郎������������Ψ�ȥå�5�ϡ������ӥ���1�̡ˡ�������2�̡ˡ���ԡ�3�̡ˡ�������4�̡ˡ�������5�̡ˤȤʤä���
���������
������ˤ��Ƶ��˽й�����Τϸ����ǤϤʤ� 10��23��
�������ƹ�������Ϲ�¤ޤ��ޤ���DJIA +344.43 @42,931.60, NASDAQ +50.45 @18,540.01, S&P500 -10.69 @5,853.98�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�150�����Ⱦ��������߰¥ɥ����Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤ϲ�����������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������135���Ф��ơ�������������1,493�Ȥʤä���ƭ��쥷����101.71%����ڥץ饤�����������3��8079���ߡ�
TOPIX -28 @2,651
����ʿ�� -543�� @38,412��
�ƹ�Ǥϡ��Ʒʵ�����Ĵ�ʤ����������ڡ����������Ȥθ��̤��˲ä��ơ�������������ǥȥ����������Τ������������ˤϺ���������˰�������Ȥθ�Ω�Ƥ�����10ǯ������꤬�轵����4.075%����4.195%�ؾ徺���������η�̡��������ϴ���6��Ϣ³�Ǿ徺��³���Ƥ������Ȥ⤢�ꡢ��������������������꤬ͥ���Ȥʤꡢ�������ȳ�30��ʿ�Ѥϲ������¾�������̥ӥǥ�����Ϥ���Ȥ���ϥ��ƥ��������줿��
����10��22��������Ծ�Ǥϡ����ƤȤ���礭��������Ƥ��뤿����������Ԥ���Ʃ�������鳤�����Ȥ���ʪ�����ųݤ������ᡢ����ʿ�Ѥβ������ϰ��700�ߤ�Ķ���������Ǥ����ƤȤ��Ĺ���������徺��Ĵ�ˤ��롣�ޤ�ȾƳ�Τ��äƤ��ƹ�����͢�е���������ˡ�Ƥο��Ĥ��ǽ��ʳ��ˤ��ꡢ���ɽ����뤳�Ȥؤηٲ����⤢�ꡢ������쥯�ȥ���䥢�ɥХ�ƥ��Ȥʤ�ȾƳ�δ�Ϣ��������������Ƽ�����Ĵ���ˤ��н�������Ϳ�ޤ϶��路�Ƥ����Ⱦ����������ǽ������ޤäƤ��롣1�ɥ��151����ޤDZ߰¥ɥ�⤬�ʤ������͢�д�Ϣ�������ư���ϸ���Ū���ä��������徺�˼夤��ư�����������줿����������Ը������������ȤʤäƤ��볤�����ϵչԹ�Ȥʤä���
����ķ��Ծ�Ǥ�Ĺû�ζ��������̾����ƥ�����ɥ����֤Υե�åȲ����ʤ�Ǥ������������ˤ��ƻߤޤä����Ȥ�����ˤʤäƤ��롣���������κ�����ư�����ۤ��ơ������徺��ͽ�ۤ���ĶĹ���Ĥ��㤦ư�����ߤޤä��ʶ������徺����Ⱥķ����ʤϲ����➡�ޤ�»�������뤳�Ȥˤʤ�ˤ������9������ǿ��Ѷ�ˤ�ĶĹ����Ĥ�5728�����㤤�ۤ��Ƥ��������Ѷ�ˤϤ���ñ��Ĺ����Ĥ��㤦�ΤǤϤʤ�����������åסʤ��ξ�硢���������ʧ������ư�����������ˤ���Ѥ��ơ֥����åȡ�����åספˤ��Ƥ����Ȥο�¬���ޡ����åȤǽФƤ��뤬�����ʤ�������ƤϤ��ʤ����������伫�Ȥ⤫�Ĥƥ����åȡ�����åפ����ˡ�ͤ���äƤ�������褯ʬ���롣���Υ����åȥ���åפν���夬��ϡ����Ѷ�ˤ��鸫��ȡ�ĶĹ����Ĥ���©������ꡢƱ���֤θ��������ʧ������ư�����������פȤʤ롣��ĶĹ����������䥹��åפ���ư������ʧ���פ�³���¤ꡢ����å�������ꤷ���ִ֤ˤ�����ʬ�������ޤǼ������Ķ�ʥץ饹���ˤ���ݤǤ��롣��������������ư����(L)�ˤʤ뤬������������徺�����ǽ�����⤤�Τǡ���عԤ��ۤɼ��������©�����ä��ƹԤ�����ɡ����Ѷ�ˤα��������ϡ�L�ܦ��ˤȤ�����ư�������Ѵ�����롣ñ��˻Ծ����ư�����DZ��Ѥ������֦��פ����⤤��������ݤ������Ȥˤʤ롣
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ�Ĺ�籢��������Ʋ��������Ͼ������25����ưʿ�����β������߹��������������ͤǤ�25����ưʿ�����ˤ��礦���ܤ���Ȥ����ǻߤޤä���������10��Ϣ³�����Ȥʤä���25����ưʿ�������ޤ�������ʤΤǰ��ߤ�˾�ߤϻĤäƤ��뤬���徺��Ĵ���������ˤϤ��ʤ���֤��ݤ��ꤽ���Ǥ��롣�Ȥˤ������ܤν��������ƹ��������������̲᤹��ޤǤ��������줬³���ȸ��롣�����ޤǤ������ɤߤǤ��ꡢ�����ǽ�����ñ�ʤ�ɾ���ȤǤ��롣�桹�����ȤˤȤäƤ������ɤߤ��⡢�֤����顢�ɤ����뤫�פ������ڤ��˽��פǤ��롣����ˡ����Ω�Ǥ��Ƥ���ͤϺ�����ư�������Ĥʤ����㤤�ݥ������ˡʼ�ưŪ�ˡ˳��Ƥ��뤫����ö���㤤�̤����������Ȼפ����������߲���ݥ���������äƤ��ʤ��ͤϡ����ϴ����Ʋ��⤻���ŴѤ��Ƥ����Τ��ɤ��������������̤��䤫���ޤä���ƶ������äƤ������ʤȤ��˴����Ƶ��˽й�����Τϸ����ǤϤʤ���
33�ȼ���31�ȼ郎������������Ψ�ȥå�5�ϡ�������1�̡ˡ����ߡ�2�̡ˡ���ư����3�̡ˡ��ڷ���4�ˡ���ԡ�5�̡ˤȤʤä���
���������
����ʿ�ѡ�9��Ϣ³������2012ǯ5�����Ϥ���ơ� 10��21��
�轵���������ƹ�������Ͼ���³��������DJIA +36.86 @43,275.91, NASDAQ +115.94 @18,489.55, S&P500 +23.20 @5,864.67�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�149������Ⱦ���轵����߹���Ǥ�ư���Ȥʤä������������ܳ����̤Ϲ�¤ޤ��ޤ��Ȥʤä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������698���Ф��ơ�������������888�Ȥʤä���ƭ��쥷����117.24%����ڥץ饤�����������3��4127���ߡ�
TOPIX -9 @2,680
����ʿ�� -27�� @38,955��
�ƹ�Ǥϡ�2024ǯ7��9������������軻��ȯɽ�����ͥåȥե�å�����11%��Ȥʤ��ƹ��������������������ȳ�30��ʿ�Ѥ�S&P500��6��³�����ƻ˾�ǹ��ͤ�������9����幩�����135.4����ʡ�ͽ��135����ˡ�9����ߵ��ķ����142.8����ʡ�ͽ��146����ˤȤʤ궯�夬�������ä���10ǯ�������ʡ�Ĺ�������ˤ�������4.096%����4.084%���㲼������FRB��ǯ���2��FOMC��0.25%�����������ơ�����������4.25���4.5%�˰���������Ȥ������������ߤΥޡ����åȤμ�ή�θ����Ǥ��뤬���������ͽ�ۤ�����
����10��21��������Ծ�Ǥϡ�����������˳����������ʿ�ѤϾ����¤ǽ����������ܳ��������ȼ�����9��Ϣ³������̱�������IJ�ɧ��������2012ǯ5�����Ϥ���ơˤȤʤä����Ȥ˸���Ƥ��롣�⤯����դ��Ƥ⡢����˾夬�뤳�Ȥ˼��������Ƥ�����꤬ͥ���Ȥʤ걢���ǽ����ѥ�����9��Ϣ³�ǵ��äƤ��롣
��������������ɼ���Ԥ���Ϳ�ޤǤ��뼫̱�ޡ������ޤ���Ⱦ�����Ȥʤ�Ȥη�ǰ���顢��ɩ�Ź���Ϥ���Ȥ������Ź���IHI�ʤ����������Ȥ����Ź�������������¤Ȥʤä�����ȯ�Ʋ�Ư�λ��Ǥ��Ѥ��Ƥ���������ϡ��������ϤⲼ���������ı��������465���ʤǡ������м���ϼ���ξ�ޤDz�Ⱦ������ݤ���������ݻ��Ǥ���233���ʤ��ܻؤ��Ƥ��롣����������ʬ�ۤϡ���̱�ޤ�247���ʡ������ޤ�32���ʤǡ�����ʻ����279���ʤ��ä���ī����ʹ������Ĵ���Ǥϡ�Ϳ�ޤ���Ⱦ����ݻ��Ǥ��뤫�ɤ�����̯�ʾ��֤Ǥ��롣
���Ƿ�Ĵ���ä��ݸ������Գ���ȿ������������ʥ����å�����Ĵ��ư���Ƥ��뤿�ᡢ������쥯�ȥ���䥢�ɥХ�ƥ��ȡ��ǥ������ʤ�ȾƳ�δ�Ϣ���������줿������̱��Ԥ�10��21���ˡ��¼�Ū�����������Ǥ����ͥ���߽ж����ʥ�����ץ饤��졼�ȡ�LPR�ˤ�1ǯʪ������������ܰ¤Ȥ����LPR5ǯʪ��0.25%��������������������ͽ�ۤ��줿�̤���ä����ᡢ�����ŵ���ե��ʥå��ʤɤ�����Ϣ����������뤳�ȤϤʤ��ä���
������礭��ư���ϡ��ޤ��Ϻ����������ν��ı��İ�����������11���������������η�̼�����������������礭�ʥ��٥�Ȥ�䤬�ƾò�������ϡ����ƶ��������Ѳ�������Ʊ���줬ư��������ư����ȿ���������ܳ����Τ�ư������
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ��������10����ưʿ�����β������߹���Ǻ�����3���ܤȤʤä���������2012ǯ5������9��Ϣ³�����Ǥ��롣9��2����������@39,080�ߤ��ͤ����Τ˳��������꤬��®�������ʥ��㡼�Ȥη��Ǥ��롣���̤ϲ������ο���˷ٲ��������������ͽ¬����äƤ�������Ǥ�ư�����٤�뤿���Խ�ʬ�Ǥ��롣�����¬��������פȷ���ˡ�Ȥ�Ϣư��ɬ�ܤǤ��롣
33�ȼ���25�ȼ郎������������Ψ�ȥå�5�ϡ��ŵ���������1�̡ˡ��建�����ӡ�2�̡ˡ���ԡ�3�̡ˡ������ʡ�4�̡ˡ��ݸ���5�̡ˤȤʤä���
���������
��Գ��Ϻ������Ĵ���ä��������� 10��18��
�������ƹ��������³��������DJIA +161.35 @43,239.05, NASDAQ +6.35 @18,373.61, S&P500 -1.0 @5,841.47�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�150���������149�����Ⱦ�Ǥ�������߰¥ɥ����Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤Ϲ�¤ޤ��ޤ��Ȥʤä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������757���Ф��ơ�������������798�Ȥʤä���ƭ��쥷����110.21%����ڥץ饤�����������3��6276���ߡ�
TOPIX +1 @2,689
����ʿ�� +71�� @38,982��
�ƹ�Ǥϡ�9���������������0.4%��ͽ��+0.3%�ˤȿ������ȼԿ��������24.1�����ͽ��26����ˤ�������̤Ȥʤꡢ�ƷкѤϥ��եȥ��ǥ�����Ȥδ��Ԥ��ޤ��ޤ���ޤä���������ȿ�Ǥ��Ƽ���3������³����������������10ǯ��������������4.016%����4.092%�ؾ徺������
����10��18��������Ծ�Ǥϡ��ƹ����³������������ʿ�Ѥ�ȿȯ���ơ��夲�������200�ߤ�Ķ����������������������˲�����ƾ夲����̾���������Գ��Ϻ������Ĵ���ä��������������������Ƥ⼫���ʥꥺ��ǤϤ��롣
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ�������ǽ��ͤǤϾ���ȿȯ���������������10����ưʿ�����β������߹�����ޤޤǤ��롣�����⡢10��8������8��Ϣ³�����ȤʤäƤ��뤿�ᡢ�����ǤⰭ���������Ф���礭������������ʷ�ϵ��Ǥ��롣���ı�������ä�����ä����դ�ɬ�פǤ��롣�⤷��Ϳ�ޤ���Ⱦ�����Ȥʤä��顢����������������������ȤϤۤܳμ¤���äƤ���Ϥ������顢������������Ƥ���������
33�ȼ���22�ȼ郎������������Ψ�ȥå�5�ϡ���������ú��1�̡ˡ��ŵ���������2�̡ˡ��������ʡ�3�̡ˡ�Φ����4�̡ˡ���ư����5�̡ˤȤʤä���
���������
���ƤǶ�ͻ������Ĵ 10��18��
�������ƹ��������ȿȯ������DJIA +337.28 @43,077.70, NASDAQ +51.49 @18,367.08, S&P500 +27.21@5,842.47�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�149����Ⱦ�Ф�������߰¥ɥ����Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤ϲ�����������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������559���Ф��ơ�������������1,026�Ȥʤä���ƭ��쥷����110.51%����ڥץ饤�����������3��7538���ߡ�
TOPIX -3 @2,688
����ʿ�� -269�� @38,911��
�ƹ�Ǥϡ������Ρ�ASLM����å��פ�;�Ȥ�³����Τγ���������ΤȤ��Ƥ�ȿȯ������ȾƳ�����������ϴ����˲����ߤޤäƤ��ʤ��������̥ӥǥ����Ͼ夲��������˥�륬������졼��Ϥ���Ȥ����ͻ����2024ǯ7��9����ι��軻�����t�礭���徺������JP��륬���������ȥ�����ɥޥ��å�����2024ǯ7��9����η軻���ɹ��ʤ���10��ʹߤ϶�ͻ���ξ徺����Ω�ġ�
����10��17��������Ծ�Ǥϡ�16�����ƹ�Ծ�ǥ�����ASML�����Ǥʤ�ȾƳ����¤�������Υ��ץ饤�ɥޥƥꥢ�륺��AMAT�ˤⲼ������Ȥ��顢������³��������쥯�ȥ���䥢�ɥХ�ƥ��Ȥʤɤ�ȾƳ����¤���ִ�Ϣ�����������ʿ�Ѥ�³��������ܤ���Ƥ���ȾƳ�μ�����¤��������������ϩ��¤��TSMC�ˤ�2024ǯ7��9����軻��ȯɽ�����������פ���Ⱦ���١����Dz��ǹ�Ȥʤꡢ�Ծ�ͽ�ۤ���ä���������ʿ�Ѥϰ�֤���ȿȯ�����塢���˲����ᤵ�줿��
10��17����������ɤ����Բ��ɲä���ư���ٱ����ȯɽ�����������Ƥ����Ȥδ��Ԥ��Ϥ������峤����ؿ����ޥ��ʥ��ˤʤ�ʤɡ���Ĵ��ư�����ä����ƹ�����Ծ�Ƕ�Գ�����Ω�ä����줿ή�������ơ�����Ծ�Ǥ��Գ��Ϸ�Ĵ��ư�����ä����轵�������Τ��Υ֥����Ǥ����������Ȥ��Ƽ��夲����ɩUFJFG������ʿ�ѤˤۤȤ�ɰ���ĥ���뤳�Ȥʤ������������Ĵ�˾徺���Ƥ��롣�ޤ��������إꥹ�����礭����������뤬���ä˥���ƥʱ��¤��ˡ�����Ը������������������չԹ�Ȥʤä���
OPEC��ǤΥ������㲼�ȡ�����ꥫ�䥫�ʥ���Ϥ���Ȥ�����OPEC��������ˤ���������������㲼���Ƥ����桢����������ӥ���ǯ��ˤ⸺�����ˤ�ž������������Ƨ���ڤ�Ȥδ�¬���鸶������WTI�ˤ�70�ɥ������Ǥ��������ηʵ���®�⸶�����פ��㲼�����뤿�ᡢ�������ˤϲ������Ϥ������ʤꤽ����������������إꥹ������ޤäƤ��뤿�ᡢ��������1�Х���70��80�ɥ뤯�餤��ư���Ƥ��뤬���⤷�ǽ�Ū�������إꥹ�����㲼����ȡ���������®����1�Х���50~60�ɥ뤯�餤�ޤDz���������ư���Ǥ��롣
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ�³��ƾ������10����ưʿ�����������������������10����ưʿ�����ξ�˺���夹��о徺��Ĵ�ϰݻ�����뤬��������Ĺ�����Ȳ��礤��³�����ݤ��礤�������뤫�⤷��ʤ���
33�ȼ���20�ȼ郎������������Ψ�ȥå�5�ϡ���̩�����1�̡ˡ���Ŵ��°��2�̡ˡ����ء�3�̡ˡ�������4�̡ˡ���°���ʡ�5�̡ˤȤʤä���
���������
��ASML����å��ס�ȾƳ�γ���Ĵ���˲�ʤ� 10��17��
�������ƹ��������ȿ�����DJIA -324.80 @42,740.42, NASDAQ -187.10 @18,315.59, S&P500 -44.59 @5,815.26�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�149������Ⱦ��������߹���Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤ϲ�����������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������354���Ф��ơ�������������1,246�Ȥʤä���ƭ��쥷����110.11%����ڥץ饤�����������3��9155���ߡ�
TOPIX -33 @2,691
����ʿ�� -731�� @39,180��
�ƹ�Ծ�Ǥϡ�������ȾƳ����¤��������ASML�ۡ���ǥ��������ä�ͽ�����1����軻ȯɽ�����������η軻��̤⸫�̤���ͽ�ۤ�ä���EUVϪ�����֤μ��ײ������ߤ����Ȥ�ʬ�ä��ˡ���Ťΰ�̣��ͽ�۳��軻ȯɽ�Ȥʤꡢ�軻���̤��β��������������ASML�ۡ���ǥ�����16.2%�¤Ȥʤꡢ¾��ȾƳ�γ�������ޤ�����줿�����η�̡�����3�������礭��ȿ������ե���ǥ�ե���ȾƳ�γ��ؿ���SOX�ˤ�5.28%�¤Ȥʤä���
����10��16��������Ծ�Ǥϡ��ƹ���¡��ä˥ϥ��ƥ����¤�ή��������������쥯�ȥ����졼�����ƥå���Ϥ���Ȥ����ͤ���ȾƳ���������濴�����줿���äˡ�EUVϪ���˻��Ѥ����ե��ȥޥ����θ������֤��ݤ���졼�����ƥå���13.44%�¤��礭�����줿������ʿ�Ѥ�850�߶��������̤����ä���ASLM�δ��Գ���η軻������Ȥ��������ε���Ϥ����2���ܤȤʤ롣��ǯ4��ˤ�ASLM��2024ǯ1��3����μ����ۤε���ȯɽ���������λ��ˤ�ȾƳ�γ��ϸ��¤��礭�����줿��������ľ��ˤ�ASML����θܵҤǤ�������������ϩ��¤��TSMC�ˤ����軻��ȯɽ����ȳ�����ȿ������������ܤ�TSMC��10��17����2024ǯ7��9��軻��ȯɽ���롣�����β������ܼ��ϡ����ΤȤ������ܳ����Τ�Ĵ���ǤϤʤ���ȾƳ�γ���Ĵ���˲�ʤ��ȸ����롣
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ�����åץ����Ʋ����������������10����ưʿ�����˥��ݡ��Ȥ����褦�����ߤޤꡢ�ڤ��֤��Ϥ�Ʋ��Ҥ��������û�����ǽ�������25����ưʿ���������Τ˾�����Ǥ��ꡢ���Υ���ϰ����Ȥ��ƾ������Ȥ����롣
33�ȼ���29�ȼ郎������������Ψ�ȥå�5�ϡ���̩�����1�̡ˡ��ŵ������2�̡ˡ����ء�3�̡ˡ�������4�̡ˡ����饹�����С�5�̡ˤȤʤä���
���������
����ʿ�ѡ�����Фǰ��40,000�������� 10��16��
�������ƹ��������³��������DJIA +201.36 @43,065.22, NASDAQ +159.75 @18,502.69, S&P500 +44.82 @5,859.85�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�149�����Ⱦ��������߰¥ɥ����Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤Ͼ夲��������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������1,203���Ф��ơ�������������386�Ȥʤä���ƭ��쥷����111.01%�Ȥʤä�����ڥץ饤�����������4��4380���ߡ�
TOPIX +17 @2,724
����ʿ�� +305�� @39,911��
�ƹ�Ǥϡ�FRB��11��ڤ�12��ˤ��줾��0.25%��������������Ȥθ�������ή�ȤʤäƤ��ꡢ�ƷкѤϥ��եȥ��ǥ����롢�����ϡ֥Ρ����ǥ��פ������ꤦ��Ȥδ�¬����ޤäƤ��롣�ķ��Ծ�Ǥ�10ǯ��������2ǯ�������κ������礷�ĤĤ��ꡢ����Ϸʵ�����������Ǥ���ȶ����줿�ֵե�����ɡפϺ��Ǥϴ����˲�ä���ơ�ʿ���Ρֽ祤����ɡפȤʤä����ȤǷʵ�������Ф����¤����ष����������桢�轵ȯɽ���줿JP��륬���������ʤɤ�����Ԥ����פ�ͽ�ۤ���ä������������ܳʲ�������3��Ⱦ���γƴ�Ȥη軻ȯɽ���Ф�����Ԥ���ޤꡢ�������̤Ͼ徺������������Х����ǥ��ν����Τ���ķ��Ծ�ȳ��ٻԾ�ϵپ�Τ����������Ȥʤ���ư�����礭���ʤä���
����10��15�������ܳ����̤ϡ��Ƴ���ȱ߰¥ɥ���ư��������ƾ徺����������¿��������ʿ�Ѥξ夲���ϰ��600�ߤ�Ķ��������Фǰ��40,000���������������ƹ�Ծ�ǥ��ʥꥹ�Ȥ��������̤��������̥ӥǥ�����������ƥϥ��ƥ�����¿�����徺����ή�������ơ�������쥯�ȥ���䥢�ɥХ�ƥ��Ȥʤɤ�ȾƳ�δ�Ϣ�������夲����
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ�����åץ��åפ���³������9��27����������@39,829�ߤ��ͤǾ�ȴ����������������Ҥ��������û�����ǽ������Τǡ����ͤǤ���갵�Ϥ����礷�Ƴ�����Ƭ���ޤ��������ܳ����ϥ���ꥫ������켡���ư����³���Ƥ��롣�����������뭢�Ϸ�³��Ǥ��롣
33�ȼ���21�ȼ郎�夲�����徺Ψ�ȥå�5�ϡ���ԡ�1�̡ˡ��ݸ���2�̡ˡ��ŵ������3�̡ˡ������̿���4�̡ˡ������ӥ���5�̡ˤȤʤä���
���������
�����Ǿ夲�Ƥ���Τ�����û���徺��Ĵ���ȼ夵�������� 10��11��
�������ƹ�������Ͼ���ȿ�����DJIA -57.88 @42,454.12, NASDAQ -9.57 @18,282.05, S&P500 -11.99 @5,780.05�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�148�����Ⱦ��������߹���Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤ϲ���������������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������503���Ф��ơ�������������1,086�Ȥʤä���ƭ��쥷����106.46%����ڥץ饤�����������3��3755���ߡ�
TOPIX -6 @2,706
����ʿ�� +225�� @39,606��
�ƹ�Ǥϡ�9������ʪ���ؿ���CPI�ˤ�ͽ�ۤ���äơ���ǯ��+2.4%��ͽ��+2.3%�ˤʤ��ʤ�����ե�Ψ��������ʤ����Ȥ��������������Ԥ���व������¾�����������ȼ��ݸ����������ͽ�۰ʾ�����á�25.8�����ͽ��23.0����ˤ��Ʒʵ������ǰ�����������֤��줿���ܥ��ƥ��å������ȥ��Ϣ�����ۤ�11��FOMC�Ǥ����������������֤�����ǽ����������������ȿ�����ơ�10ǯ��������������4.067%������4.120%�ޤǾ徺���������ǽ�Ū�ˤ�4.067%�ޤ���ä��褿��
����10��10��������Ծ�Ǥϡ����軻��ȯɽ�����ե������ȥ�ƥ���Ͼ夲�������軻���Ƥ������ä����֥��������Ϥ���Ȥ�����ư����Φ���������ʤʤ���������濴�˲�����������¿���ä���
������ɤΥƥ����������ˤ������������ȿȯ���Ƥ�����������ȿȯ��©�ڤ줷���褿���ᡢ���ܳ����β��٤��Ȥʤ뤫�ɤ�����Ʃ���Ǥ��롣����9��13���ˤ���ǯǯ��ΰ����夲�����θ��¶����Ψ�ΰ������������������ΰ�������������ˡ������������Ƭ����δ��¤�ɽ�������������������кѤ����ڤϤ�����ñ�ˤϲ��Ǥ��ʤ���������Ĺ���ּ»ܤ����ְ�ͤû������פ������ε���Ȥ��ơ����ܤ�Ʊ���褦������ǯ�������¤˲����Ƥ��롣��ư�����פ��迩��������̡���ư���Х֥뤬����������������Ѽ���������������ܤϺ�̳������㤷�Ƥ��롣����ˡ����ƤȤ������Ω�Ϥ���礭���ʤ����ޥ͡������ƨ�Ƥ��롣
����ʿ�Ѥ�����ȡ����Ҥ��������û�����ǽ�������������Ȥʤä���4��Ϣ³������3��³�����Ƥ��뤬�������Ǿ夲�Ƥ���Τ�����û���徺��Ĵ���ȼ夵���롣���������㡼�Ȥη�������ȳ����������뭢��ȿȯ��ư������¤ʾ徺�����̡ˤʤΤǰ����Ϥʤ���9��27�����դ����ֹ�ԥȥ졼�ɡפǺ�ä�������@39,829�ߤ����̤���ɸ�Ǥ��롣
33�ȼ���28�ȼ郎������������Ψ�ȥå�5�ϡ���ư����1�̡ˡ�Φ����2�̡ˡ����ߡ�3�̡ˡ���°���ʡ�4�̡ˡ��ŵ���������5�̡ˤȤʤä���
���������
���줫��ФƤ����Ʒк����פ������ա� 10��10��
�������ƹ��������³��������DJIA +431.63 @42,512.00, NASDAQ +108.70 @18,291.62, S&P500 +40.91 @5,792.04�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�149������Ⱦ��������߰¥ɥ����Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤ϲ������������������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������646���Ф��ơ�������������939�Ȥʤä��� ƭ��쥷����102.04%����ڥץ饤�����������3��5288���ߡ�
TOPIX +5 @2,713
����ʿ�� +103�� @39,381��
�ƹ�Ǥϡ�9����Ϣˮ�����Ծ�Ѱ����FOMC�˵Ļ��ݤ��������졢��¿���Υ��С���0.50%����������ٻ��������Ȥ�ʬ�ä����������ξ徺��������ơ����åץ�䥢�ޥ���ʤɤξ徺����������Ƴ����Ͼ徺������������S&P500�ϻ˾�ǹ��ͤ����Ƥ��ꡢ�����Ϲ��ͷ��ˤ���Τ���������꤬�аפ�������äȤ������ä�������꤬�������뤳�Ȥ����뤿�����դ�ɬ�פ�������
����10��10��������Ծ�Ǥϡ��ƹ����ȷ�Ĵ��ϫƯ�Ծ��ȿ�Ǥ����߰¥ɥ��οʹԤ�����ơ�����͢�д�Ϣ�������濴�˾徺����������դ��塢����ʿ�Ѥξ夲���ϰ��300�ߤ�Ķ�����������θ�����˲�����Ʋ��������������ե������ȥ�ƥ���ȥ��եȥХ��롼�פ�2��������������ʿ�Ѥ���100�߲����夲�����Ĥޤꡢ����2�������徺���ʤ��ä��顢����ʿ�ѤϾ徺���ʤ��ä����Ȥ��̣������ڥץ饤�����ΤǤϡ��徺���������Ⲽ�����������������¿���ä����¾夲�����פ����ä��ɤ��դ��Ƥ��ʤ�����Ķ����פ��礭���������Ƥ��ꡢ�����㤨�ʤ���
������Хե��åȤ�Ψ����С������㡼�ϥ���������2019ǯ������緿���ġ�2,818���ߡˤ���ꤷ�����С������㡼���ݸ��������羦�ҳ�����Գ������ΤǤϤʤ����Ȥλ��Ǥ��顢SOMPO�ۡ���ǥ������������ۡ���ǥ�������ɩ����������ʪ���ʤɤ��夲�������羦�Ҥϴ�����9%��ͭ���Ƥ��ꡢ��¤�9.9%�ޤǶ�Ť��Ƥ��뤿�ᡢ¿ʬ��¾�ζȼ郎���������ȸ���졢ͭ�ϸ���Ȥ��ƻ�ɩUFJ�ե����ʥ�륰�롼�פ�̾������夷���褿�������ʹߤ�ư�������ܤǤ��롣10���ڤ�25����ưʿ�����ϲ������Ȥʤ���̤��Ƥ��ꡢ�����Ϥ��ξ�ǿ�ܤ��Ƥ��롣���ä�����������Ф��ľ������ƤƤ⤪�������ʤ������ߥǤϤ��롣
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ�������³������������3���֤����Ϥ��٤�û�������������˾夲�Ƥ��롣�����������ȼ��μ��ϤǾ夲�Ƥ���ΤǤϤʤ����ƹ�����夲�Ƥ��뤫�餽���Ϣ��⤷�Ƥ�������ʤΤǡ�����դ������⤯�ʤ뤬���θ�����ͥ���Ȥʤꡢ��ɡ������ǽ���äƤ��롣������ߤιˤ��ƹ����FRB�ˤ�����������Ԥ��٤��ȤʤäƤ��뤿�ᡢ���������Ԥ����ह��ȼ�®�����ǽ�����⤤�������ơ���������ܳ��ˤ�Ϣ�����롣���줫��ФƤ����Ʒк����פ������դ���
33�ȼ���23�ȼ郎�夲�����徺Ψ�ȥå�5�ϡ��������ʡ�1�̡ˡ��ݸ���2�̡ˡ���ԡ�3�̡ˡ������ʡ�4�̡ˡ�͢���ѵ����5�̡ˤȤʤä���
���������
�����������뭢��³�� 10��10��
�������ƹ��������ȿȯ������DJIA +123.13 @42,080.37, NASDAQ +259.01 @18,182.92, S&P500 +55.19 @5,751.23�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�148����Ⱦ�Ф�������߰¥ɥ����Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤Ϲ�¤ޤ��ޤ��Ȥʤä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������886���Ф��ơ�������������720�Ȥʤä���ƭ��쥷����108.12%����ڥץ饤�����������3��6430���ߡ�
TOPIX +8 @2,707
����ʿ�� +340�� @39,278��
�ƹ�Ǥϡ��������ʤ�����ȿ���5%��ˤ���10ǯ�������ξ徺���������ơ�������4.026%������4.05%�ޤǾ夲���������ͤǤ�4.0139%�ؾ�������������������FRB�ⴱ�Υ����顼�����ϡ�����ե찵�Ϥ�ͽ���̤�˴��¤�����ɲ���������Ԥ���ȯ�������ɲ��������ؤδ��Ԥ���ޤä���
����10��9��������Ծ�Ǥϡ��ƹ�Ծ�ǥ��̥ӥǥ�����Ϥ���Ȥ���ϥ��ƥ������徺�������Ȥȡ����ٻԾ�DZ߰¥ɥ�⤬�ʤ�����Ȥ�����ȾƳ�δ�Ϣ�����ڤ�͢�д�Ϣ�������濴�˾夲������ʿ�Ѥϰ��500��Ķ�徺������9����塢����������ϩ��¤��TSMC�ˤ�9��η���⤬��ǯ��39.6%���Ȥʤä���ȯɽ����ȡ�������쥯�ȥ����졼�����ƥ��ʤɤ�ȾƳ�δ�Ϣ���������ʹ�Ȥʤä������̥ӥǥ�����GPU�Τ褦����ü�ʤ���¤������ʣ�������Ƥ��뤿�ᡢ�ָ幩���פǻȤ����֤ν������������Ƥ��롣���ʤ˰۾郎�ʤ����ɤ�����в����˸������뤿��θ������֤��ݤ��륢�ɥХ�ƥ��Ȥ����ä������Ȥλ��Ǥ����㤤���פ����������ɥХ�ƥ��Ȥϳ���ʬ���θ��ξ������͡�7456�ߡˤ�������7669�ߡˡ��ޤ���������ɤ�12�����ɲú�����ư��ȯɽ����ΤǤϤʤ����Ȥδ��Ԥ���ޤꡢ����ϥ�ؿ���ȿȯ�������Ȥǡ������ŵ����ե��ʥå�������Ʋ�ʤɤ�����Ϣ������夲����
���ı���������塢��������������㤤�פȤ褯�����뤬���¤Ϥ���ۤ�������ʤ�����ɼ���ޤǤϾ夲�뤳�Ȥ�¿�����������˿��������ɤΤ褦�ʷк��������Ǥ��Ф�������Ǥ��θ�γ����Ͼ夲�뤳�Ȥ⤢��в����뤳�Ȥ⤢�롣������������äƤ⡢��ǯ�βƤˤϻ������������Ƥ��ꡢ���줬�����ޤǤ����˼��꤬�����ܻؤ��Ƥ�����ͻ�������Ǥʤɤ����������������ͽ�ۤ��뤬���̤����Ƥɤ��ʤ����������
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ�����åץ��åפ��ƻϤޤ�û�����ǽ��������������10����ưʿ�����β��˾������25����ưʿ���������äƤ��ꡢ�����Ϥ���餹�٤Ƥξ�ǿ�ܤ��Ƥ��롣�����������뭢��ȿȯ��ư������¤ʾ徺���ܻؤ����̡ˤǤ��ꡢ��ΨŪ�ˤϲ��������忶�줷�פ��������260����ưʿ�����������Ǥ��롣
33�ȼ���15�ȼ郎�夲�����徺Ψ�ȥå�5�ϡ���̩�����1�̡ˡ�������2�̡ˡ������ӥ���3�̡ˡ������ʡ�4�̡ˡ����ء�5�̡ˤȤʤä���
���������
��Ĺ���������Ƥ�4.0%��ؾ徺�����褿����ˡ����� 10��08��
�������ƹ��������ȿ�����DJIA -398.51 @41,954.24, NASDAQ -213.95 @17,923.90, S&P500 -55.13 @5,695.94�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�147�����Ⱦ��������߹�ɥ�¿��Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤�ȿ�������ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������241���Ф��ơ�������������1,386�Ȥʤä���ƭ��쥷����105.43%����ڥץ饤�����������3��9410���ߡ�
TOPIX -40 @2,699
����ʿ�� -395�� @38,938��
�ƹ�Ǥϡ�����������إꥹ���ι�ޤ��ȿ�Ǥ��Ƹ�������WTI�ˤ�5��³������1�Х���77�ɥ���ؾ徺���Ƥ��뤳�Ȥ˲ä���9���Ƹ������פ�ͽ�۳��˶����ä����Ȥ�ȿ��������10ǯ������꤬7��31�������4.0%��ؾ徺������������������Ƽ���3�����ؿ���·�ä�ȿ����������Ͽ������ˤ�9��FOMC�Ļ�Ͽ�ݤ��������졢�������ˤ�9������ʪ���ؿ���CPI�ˡ��������ˤ�9��������ʪ���ؿ���PPI�ˤ�ȯɽ����롣
����10��9��������Ծ�Ǥϡ���Ĺ�������ξ徺���������ȿ����ƹ������������������إꥹ���ι�ޤ������ơ�������������ȿ������������礭���徺�����ݸ����ȶ�Գ�����Ω�ä�ȿ�����Ĺ�������徺�϶�ԡ��ݸ��ˤϼ������ι��ƶ���Ϳ����Τ�������㤤�ΤϤ����������������줿��������ɤˤ���ɲú����ٽд��Ԥ������Ͼ夲�Ƥ����������δ��Ԥ�������Ȥʤ�8���Ϲ���ϥ�ؿ�������ȿ��������η�̡�����Ϣ�����Ȥ�������Ʋ������ŵ������줿��������줬�夲�Ƥ��뤿��INPEX��ENEOS�ʤ�������Ϣ���������줿��
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ�����åץ��åפ��ƻϤޤ�岼��û���Ҥ��������û�����Ȥʤä����������Ȥ��ƾ������10����ưʿ�����ξ�ˤ��롣10����ưʿ������25����ưʿ�����������Ǥ��ꡢ8��5�������Ȥ��ƹ��ͤ���ͤ��ڤ�夬�äƤ��ꡢû���٥��ȥ�Ϻ��ΤȤ����������³���Ƥ��롣
33�ȼ���30�ȼ郎�����������Ψ�ȥå�5�ϡ��ڷ���1�̡ˡ������2�̡ˡ�͢���ѵ����3�̡ˡ���ԡ�4�̡ˡ��ݸ���5�̡ˤȤʤä���
���������
�Ʒʵ��Υ��եȥ��ǥ����Ԥ��ޤ��ޤ���ޤꡦ���� 10��07��
�轵���������ƹ���������礭���徺������DJIA +341.16 @42,532.75, NASDAQ +219.38 @18,137.85, S&P500 +51.13 @5,751.07�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�148����Ⱦ�Ф�������߰¤Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤Ͼ夲��������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������1,234���Ф��ơ�������������359�Ȥʤä���ƭ��쥷����115.26%����ڥץ饤�����������4��4765���ߡ�
TOPIX +45 @2,739
����ʿ�� +697�� @39,333��
�ƹ�Ǥϡ�9��������פ�������������ѼԿ���25.4�������ʡ�ͽ��14.0�������ˤ�ͽ�ۤ��礭�����ꡢ����Ψ�������4.2%����4.1%���㲼�������Ȥ��ƷкѤΥ��եȥ��ǥ����Ԥ������ع�ޤä������η�̡�����3�����ؿ���·�äƾ徺���ƽ��������ʵ��¤��������������Ԥ����ष�����ᡢ10ǯʪ��������ϰ��3.98%��ޤǾ徺������2����֤�ι���Ȥʤä�����Ĺ�������ξ徺��ȿ�Ǥ��Ƴ��ٻԾ�Ǥϥɥ��㤤����꤬�ʤߡ������1�ɥ��149����Ȥʤä����轵�Ͼ����ʪ���ؿ���CPI�ˤȲ����ʪ���ؿ���PPI�ˤ�ȯɽ�����롣
����10��7��������Ծ�Ǥϡ���Ĵ���Ƹ������פη�̤ȳ���˲ä��ơ�����줬�ɥ��߰¤Ȥʤä�ή�������ơ���ư�֤䵡���ʤ�͢�д�Ϣ�������濴�����������줿������ʵ��ɷ�����Ǥ��Ф��Ƥ��뤿����㤤�¿��������롣�߰¥ɥ�������ɴ��Ź�ʤɥ���Х�����������������Ĺ�������ʿ�ȯ10ǯʪ��������ˤ�0.920%�ޤǾ徺�������Ȥǡ����Ѽ���������Ԥ��ƶ�Ԥ��ݸ������줿������ʿ�Ѥξ夲���ϰ��900�ߤ�Ķ���������Ǥϥɥ��������ߤޤꤹ���桢�����м���Υϥ���Ūȯ���ˤ��������ɲ����夲��ǯ���������줿�������ꡢ�߰¥ɥ�������˿���䤹����
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ�����åץ��åפ��ƾ�Ҥ��������û�����ǽ�������9��2����������@39,080�ߤ�Ķ����9��27����������@39,829�ߤ�������ɸ�Ǥ��롣�����������뭢��ȿȯ��ư������¤ʾ徺���ܻؤ����̡ˤ���³���Ƥ���Τǡ������岼�˿���ʤ��������˾�������ư���䤹����
33�ȼ���28�ȼ郎�徺�������徺Ψ�ȥå�5�ϡ���ԡ�1�̡ˡ��ݸ���2�̡ˡ��ڷ���3�̡ˡ�����¾��ͻ��4�̡ˡ������ӥ���5�̡ˤȤʤä���
���������
�ɲ����夲����Τ����ճ�����������ܳ���� 10��04��
�������ƹ��������ȿ�����DJIA -184.93 @42,011.59, NASDAQ -6.65 @17,918.48, S&P500 -9.60 @5,699.94�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�146������Ⱦ��������߹�ɥ�¿��Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤Ͼ夲��������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������1,150���Ф��ơ�������������448�Ȥʤä���ƭ��쥷����108.63%����ڥץ饤�����������3��8802���ߡ�
TOPIX +10 @2,694
����ʿ�� +84�� @38,636��
�ƹ�Ǥϡ�����������إꥹ���ʥ����饨��ˤ�륤���ؤ���������ˤ��Ф���ٲ�������ޤ��桢������9��������פ�ȯɽ��������Ȥʤ��ͻҸ��ࡼ�ɤ����ޤä�������ˡ�10��1���˻Ϥޤä��ƹ���ϫƯ�Ԥˤ�륹�ȥ饤����ʪή���Ф��밭�ƶ��⿴�ۤ��졢�������ȳ�30��ʿ�Ѥϰ��348�ɥ�¤ޤDz�������̤����ä���
����10��4��������Ծ�Ǥϡ�������ɲ����夲��ľ���ˤϤʤ��Ȥδ�¬�����㤤��ͥ���Ȥʤä���2���������м��꤬���ɲ����夲��Ķ��ˤʤ��פ�ȯ���������ᡢ������夲�λ��Ǥ���®�˸��ष������ʿ�Ѥ�200�߶�徺������̤����ä��������ν꿮ɽ������Ǥ⡢�ޡ����åȤ����ۤ��Ƥ�����ͻ�������Ǥζ������äϽФƤ��ʤ��ä������������ܻ��֤θ��9��ȯɽͽ���9���Ƹ������פη�̤�Ƚ������ޤǤ��Ѷ�Ū�ˤ�ư���ä���
����������Ծ����ħ�ϡ���굥����-10%�ˡ���������-9%�ˡ����������-6% �ˤʤɳ������ε�����ä����������ƹ����ϫƯ�ԤΥ��ȥ饤����������뤷�����ȤǤ��롣����Ծ�����ѻԾ����곤�������礭����������2023ǯ�����饳��ƥ����α��¤Ͼ徺���Ƥ���������ǯ�ƾ�ʹߤϼ��뤬�ˤϤ���ᡢ����ƥ������¤Ⲽ���Ĵ�ˤ��ä�������Ǥ⥹�ȥ饤����Ĺ�����Х���ƥ������¤��ƤӾ徺����ȴ��Ԥ���Ƥ����������Υ��ȥ饤���������«�������ᡢ����ȿȯ�δ��Ԥ��쵤�ˤ��ܤ��������꤬����������
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ��ۤܽ������Ǿ�����Ȥʤä����ƹ���������Ƥ⤽��ή��˰���ĥ��줺������ˤʤä��Ȥ����˺������ܳ�������Ū�ʷ�Ĵ���������롣���κ���ˤ���Τ�������ɲ����夲��������ˤʤä��Ȥ����ޡ����åȤδ�¬��������������������������뭢��ȿȯ��ư������¤ʾ徺�����̡ˤǤ��뤳�Ȥ�ռ����Ƥ���������
����9���Ƹ������פη�̤���ɽ���줿��ͽ�ۤ��ڤ���Ķ������Ѿ����η�Ĵ���������ᡢFRB�ˤ�뼡���ɲ���������0.50%�Ϥޤ��ʤ��������Ȥθ������顢0.25%�ȸ����������®�������������η�̡������ߡ������ϱ߰¥ɥ�⤬�ʤ�Ǥ��ꡢ1�ɥ��148����Ⱦ�Ф�ư���Ƥ��롣�ޤ����ƷкѤθ���Ϥʤ����եȥ��ǥ�����Τȴ��Ԥ��ޤ��ޤ���ޤꡢ�Ƴ�����徺���Ƥ��롣���ΤޤԤ��С��轵�����������ܳ����礭���夲�ƻϤޤꤽ������â�������ν����˥����饨�뤬�������Ф����絬����������Ϥ��ʤ���ФȤ�������դ��ǤϤ��뤬��
33�ȼ���30�ȼ郎�夲�����徺Ψ�ȥå�5�ϡ��۶ȡ�1�̡ˡ���������ú��2�̡ˡ��ŵ���������3�̡ˡ���ԡ�4�̡ˡ��ѥ�ס����5�̡ˤȤʤä���
���������
�����м���Ρּ�ΤҤ��֤��פΤ褦��ȯ���DZ߰¥ɥ��Ȥʤꡦ���� 10��03��
�������ƹ�������Ͼ�����Ȥʤä���DJIA +39.55 @42,196.52, NASDAQ +14.76 @17,925.12, S&P500 +0.79 @5,709.54�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�146����Ⱦ�Ф�������߰¥ɥ����Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤ϲ�����������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������1,291���Ф��ơ�������������309�Ȥʤä���ƭ��쥷����102.86%����ڥץ饤�����������4��2946���ߡ�
TOPIX +32 @2,684
����ʿ�� +743�� @38,552��
�ƹ�Ǥϡ�ADP̱��������ѼԿ���14.3�������áʡ�ͽ��12.0���͡����������10.3���͡ˤȤ���������̤Ȥʤꡢ�Ƹ��Ѥ�����������������ȿ�Ǥ�����10ǯ��������������3.743%����3.784%�����ä�����������������ȯɽ�����9���Ƹ������פ���������ȴ��Ԥ���Ƥ��롣�����������饨��ȥ�����������������إꥹ���ι�ޤ꤬������Ƭ���ޤ����������ȳ�30��ʿ�Ѥϰ��190�ɥ���������̤����ä���
����10��3��������Ծ�Ǥϡ����ٻԾ�DZ���줬�߰¥ɥ��ؿ��줿���Ȥ�ȿ�����ơ���ư�֤䵡���ʤ�͢�д�Ϣ�������濴�����졢����ʿ�Ѥξ夲���ϰ��1,000�ߤ�Ķ�������ƹ�Ծ��ȾƳ�δ�Ϣ�������徺����ή�������ơ�������쥯�ȥ���䥢�ɥХ�ƥ��Ȥʤ�ȾƳ�δ�Ϣ������夲������ͻ���ﲽ�ʡ��ɲ����夲�ˤ��Ѷ�Ū�ǥ����ɤȸ����Ƥ��������м��꤬��10��2����ο��������������ۤȤ����̤θ塢��������夲�ˤ�����Ū�ʻ������������ı��β���������Ф��밭�ƶ��������Τ�������ñ�˳θǤȤ�����ǰ���к��μ����ʤ������ʤΤ�����̱����������������ȯ�����鸫��ȡּ�ΤҤ��֤��פΤ褦��ȯ���˥ޡ����åȤϿ���줿���ˤʤ롣���������ơ������ϰ����1�ɥ��147����ޤDZ߰¥ɥ��Ȥʤä��������ʤ��������͢�д�Ϣ�������濴�����ܳ������줿������������������إꥹ���ι�ޤ�����Ǥʤ����������ˤ�9���Ƹ������פ�ȯɽ������Τǡ���������ϳ����Ťˤʤꤽ������
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ�����åץ��åפ����礭��ȿȯ������Ҥ��������û�����ǽ�����������ǺƤӾ������10����ưʿ�����ξ����夷����
33�ȼ���28�ȼ郎�夲�����徺Ψ�ȥå�5�ϡ��ݸ���1�̡ˡ�������2�̡ˡ������ʡ�3�̡ˡ�Φ����4�̡ˡ������ӥ���5�̡ˤȤʤä���
���������
��������ζ���������������Ƴ��� 10��03��
�������ƹ��������ȿ�����DJIA -173.18 @42,156.97, NASDAQ -278.81 @17,910.36, S&P500 -53.73 @5,708.75�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�144�����Ⱦ�Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤ϲ�����������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������248���Ф��ơ�������������1,370�Ȥʤä���ƭ��쥷����103.18%����ڥץ饤�����������4��3895���ߡ�
TOPIX -39 @2,652
����ʿ�� -843�� @37,809��
�ƹ�Ǥϡ���������饨��˥ߥ����빶������Ȥ����������������إꥹ���ι�ޤ꤬�������줿��������쳤�ߤȥᥭ�����Ѥǹ���ϫƯ�ԤΥ��ȥ饤�������ꡢ���줬�ʵ������ˤĤʤ���ΤǤϤʤ����ȷ�ǰ����ޤ������ȿ�����¾��������������إꥹ���ι�ޤ��ȿ�Ǥ��Ƽ��ؤ�ƨ���ꡢ��Ĺ����Ĥ������Ĺ��������10ǯ�������ˤ�������3.802%����3.729%���㲼������
����10��2��������Ծ�Ǥϡ���������ζ�������������ƹ����ȿ���ή�줫�顢������쥯�ȥ���䥢�ɥХ�ƥ��Ȥʤɤ��ͤ���ȾƳ�δ�Ϣ�������Ż������������濴�����������ʿ�Ѥ��礭���������������饨���ȿ���ɬ�������������ʿ�Ѥβ������ϰ��1,000�ߤ�Ķ������
¾�����չԹ⤷�������⤢�롣��������ζ���������������������դ���Ȥλ��Ǥ��鸶����ʪ���ʡ�WTI�ˤϾ徺����������ȡ�INPEX�ʤɤθ�����Ϣ���������졢����ʪ���ʤ����羦�Ҥ��Ϣ���Ȥ������줿������������͢������ư̮�Ǥ���ۥ�ॺ�������̤��Ƥ��ꡢ�������פ���2���������2,000���Х������������γ������̲᤹�롣�����졢�ۥ�ॺ��������������뤳�Ȥ�����С��������ʤε�ƭ�����ʤ�������ȡ��ƹ�ڤ�������ǥ���ե줬��dz�����ƹ���ɲ���������̵���±������롣����ȡ��ޤ��߰¥ɥ���Ĵ�Ȥʤ뤬������ˤ��������ɲ����夲���䤹���ʤꡢ���ܳ��ϲ����롣���äȤ���ʥ��ʥꥪ��Ƭ�������®�Ƕ��ä���
�ޤ��������п����꤬�����륢������NATO�����ߤ�����ˡ����Ź����������ݽꡢ���������ʤ��ɱҴ�Ϣ���������¤߾徺�������ƹ�Ծ�Ǥ�Ρ������åס�����ޥ����å����ɡ��ޡ�����ʤ��ɱҴ�Ϣ�������夲����
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ�������ȿ��ƾ������10����ưʿ���������������ޤ�25����ưʿ�����ξ�ǿ�ܤ��Ƥ���Τǡ����˿��������˿�����Ψ�������⤤�ȸ��Ƥ��롣���������礭�ʰ��������㤨�С������饨��ȥ���������������ȯ�ˤ����ӽФ��Ƥ���С����㡼�ȡ���ǥ������Фʤɴ�ñ�˿���Ф���롣���Τ����������ɤߤ�ɬ�פ�������������ǤϾ��Ƥʤ������ɤߤϳ�����ˤˡַ��Ū�ˡ״ְ㤨�롣���������ˡ���䤦ɬ�פ����롣
33�ȼ���28�ȼ郎������������Ψ�ȥå�5�ϡ�������1�̡ˡ��ŵ������2�̡ˡ���ԡ�3�̡ˡ��ݸ���4�̡ˡ�������5�̡ˤȤʤä���
���������
���˥���å��ˤ��߹�ʹԤ������ϻߤޤä��褦�� 10��02��
�������ƹ�������Ͼ�����Ȥʤä���DJIA +17.15 @42,330.15, NASDAQ +69.58 @18,189.17, S&P500 +24.31 @5,762.48�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�144�����������߰¥ɥ����Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤�ȿȯ��������ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������1,272���Ф��ơ�������������331�Ȥʤä���ƭ��쥷����108.84%����ڥץ饤�����������4��1843���ߡ�
TOPIX +45 @2,691
����ʿ�� +732�� @38,652��
�ƹ�Ǥϡ��ѥ�����FRB��Ĺ���ֱ�ǥޡ����åȤβ��٤��ɲ����������Ԥ����������Ȥǡ��ķ��Ծ�Ǥ�10ǯ������꤬3.80%����դ�����̤����ꡢ�������ȳ�30��ʿ�Ѥϰ��383�ɥ�ޤDz���������������9���FOMC��0.50%���������������¸��������Ȥȡ��ƷкѤΥ��եȥ��ǥ����Ԥ�٤��˳����Ͼ����˾夲�ư��������������ȳ�30��ʿ�Ѥ�S&P500��Ϣ���Ǻǹ��ͤ�������
����10��1��������Ծ�Ǥϡ��ѥ�����FRB��Ĺ����������ޤ��ʤ������������Ȥ��ƹ�������ɲ���������¬�����ष����ɽ���줿9��ζ�ͻ����������Ρּ�ʰո��פ���������ɲ����夲��¬�����ष��12��ޤǤ��ɲ����夲�Ϥʤ��������Ȥ�����¬�ˡ����ٻԾ�Ǥϱ���줬1�ɥ��144����ޤDz���Ʊ߰¥ɥ��Ȥʤä������������͢�д�Ϣ�������濴�����������ʿ�Ѥϼ�Χȿȯ�������㤤�����ꡢ����ȿȯ�������ɱ��϶������Ѷ�Ū����������������102�����������ǡ���ɩ�Ź������Ź���IHI�ʤɤ��ɱҴ�Ϣ���������줿����®�ʱ߹�ȳ����ε���������л�ϻԾ�ؤ���θ���Ϥᡢ���������������ä����Ȥ���߹�ʹԤ������ϻߤޤä��褦���������ι⤤�ɥ����ꡢ�������㤤���㤤�Υݥ�������ݻ����������������ʬ�Υ����Ȥ��ʧ��ʤ���Фʤ�ʤ�����Ĺ³�����ˤ�����
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ�������Ĺ�籢����Ⱦʬ���餤�����ᤷ����25����ưʿ������10����ưʿ�����������Ǥ��ꡢ�����Ϥ��ξ�ǿ�ܤ��Ƥ��롣8��5�������Ȥ���ȡ����ͤȰ��ͤ��ڤ�夲�Ƥ��롣���㡼�Ȥη��Ȥ��Ƥϰ����ʤ���
33�ȼ���30�ȼ郎�夲�����徺Ψ�ȥå�5�ϡ�������1�̡ˡ��ڷ���2�̡ˡ������3�̡ˡ��ŵ������4�̡ˡ��������ʡ�5�̡ˤȤʤä���
���������
���ڡ����Υȥåפ�
|
|