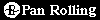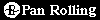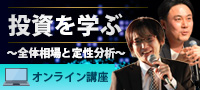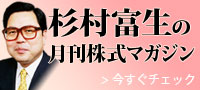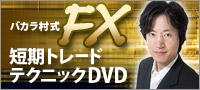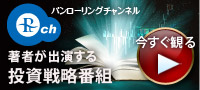|
����������Υȥ졼��������
|
7����Ƹ���ư��Ĵ����JOLTS�ˤ��夤��̤��ä����Ȥ����ơ����� 08��30��
�������ƹ��������³��������DJIA +292.69 @34,852.67, NASDAQ +238.63 @13,943.76, S&P500 +64.32 4,497.63�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�146������Ⱦ����Ⱦ��������߹���Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤Ͼ夲��������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������1,000���Ф��ơ�������������740�Ȥʤä���ƭ��쥷����113.08%����ڥץ饤�����������3��3061���ߡ�
TOPIX +10 @2,313
����ʿ�� +106�� @32,333��
�ƹ�Ǥ�7��θ���ư��Ĵ����JOLTS�ˤǵ�ͷ����2021ǯ3����������˸�������6��ʬ�Ⲽ���������졢����˼�ȯŪ��Υ��Ψ��2.3���2021ǯ1����������Ȥʤä����Ĥޤꡢ���⤤�¶�����ž������ư�����ߤäƤ������Ȥ��̣���롣����ˤ�ꡢ����ե�ΰ���ȤʤäƤ���ϫƯ����β�Ǯ�����¤餰�ȴ��Ԥ��졢�����徺���Ф����ǰ�����ष������Ĺ�������ʡ�10ǯʪ��������ˤ��㲼�����ϥ��ƥ������㤤�ᤵ�줿���ƥ����8%�徺������������ȾƳ�Ρ�GPU�����Υ��̥ӥǥ�����4��夲�����ե���ǥ�ե���ȾƳ�γ��ؿ���SOX�ˤϤۤ�3%�夲��������3�����ؿ���·�ä�³��������ϫƯ����δ��¤������Ƥ���ΰ�̱�����ä�����Ǥ��ꡢ�������ǯ������������˸���������Ū�������Ȥ�ʤꤦ��Τ����롣
�ƹ���������ơ�����������ʿ�Ѥ�3��³���������ƹ�Ծ�Ǥϥϥ��ƥ������礭���夲������ή�������ơ�������쥯�ȥ���䥢�ɥХ�ƥ��Ȥʤɤ�ȾƳ�δ�Ϣ������¼�������������ʤɤ��Ż��������������줿���夲���ϰ��300�ߤ�Ķ�����������ͤǤ���꤬ͥ���Ȥʤä���
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ���������25����ưʿ�����ξ�˺���夷��������Ҥ��������û�����ǽ��������ޤ����ߥ���ͥ���������Ƥ����ʳ��Ǥ��롣
33�ȼ���21�ȼ郎�夲�����徺Ψ�ȥå�5�ϡ���ԡ�1�̡ˡ�������2�̡ˡ��ڷ���3�̡ˡ�����¾��ͻ��4�̡ˡ���̩�����5�̡ˤȤʤä���
���������
�ޤ�����Ÿ�� 08��29��
�������ƹ��������³��������DJIA +213.08 @34,559.98, NASDAQ +114.48 @13,705.13, S&P500 +27.60 @4,433.31�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�146������Ⱦ�Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤Ͼ夲��������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������1,221���Ф��ơ�������������538�Ȥʤä���ƭ��쥷����113.74%����ڥץ饤�����������2��805���ߡ�
TOPIX +4 @2,303
����ʿ�� +57�� @32,227��
�ƹ�Ǥϡ��轵���Υ��㥯����ۡ����ĤǤΥѥ륨��FRB��Ĺ�ιֱ������ʤ��̲ᤷ�����ɲ����夲���Ф�����٤ʷٲ����¤餮�������Ĺ�������ʡ���10ǯ�������ˤξ徺�������������Ȥ�����ư���Ȥʤä���
���������ܳ��ϡ��ƹ����ȿȯ�������³�����������ͤ��Ť��ʤꡢ�����㤤�����ϤۤȤ�ɤʤ��������ޤǼ�Χȿȯ�Ǥ��롣����ʿ�Ѥϰ��200��Ķ�夲����FRB������ե��ɸ�Ȥ������ܤ��Ƥ���7��Υ����Ŀ;���ٽС�PCE�ˤ������������ˡ��������ˤ�8����Ƹ������פ�ȯɽ�����롣���ʵ��θ�®�˲ä��ơ�ʡ����츶ȯ�ν����峤�����Ф�������ط��ΰ�������ǰ���졢���Υ���Х���ɼ��פθ����������������㱿ư���Ф����¤��Ф��褿���ޤ���ȾƳ�δ�Ϣ������ư�����ߤ����Ȥ�������Τ��ߤ��ˤĤʤ��äƤ��롣
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ���������25����ưʿ�������ܤ���ޤ�ȿȯ�����褿���������ΤȤ�����û�����ǽ����Ƥ��ꡢ��ȴ���Ǥ��Ƥ��ʤ����㤨���Ū�˾�ȴ���Ǥ����Ȥ��Ƥ⡢25����ưʿ�����η������������Ǥ���¤��������˲�ʤ���
33�ȼ���24�ȼ郎�夲�����徺Ψ�ȥå�5�ϡ��ŵ���������1�̡ˡ���ư����2�̡ˡ�������3�̡ˡ�Φ����4�̡ˡ������ӥ���5�̡ˤȤʤä���
���������
�ƶ�ͻ��������ϡ֥ȥ�ͥ�θ������������꤬�����Ϥ�Ƥ���� 08��29��
�轵���������������ƹ�������Ͼ夲����DJIA +247.48 @34,346.98, NASDAQ +126.68 @13,590.65, S&P500 +29.40 @4,405.71�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�146������Ⱦ��������߰¿��Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤Ͼ夲��������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������1,508���Ф��ơ�������������276�Ȥʤä���ƭ��쥷����116.55%����ڥץ饤�����������2��8936���ߡ�
TOPIX +34 @2,300
����ʿ�� +546�� @32,170��
�ƹ�Ǥϡ��������ƥ�Ϣ���Ťηкѥ���ݥ�����ʥ��㥯����ۡ����ġˤǥѥ�����FRB��Ĺ���ֱ����������ͽ���̤ꡢ��ͻ����������Ѷ�Ū�ʥ�����Ū��ȯ�����ä����ᡢ��������ͥ���Ȥʤä���ǯ��ˤ⤦�������ɲ����夲�����ꤽ�����������줬�Ǹ�Ǥ���ȥޡ����åȤϸ��Ƥ��ꡢ1ǯ���Ȥϰۤʤ꺣�����夲�����ν��פǤ��롣�ȥ�ͥ�θ������������꤬�����Ϥ�Ƥ���Ȥθ�����ͥ���Ȥʤꡢ�ڤ��֤��ƾ夲�ƽ�����������ʿ�Ѥξ夲���ϰ����300�ɥ��Ķ������
�ƹ���ξ徺������ơ���������������Ծ��夲�����ե������ȥ�ƥ��������ʤɤ��Ϳ�����濴�����������ʿ�Ѥ��礭���徺���������������������ΰ����Ǥ������뤳�Ȥ����ƾ峤����ؿ��ȹ���ϥ�ؿ����徺����ȡ����ܳ����㤤����Ū�˻٤�������������ʡ����츶����ȯ�Ž�ν����峤�����Ф��ꡢ����ط�����®�˰������Ƥ��뤿�ᡢɴ��Ź��������Φ���ʤɤΥ���Х�������������줿��
�����峤�����Ф��깳�Ĥ�����餻���ä����ܳ��Ϥ��꼡���Ǥ��ꡢ��������ܤؤ�����ι�ԥ�����ư����������ǥ�������ƻ����Ƥ��롣16�Ф���24�ФޤǤ��Ի����μ�Ԥμ���Ψ��6��ˤ�21.3%�Ȳ��ǰ��ȹ�������ȡ�������ܤ�������8���μ�Ԥμ���Ψ�θ�ɽ����ߤ����ȯɽ�������Ȥϵ����˿�����������ۤ�������θĿ;���Ͽ���鷺�����ܤؤΥ���Х���ɾ���β�������Τ��ȴ��������ޡ����åȤ�ȿ�������������ܳ�����ħ���ä��������������Ǥ���ʪ����ब�㤯������Ǽ��¤��ɤ����ܤϡ�1�ɥ��146����α߰¤��ä�����ʹ�ʾ�γ��鸫��С�Ķ���㤤���פ˴�����Ϥ��Ǥ��롣�㤨���Υ���Х���ɼ��פ����Ԥ����ۤɤʤ��Ƥ⡢¾���ι�ԼԤ����ä�����������ޤ�����������ͽ�ۤξ徺�����γ�礫�鲼�������γ�������Ʒ������ӥ������ǥ������͡���¼�ʤ����ڷ������Ф��Ƥ��뤬���ȥ졼�����������֤�HP����ǡ�����³����иĿͤǤ���Ǥ���ˤ�7����1������8��³���ƥץ饹�ǿ�ܤ��Ƥ��롣�Ĥޤꡢ���ܴ�����ΤǸ���ȡ����Ӹ��̤��ϲ�����³���Ƥ���Ȥ������ȤǤ��롣
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ��轵�ζ������˳������10����ưʿ�����������ƤӲ����������ޤ��Ͽ�������˲�������25����ưʿ�����ξ�˺����Ǥ��뤫�ɤ��������ܤ��Ƥ��롣
33�ȼ��桢������Φ���������31�ȼ郎�夲�����徺Ψ�ȥå�5�ϡ�������1�̡ˡ���������ú��2�̡ˡ�Ŵ�ݡ�3�̡ˡ��������ʡ�4�̡ˡ�͢���ѵ����5�̡ˤȤʤä���
���������
�֥��̥ӥǥ����פ�פ���֥ѥ����롦����å��פκ���Ȥʤ뤫�� 08��26��
�������ƹ���������礭��ȿ�����DJIA -373.56 @34,099.42, NASDAQ -257.06 @13,463.97, S&P500 -59.70 @4,376.31�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�146������Ⱦ��������߰¿��Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤ϲ�����������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������621���Ф��ơ�������������1,127�Ȥʤä���ƭ��쥷����109.08%����ڥץ饤�����������2��7987���ߡ�
TOPIX -20 @2,266
����ʿ�� -663�� @31,624��
�ƹ�Ǥϡ����̥ӥǥ����ι��軻�ʽ�����9.4�ܡˤ���Ӷ������Ӹ��̤����̤ˤ�����������Τ��㤤ͥ���ǻϤޤä����������������˥��㥯����ۡ����ĤǤΥѥ륨��FRB��Ĺ�ιֱ���Ƥ��뤿�ᡢ���̥ӥǥ����ϼ���˾徺����̾�������ȡ�ȾƳ���������濴�����׳�����꤬ͥ���Ȥʤä����ե���ǥ�ե���ȾƳ�γ��ؿ���3%�������û���֥��̥ӥǥ����פ�פ�����ꡢ���礦��1ǯ���λ��Τ褦�ʡ֥ѥ����롦����å��סʡ��ͻ�����˴ؤ��ƥ�����ȯ���ˤκ���������Ƥ���褦����
����������Ծ�Ǥ⡢�֥��̥ӥǥ����פ�פ�����ꡢ������쥯�ȥ���䥢�ɥХ�ƥ��Ȥʤɤ�ȾƳ�δ�Ϣ�����ϵ��������˥��եȥХ��礭��������������3��������������ʿ�Ѥ�300��Ķ���������Ƴ���������Τ��礭��������������ʿ�ѤϺ�����4���֤�����800��Ķ�夲�Ƥ����Τ����׳�����꤬�аפ��Ϲ礤�Ǥ⤢�ä�����ǯ����������ޤǤδ��֤Ǹ���ȡ�����ʿ�ѡ�ȾƳ�δ�Ϣ��������Ť��⤤�ˤϥ��̥ӥǥ����ξ夲���������˹⤤��شط��ʡ���ط���0.96�����̥ӥǥ����γ���������ʿ�Ѥγ����ǡ������¤٤�Х��������COREL�ؿ��Ǵ�ñ�˷��Ǥ���ˤ����롣�Ҳ����Τ�����AI�ˤ������������ƹԤ����Ȥ�Ĺ���ܤǸ��줬�����徺�ˤĤʤ���Ϥ������줬����������γ����ȥ졼�ɵ��ѡפ������������ספΰ���Ǥ��롣������������������ζ�ͻ�������礭��ȿ�������ΤǤ��롣���줬��ή�ԡפǤ��롣
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ����������礭��ȿ�����������10����ưʿ�����β��غ������߹������25����ưʿ����������Ǥ����˺���10����ưʿ������ȴ�����������ޤǤ�ư���Ǥϡ��⤦�������ͤ�ư���ˤʤꤽ���Ǥ��롣
33�ȼ���30�ȼ郎������������Ψ�ȥå�5�ϡ��ŵ������1�̡ˡ�������2�̡ˡ�����¾���ʡ�3�̡ˡ���Ŵ��°��4�̡ˡ������5�̡ˤȤʤä���
���������
�ޡ����åȤ����ˤ��른�㥯����ۡ����ĤǤ�FRB��Ĺ�α��� 08��24��
�������ƹ�������Ͼ徺������DJIA +184.15 @34,472.98, NASDAQ +215.16 @13,721.03, S&P500 +48.46 @4,436.01�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�145������Ⱦ��������߹���Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤�³����������ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������1,153���Ф��ơ�������������610�Ȥʤä���ƭ��쥷����107.80%����ڥץ饤�����������2��9084���ߡ�
TOPIX +10 @2,287
����ʿ�� +277�� @32,278��
�ƹ�Ծ�Ǥϡ�8����ƹ���ô���Էʵ��ؿ���PMI�ˤ������50.4��Ⱦǯ�֤�ο����㲼�����ᡢ��ͻ���������Ĺ������ǰ���¤餮��Ĺ�������ʡ�10ǯ�������ˤ��㲼����������ˤ�����ȿ���������������������ˤϡ�����������ǽ��AI�ˤ˻Ȥ����������ȾƳ�Ρ�GPU�����Υ��̥ӥǥ����η軻ȯɽ�����ꡢ�⤤���Ԥ˻٤����ƥ��̥ӥǥ������ʥ������������ǤϤʤ��ˤ�3.17��夲��������ƥ��AMD�ʤ�CPU����¾��ȾƳ��������3��Ķ�夲����
����������Ծ�Ǥϡ�ȯɽ���줿���̥ӥǥ����ι��軻���ݤ�������Ȥ���������쥯�ȥ���䥢�ɥХ�ƥ��ȡ�GPU�θ������֤��äƤ���ˤʤɤ��ͤ���ȾƳ���������濴�����������ʿ�Ѥ�³���������ޤ�������Ծ�Ǥϥϥ��ƥ������ǹ�������ϥ�ƥå��ؿ������4%Ķ�徺�������Ȥ����ܳ��٤�������¾������Ĺ���������㲼��ȿ�Ǥ��ơ����ٻԾ�Ǥϱ߹⡦�ɥ�¤ؿ��줿���ᡢ�ȥ西�������ʤɤμ�ư�ֳ��ΰ�Ѥ����줿���֥��̥ӥǥ������̡פˤ�ꡢ������쥯�ȥ����57�ߡˤȤ䥢�ɥХ�ƥ��ȡ�30�ߡˤ�2��������������ʿ�Ѥ�87�߲����夲�����轵�γ�������������8��25���Υ��㥯����ۡ����Ĥǥѥ�����FRB��Ĺ���ɤ�ʥ�å�������ȯ���뤫���������������ե���臘����˥�����Ū�ʥ�å�������Ф��Ƥ���ȻԾ�Ͽȹ����Ƥ��롣
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ���������10����ưʿ�����ξ�˺���夷�Ƥ�������������³�����Ʋ�������25����ưʿ�����ˤ⤦�������Ϥ��Ȥ����ޤ�ȿȯ�����褿�����������ޤ��¿����ƤϤ����ʤ���8��1����������@33,488�ߤ��ȴ������ʤ��¤ꡢ������줬��³���Ƥ��뤫������ޤ��ϡ���������25����ưʿ�����ξ�˺���夷�ʤ��ƤϤʤ�ʤ�������ʬ�⤯�夬��ʤ��Ȥ䤬�ƾ�����ȿ�������Ǥޤ�25����ưʿ�����β������߹��ߡ����ߥȥ��ɤ��³���뤳�Ȥ����ʤ��ʤ��������
33�ȼ���28�ȼ郎�夲�����徺Ψ�ȥå�5�ϡ��۶ȡ�1�̡ˡ����ߡ�2�̡ˡ���������ú��3�̡ˡ������̿���4�̡ˡ��ڷ���5�̡ˤȤʤä���
���������
���̤β����ߤޤ��10����ưʿ�����β��� 08��24��
�������ƹ�������Ϲ�¤ޤ��ޤ��Ȥʤä���DJIA +85.83 @34,374.66, NASDAQ +8.28 @13,505.87��S&P500 -12.22 @4,387.55�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�145�����Ⱦ��������߹���Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤Ͼ夲������ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������1,410���Ф��ơ�������������354�Ȥʤä���ƭ��쥷����112.23%����ڥץ饤�����������2��5093���ߡ�
TOPIX +11 @2,277
����ʿ�� +154�� @32,010��
�ƹ�Ǥϡ������Υ��㥯����ۡ����ĤǤΥѥ�����FRB��Ĺ�ιֱ���Ʒٲ����ʡ����夲Ĺ����������ˤ����ޤäƤ��롣������桢��Ĺ�������ʡ�10ǯʪ��������ˤ��徺��Ĵ�ʰ��4.36%�ޤǾ徺�ˤȤʤäƤ��ꡢ������������Ʋ�������S��P�������Х뤬������ư��ͻ�����Ĵã�����Ȥξ徺�ʤɤ���ͳ�˰����϶�γ��դ���������������ᡢ�϶�����Ǥʤ�JP��륬������������Х����֡�����ꥫ�����ƥ����롼�פʤɤ�����Ԥ⸮�¤�2��Ķ�β����Ȥʤä���
����������Ծ�Ǥϡ��ƹ���β��������ƶ�ͻ�������줿����Ω������桢�Ƴ����ؿ���ʪ����Ĵ�˿�ܤ��Ƥ������ᡢ��������ڤ��֤������ä˥ᥬ�Х���Ĺ�������ξ徺������ǫ���夲�ƽ����������ܤ�Ĺ�������ʡ�10ǯʪ��������ˤ�0.01%�夲��0.675%�ؾ徺����2014ǯ1����衢9ǯ7����֤�ι���Ȥʤä������η�̡��ɥ�߰��إ졼�Ȥϱ߹⡦�ɥ�¤������ؿ��줿��
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ���������10����ưʿ�����ξ�˺���夷��������Ǥ�ä����̤β����ߤޤ�Υ�����Ȥʤ롣1��2���ְ���ˤޤ�10����ưʿ����������ळ�Ȥ�¿���������λ���ľ��ΰ��ͤ������˺�ȿȯ����Ф��θ�ϻä��夲����ɤ�Τ����ФǤ��롣
33�ȼ���30�ȼ郎�夲�����徺Ψ�ȥå�5�ϡ�Ŵ�ݡ�1�̡ˡ���Ŵ��°��2�̡ˡ��ѥ�ס����3�̡ˡ��ŵ���������4�̡ˡ�Φ����5�̡ˤȤʤä���
���������
��Χȿȯ�������㤤��ͥ�� 08��23��
�������ƹ�������Ϲ�¤ޤ��ޤ��Ȥʤä���DJIA -36.97 @34,463.69, NASDAQ +206.81 @13,497.59, S&P500 +30.06 @4,399.77�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�146������Ⱦ�Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤Ͼ夲��������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������1,329���Ф��ơ�������������443�Ȥʤä���ƭ��쥷����111.05%����ڥץ饤�����������2��7279���ߡ�
TOPIX +24 @2,266
����ʿ�� +291�� @31,857��
�ƹ�Ծ�Ǥϡ���ͻ���������Ĺ�����ؤηٲ����Τ�����10ǯ�������ϰ��4.35%��2007ǯ11�����ο��ޤǾ夲�����������轵�ϼ���3�����ؿ���·�äƽ��֤�2%Ķ�β����ȤʤäƤ������ᡢ��Χȿȯ�����β������㤤��ͥ���Ȥʤä����äˡ����̥ӥǥ����ʤɤΥϥ��ƥ�������ƥ��餬����ƥʥ����å����礭���徺������
���������ܳ����̤ϡ���1�˥ʥ����å��������徺����2�˱߰¡��߹��ư������3���轵���礭�ʲ���������ʿ�Ѥ�1,000��Ķ�β����ˤ���μ�Χȿȯ���Ԥˤ�ꡢȿȯ����������ʿ�Ѥξ夲���ϰ��340�ߤ�Ķ�������߰¡��ɥ������ƥȥ西��Ϥ���Ȥ��뼫ư�ִ�Ϣ�������夲����Ĺ�������ξ徺������ƥᥬ�Х���夲��������������������˳�������㤤����Ͼ��ͤ��Ť��ʤä��������ˤϹ�ݷкѥ���ݥ�����Ǥ���֥��㥯����ۡ����Ĥ��Ƥ��ꡢ�����Ͽ��Ť��ä���
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ��岼�ˤҤ��������û�����Ǿ徺����������Ǥ�ޤ���������10����ưʿ�����β��ǿ�ܤ��Ƥ��롣���ߥ���ͥ�β��¤ޤ��Ϥ������ȿȯ�ʤΤǻä���ȿȯ���³���뤫��
33�ȼ���30�ȼ郎�夲�����徺Ψ�ȥå�5�ϡ���ԡ�1�̡ˡ�͢���ѵ����2�̡ˡ��ڷ���3�̡ˡ������4�̡ˡ���������ú��5�̡ˤȤʤä���
���������
û���ڤˤ����ʪ�����ᤷ��Ƴ�Ǿ���ȿȯ������������ 08��21��
�轵���������ƹ�������Ϲ�¤ޤ��ޤ��Ȥʤä���DJIA +25.83 @34,500.66, NASDAQ -26.16 @13,290.78, S&P500 -0.65 @4,369.71�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�140����Ⱦ�ФǤ�ư�����ä������������ܳ����̤Ͼ夲��������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������1,177���Ф��ơ�������������587�Ȥʤä���ƭ��쥷����104.26%����ڥץ饤�����������2��5854���ߡ�
TOPIX +4 @2,241
����ʿ�� +115�� @31,566��
�ƹ�Ǥϰ����Ȥ������夲��Ĺ������ǰ��³���Ƥ��뤬����Ĺ�������ʡ�10ǯ�������ˤξ徺���������������ηʵ�����Ԥ���Ʃ���������ޤ��桢�����ư�����ι��罸�Ĥ��˥塼�衼����Ϣˮ�˻�ˡ��15���Ŭ�Ѥ���������������ȿ������ɤ��ʤ�����Ϣ���β����ʥ���ʿ�Ѥ�1���֤�780�ɥ벼��ˤˤ���ͤ����������㤤�����ꡢ�ƹ�����ΤȤ��ƤϹ�¤ޤ��ޤ��Ȥʤä���
����������Ծ�Ǥϡ���Ĺ�������ξ徺���������ơ�����û���ڤ������ؿ���ʪ���㤤�᤹���㤤ͥ���Ȥʤꡢ����ʿ�Ѥ������300��Ķ�夲����̤����ä������������㤤����ϡ��ʵ��Υƥ�����Τ��ᡢ����̱��ԡ������ԡˤ�8��21�����¼�Ū�����������������������3.55%����3.34��ءˤˤ⤫����餺��Ĵ�ʾ峤����ؿ������ϥ�ؿ����Ť��Ȥʤꡢ���ˤϾ��ͤ��Ť��ʤä������ν���������ܰ¤Ȥ����LPR5ǯʪ�����Ͽ����֤��Ȥʤä�����ʵ����Ф��륤��ѥ��Ȥ˵����䤬�դ����ᤫ�������ŵ�������Ʋ����������ʤ�����Ϣ�����ϰ���³�����줿�������ξ夲��û���ڤˤ����ʪ�����ᤷ�ˤ��Ȥ������礭�����ᡢ�����ʹߤ��³���뤫�ɤ�����
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ����ߥ���ͥ�β����դ�ޤDz���Ƥ��롣�����Ͼ岼�ˤҤ�����������Ʊ�����Ȥʤꡢ����դ�����������˴ؤ��Ƥ��礭���¤������ä����Ȥ��Ƥ��롣��������֤ˡ�(1)���Τ˲�������10����ưʿ������(2)�ˤ䤫�˲�������25����ưʿ�ѡ�(3)�ޤ����������60����ưʿ���������äƤ��ꡢ�����ϲ�������10����ưʿ�����β��ǿ�ܤ��Ƥ��롣���ߤϳ����������뭥����¤ʲ�����ˤǤ��ꡢ���Τޤޤ��ȸ�1���֤ۤɤdz����������뭦����¤ʲ�����̡ˤ����ꤽ����Ÿ���ȤʤäƤ��롣
33�ȼ���25�ȼ郎�夲�����徺Ψ�ȥå�5�ϡ��ŵ���������1�̡ˡ��۶ȡ�2�̡ˡ���ư����3�̡ˡ�������4�̡ˡ������ӥ���5�̡ˤȤʤä���
���������
����������γ����ȥ졼�ɵ��ѡס���63���ٶ������20��ǯ�ˤ�ͽ���̤꽪λ�� 08��21��
ͥ���ý���������å������Ǥ���
��63������롼�빽���ٶ���˻��ä���������4���֤�����ͤǤ�����
����������γ����ȥ졼�ɵ��ѡפ��ٶ���Ǥ�������롼�빽���ٶ������20��ǯ��ޤ��ޤ��������Υ֥�����20ǯ�ʾ�³�Ƥ��ޤ���
����ϥ��������ȥ졼�ɤη�������Ĵ���ơ�������ˡ���ä˵徺�����塢��������ͭ���ʼ����ˡ���Ƭ���������ޤ�����������ͭ�����ȸ³��ˤĤ��Ƥϡ��Ƽ��Ǹ��ڤ��Ƥߤơ��ֳ����ȥ졼�ɵ��ѡפΥ����ͥ�Ǥ��θ��ڷ�̤�ȯɽ���ޤ��礦��
�����ʤɳع��Ǥ��ٶ���ޤᡢ�ɤ�ʽ������⡢ͽ���������⤻�������դ�äȶ�����Zoom�ˤ���ơ������Ȥλ����Ǽ��Ȥ�ֵ�������������ǤϤۤȤ�ɲ���Ȥ��դ��ޤ���������ͥ���ýΤdzؤ�Ǥ��뤳�Ȥ�ñ�ʤ���ΤäƤ���»�Ϥʤ��פȤ����褦���μ��ǤϤʤ������Τޤ���������������������ɴ����Ԥ����Ȥ��Ǥ����Ķ����Ū�μ��פǤ������Τ褦��Ķ����Ū�μ���ñ�ˡ֤����ä�ʹ�����פǽ���餻�뤫����̤��ؤ�ͦ�����������������뤿����ϡפˤ��뤫�ϳ�����γؤӤ��Ф����������Ǥ�����ĥ��ޤ��礦��
���������
��Ĺ�������Τ���ʤ�徺�������ư��������þ�����ǡ����� 08��18��
�������ƹ��������3��³�����DJIA -290.91 @34,474.83, NASDAQ -157.70 @13,316.93, S&P500 -33.97 @4,370.36�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�145������Ⱦ��������߰¹���Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤ϲ�����������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������334���Ф��ơ�������������1,448�Ȥʤä���ƭ��쥷����103.47%����ڥץ饤�����������2��8832���ߡ�
TOPIX -16 @2,237
����ʿ�� -175 @31,451��
�����˸������줿��Ϣˮ�����Ծ�Ѱ����FOMC�ˤεĻ��ݤ�������Ū�����Ƥ��ä��������夲��Ĺ������ǰ����ޤä��������������ƶ����кѻ�ɸ���Ф��褿�����֤ο��������ݸ����������23��9000��ȻԾ�ͽ�ۤ�24�����ä������̤ʤ�м��ȼԤ��������뤳�Ȥϴ�Ф������ȤʤΤ����������������ۤܿ��դǤ��롣���ϡ����ȼԤ���������ۤ�ϫƯ���뤬�Ҥ������Ƥ��뤿�ᥤ��ե�Ψ��������ʤ��������夲���̤������ʤ��ȹͤ��롣���η�̡���Ĺ�������ʡ�10ǯ�������ˤ�4.328%�ʺ�ǯ10��21������ο��ˤޤǾ徺�������ᡢ����3�����ؿ���·�ä�3��³���������ˤ�ꡢ����3�����ؿ��Ϥ��٤�50����ưʿ�������Ȥʤä���
����������Ծ�Ǥϡ��ƹ����3��³��˲ä��ơ���������бĺƷ�����ä������ư�����Ǥ�������罸�Ĥ�8��17���˥˥塼�衼����Ϣˮ�˻�ˡ��15���Ŭ�Ѥ����������Ȥ�����ơ����ܳ����̤���꤬ͥ���Ȥʤä����⤦��Ĥ������ư�����ǻ�ⷫ�꤬�������Ƥ����˷˱�ԡʥ���ȥ�������ǥۡ���ǥ����ˤʤɤˤ�б���þ��Ϣ������ΤƤϤʤ����ȥޡ����åȤϿȹ����������Τ��ᡢ����Ϣ�����ʥե������ȥ�ƥ���������ŵ�������Ʋ���ԥ����ʤɡˤ����Υ���Х���������ʰ���ð�����粰��J�ե���ȡ���ƥ����ANA�����ĵ���Ŵ�ʤɡˤϸ��¤߲���������ʿ�Ѥβ������ϰ��350�ߤޤdz��礷����¾����������쥯�ȥ���䥢�ɥХ�ƥ��Ȥʤ�ȾƳ�δ�Ϣ�����ΰ�Ѥȥ˥ǥå�����ɩ�����ʤɤϾ夲������ǥե�кѤ˴٤äơ����ܲ��פ��뤳�Ȥ�3~5ǯ���٤����´������뤫�⤷��ʤ��ȥޡ����åȤϿ����˷�ǰ���Ϥ�褦����
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ���Ҥ�������������ǽ������������ͤǤ�³�����10���ڤ�25����ưʿ���������Τ�60����ưʿ�����β������߹�����褿�������ͤ���ͤⶦ���ڤ겼���äƤ��ꡢ���ߥ���ͥ�������Ƥ��롣���ߥ���ͥ�β����դ�ޤDz����Ƥ���Τǡ�����������Χȿȯ�����äƤ⤪�������ʤ������ߥǤϤ��롣�㤤�̤δޤ�»�������Ƥ���ͤϼ��μ�Χȿȯ���̡ʡ����ˤ��Ǹ��ƨ����ȸ��Ƥ����٤����Ȼפ���
33�ȼ���30�ȼ郎������������Ψ�ȥå�5�ϡ��ŵ���������1�̡ˡ�������2�̡ˡ����ߡ�3�̡ˡ�Φ����4�̡ˡ�������5�̡ˤȤʤä���
���������
��Ĺ�������ξ徺���ޤ����������Ĥޤ�³������ 08��17��
�������ƹ��������³�����DJIA -180.65 @34,765.74, NASDAQ -156.42 @13,474.63, S&P500 -33.53 @4,404.33�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�146������Ⱦ��������߰¿��Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤ϲ�����������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������561���Ф��ơ�������������1,214�Ȥʤä���ƭ��쥷����104.72%����ڥץ饤�����������3��2976���ߡ�
TOPIX -8 @2,253
����ʿ�� -141�� @31,626��
7��25��26���˳��Ť��줿��Ϣˮ�����Ծ�Ѱ����FOMC�ˤεĻ�Ͽ�ݤ�ȯɽ���줿��������ե�Ψ�������Ȥ��ƹ⤯��ϫƯ�Ծ��������ޤäƤ��ꡢ����ե���������뤿��ˤ��ɲ����夲��ɬ�פȤʤ��ǽ�����������줿�����������ơ���10ǯ��������������4.22%�椫������4.28%��ʺ�ǯ10�����ο��ˤؾ徺��������3�����ؿ���·�ä�2��³�����10ǯʪʪ��Ϣư�Ĥ������Ƽ¼�������1.95%��Ķ���ơ�2009ǯ8�����14ǯ�֤�ι���Ȥʤä���2022ǯ3���³���ƹ�����夲�Ϻǽ����̤����äƤ��롣���夲�ϸ�1���⤷������������Ǥ��ߤ�ȤʤäƤ��뤫�⤷��ʤ�������ե�Ψ�θ�®��ȿ�Ǥ��ʤ���2024ǯ�ˤ���������ž����ȤΥ��ʥꥪ��ޡ����åȤ������Ƥ��褿�����Τ褦��2024ǯ3��餤���������Υ����ߥȸ��Ƥ���������������Ƥ��줬2024ǯȾ�аʹߤ�������ˤʤꤽ���Ǥ���ȶ�����ʪ�Ծ�Ͽ�����Ϥ��
���ʵ�����Ԥ���ǰ����ޤ��桢�ƹ����³�������ơ����������ܳ����̤�³������ե������ȥ�ƥ���ʤ��Ϳ��������ơ�����ʿ�Ѥ������450�߰¤ޤDz���������礹����̤����ä�������꤬��䤹��ȡ��礭�������Ƥ�������ϥ�ؿ���ȿž�������Ȥ����ơ��ڤ��֤��Ʋ�������̾�������
���ٻԾ�Ǥϡ��ƹ��Ĺ�������徺��ȿ�Ǥ��Ʊ߰¡��ɥ�⤬�ʤߡ�����3���֤�8�ߤ�߰¥ɥ��Ȥʤ�1�ɥ��146����Ⱦ�ФȤʤä��������ܡ�����ʲ������뤫���ʤ����Ϻ�̳�ʤκ�̳�������ꤷ�������ñ�ˤ��������Ȥ������㤹������ˤα��㤤������ٲ����Ƽ�ư�֤ʤ�͢�д�Ϣ�����������ư���ϤۤȤ�ɤʤ��ä�����ǯ9��22�������ܡ������24ǯ�֤�˱��㤤���ɥ����λԾ������Ƨ���ڤä������λ��Υ졼�Ȥ�1�ɥ��145��90�����ä����ᡢ���Ϥ��IJ��������äƤ⤪�������ʤ��ȥޡ����åȤϿȹ����Ƥ��롣
7��28�������䤬Ĺû��������YYC�ˤν�����ȯɽ����ľ��ˤ�1�ɥ��138������ޤDZ߹⡦�ɥ�¤��ʤ���������θ�Ϥ�3���֤DZߤ�8�ߤⲼ��������ܤ�Ĺ�������ʡ�10ǯ�������ˤ�YCC�ν�������0.4%�椫�鸽�ߤ�0.6%��ؾ徺����������Ĺ������������ʾ�Υڡ����Ǿ徺���Ƥ��뤿�����Ƥζ�������3.6%���٤ȤʤꡢYCC������������礷�������줬���ε�®�ʱ߰¡��ɥ��μ�ʸ����Ǥ��ꡢ���Τ褦��2��֤λμ���Ψ�κ����Ѳ������إ졼�Ȥ�ư�����Ȥ����ͤ�����֥����åȡ����ץ������פȸƤ֡�
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ�Ĺ�����Ҥ�����������Ʊ�����ǽ��������������¤ä����������ƹ�����礭��³��ʤ��¤ꡢ����������ʿ�Ѥϼ�Χȿȯ�������㤤����Ԥ���Ϥ�������������������Ͽ����ʾ徺���λϤޤ�ǤϤʤ��������ޤǤ�������˲�ʤ��ȸ��Ƥ����٤����������ޤ��ϲ�������25����ưʿ�����ξ�˺����Ǥ��뤫�ɤ����Ǥ��롣
33�ȼ���23�ȼ郎������������Ψ�ȥå�5�ϡ���̩�����1�̡ˡ������2�̡ˡ�Ŵ�ݡ�3�̡ˡ��۶ȡ�4�̡ˡ��ѥ�ס����5�̡ˤȤʤä���
���������
�����̤��Ÿ���dz����������뭦����¤ʲ�����̡����꤬ǻ���� 08��16��
�������ƹ���������礭��ȿ�����DJIA -361.24 @34,946.39, NASDAQ -157.28 @13,631.05, S&P500 -51.86 @4,437.86�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�145����Ⱦ�Ф�������߰¿��Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤ϲ�����������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������360���Ф��ơ�������������1,425�Ȥʤä���ƭ��쥷����103.67%����ڥץ饤�����������3��1410���ߡ�
TOPIX -29 @2,261
����ʿ�� -472�� @31,767��
�����꼡�����кѻ�ɸ�ϸ��¤����λԾ�ͽ�ۤ�ꡢ�ʵ���ǰ����ޤäƤ��롣����̱��ԡ������ԡˤ�1ǯʪ������߽����١�MLF�˶�����������������ɤϼ���Ψ��ǯ���̥ǡ����θ�������ߤ����������ư����ҤηбĴ�����³���Ƥ��롣����ˡ��ƹ�Ǥ��ɹ��ʡ������̣�Ǥ϶�������������ץǡ�����ȯɽ��³���Ƥ��뤿���ƶ�ͻ����������̤�Ĺ��������ǰ���줿�����η�̡���Ĺ��������4.27%�ޤǾ徺������2022ǯ10�������10����֤�ˡ��ɤ��Ǥ�����褦�ˡ��ե��å����졼�ƥ�������ƶ��ޤ�70�ʾ�γʲ������ǽ�����������CNBC�ǽҤ٤����ᡢ��Գ������¤�����Ʋ�����������Ԥǹ�������KBW�ʥ����å���Գ��ؿ���2.7%�¤Ȥʤä�������3�����ؿ���·�ä��礭��ȿ�����
�ƹ����ȿ�������ơ����������ܳ����̤ϲ�����������¿���ä����ä˥ե��å����졼�ƥ��ˤ������Ԥ�ޤ�70�ʾ���ƶ�γʲ������ǽ���μ����ˤ�����ܤζ�Գ������줿�����ηʵ���Ԥ��¤�����ơ�����ϥ�ؿ���Ϥ���Ȥ��륢���������̤���Ĵ�ȤʤꡢTDK���ե��ʥå��������ŵ��ʤ�����Ϣ���ΰ�Ѥ����줿������ˡ����ʵ����¤�ȿ�Ǥ��ơ��������ʤ���������������ú���ȹ۶ȳ��������羦�ҳ����Ʋ������������Ŵ�ݳ�������
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ�����ʿ�Ѥ�472�߰¤Ȥʤꡢ6��9�������Ȥ��������β��¤�ȴ���������ͤȰ��ͤ��ڤ겼���ʤ��顢2��ŷ�桦3��ŷ���ŷ����դ������Ȥ��ե���������ˤ�������Ƥ��롣10����ưʿ������25����ưʿ�����Ͼ��������鶦�˲������Ǥ��ꡢ��ġ��ޤ��������60����ưʿ�����β��˳����ϴ��������߹��������³����ȿȯ���ʤ��¤ꡢ���Τޤ��Ф��ǿ�ܤ����Ȥ��Ƥ�䤬��60����ưʿ�����Ⲽ������ž���ơ������������뭦����¤ʲ�����̡�����Ʋ�����줬��®���롣���θ�Ϥ������ٲ������ȿȯ���뤬������Ϥ����ޤǤ�����פǤ��ꡢ���Ū�˲�������25����ưʿ�����ξ�˺���夷���Ȥ��Ƥ�ޤ�ľ���˲������ǽ�����⤤������������㤤�̤�û������Ȥ��뤳�Ȥ��������Ȼפ���
33�ȼ���30�ȼ郎������������Ψ�ȥå�5�ϡ���������ú��1�̡ˡ������2�̡ˡ�Ŵ�ݡ�3�̡ˡ���ԡ�4�̡ˡ��۶ȡ�5�̡ˤȤʤä���
���������
GDPǯΨ6.0%����ȤƤߤ�ȡ����� 08��15��
�������ƹ�������Ͼ夲����DJIA +26.23 @35,307.63, NASDAQ +143.48 @13,788.33, S&P500 +25.67 @4,489.72�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�145����Ⱦ�Ф�������߰¿��Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤Ͼ夲��������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������1,061���Ф��ơ�������������715�Ȥʤä���ƭ��쥷����112.23%����ڥץ饤�����������3��675���ߡ�
TOPIX +9 @2,290
����ʿ�� +179�� @32,239��
�ƺķ��Ծ��Ĺ�����������4.21%�ޤǾ夲���ʺ�ǯ11�����ˤ���ȾƳ�γ����㤤ľ����ƥե���ǥ�ե���ȾƳ�γ��ؿ���SOX�ؿ��ˤ�2.87%�������ȿȯ����������3�����ؿ���·�äƾ夲����
���������ܳ����̤⡢ȾƳ�δ�Ϣ������ϥ��ƥ����������������Τ��夲��������դ�����ȯɽ���줿2023ǯ4~6����μ¼�������������GDP�ˤ�������6.0%����ǯΨ����������Ĵ���ѤߡˤȤʤä���ǯΨ6����Ĺ�ȸ����Τ�1980ǯ���Ⱦ�ΥХ֥�кѴ��¤ߤʤΤǶä����������������Ƥ�褯���Ƹ���ȡ��ο��θĿ;���Ϥष�������������Ƥ�����GDP�徺Ψ���⤯�ʤä���ʸ����ϳ����ν����äǤ��ꡢ������ˤϥ���Х���ɼ��פ����ä�͢���θ�����ץ饹�װ��Ȥ������äƤ��롣����ι�ԼԤ����ܹ���Ǥξ����GDP�����͢�ФȤ��ƥ�����Ȥ���������͢���θ�����GDP�β����夲�װ��Ȥʤ롣�߰¡��ɥ�������͢�д�Ϣ�����ΰ�Ѥ����줿������ʿ�Ѥξ夲���ϰ��340�ߤ�Ķ������¾�������ʵ�����Ԥ���Ʃ��������Ĺ�������ξ徺�����ܳ��νŤ��Ȥʤä���
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ�����10���ڤ�25����ưʿ�����ϲ�������ž���Ƥ��뤬�������ϲ�������10����ưʿ�������ޤ��������60����ưʿ������夫�鲼���ͤ�ȴ���ĤĤ��롣32,000�ߤβ��ͻٻ����ζ��������롣
33�ȼ���24�ȼ郎�夲�����徺Ψ�ȥå�5�ϡ�������1�̡ˡ�Ŵ�ݡ�2�̡ˡ�����¾��ͻ��3�̡ˡ��ݸ���4�̡ˡ������̿���5�̡ˤȤʤä���
���������
�����������뭦����¤ʲ�����̡ˤο��٤����ޤꤽ������������ 08��14��
�轵���������ƹ�������Ϲ�¤ޤ��ޤ��Ȥʤä���DJIA +105.25 @35,281.40, NASDAQ -93.14 @13,644.85, S&P500 -4.78 @4,464.05�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�144�����Ⱦ��������߰¿��Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤ϲ�����������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������621���Ф��ơ�������������1,167�Ȥʤä���ƭ��쥷����106.28%����ڥץ饤�����������3��6668���ߡ�
TOPIX -23 @2,281
����ʿ�� -414�� @32,060��
7����Ʋ���ʪ���ؿ���PPI�ˤ���ǯƱ�����0.8%�徺�����ʡ�Ծ�ͽ��0.7��ˤ��ᡢ��Ϣˮ���������������FRB�ˤ��ޤ��ɲ����夲��;�Ϥ��Ĥꡢ��Ĺ�������ʡ�10ǯʪ��������ˤ�4.15%�ޤǾ徺������¾�����ߥ�������ؤ�ȯɽ����8��δ��ԥ���ե�Ψ����������㲼�������кѻ�ɸ�����庮���ä����Ȥ�ȿ�Ǥ��ơ��������ȳ�30��ʿ�ѤϾ夲���������ʥ����å��ϲ�������
��Ĺ�������ξ徺������ơ����������ܳ����礭��������������Ǥ�1�ɥ��145����ޤDZ߰¡��ɥ�⤬�ʤ�����Ȥ���������ʿ�Ѥϰ���ץ饹�Ȥʤä��������θ塢����ʿ�Ѥϰ��440�߰¤ޤDz�����������Ķ������徺�������0.620%�ޤǾ夲�����ե���ǥ�ե���ȾƳ�γ��ؿ���2%�¤Ȥʤä����Ȥ˲ä��ơ�Ĺ�������ξ徺���Ҵ���ȾƳ�δ�Ϣ������Ϥ���Ȥ��������Ĺ��������Ƴ����ؿ������������ޤ����ʵ�����Ԥ��¤�ȿ�Ǥ����峤����ؿ��ȹ���ϥ�β��������ܳ��ν��ФȤʤä������ߵ٤ߤǻԾ컲�üԤ����ʤ��ʤäƤ��뤿����ư�����礭������䤹����ɴ��Ź����Ŵ�ʤɥ���Х���ɴ�Ϣ�������������ư�����ä���
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ��轵��������������ۤܤ��٤ơ������α������Ǥ��ä��������Ͼ������60����ưʿ�����β������߹���������˲�������10����ưʿ��������Ӳ�������25����ưʿ�Ѥβ��˴��������߹���Ǥ��ꡢ�����ߡ������������뭦����¤ʲ�����̡ˤ����äƤ��롣��������ˤޤ�60����ưʿ�����ξ�˺����Ǥ�����ɤ��������Τޤ��Ф���³�������Ǥ⡢�����������뭦�ο��٤����ޤꡢ���Ԥ��Ϥޤ��ޤ��Ť��ʤäƤ�����
33�ȼ���29�ȼ郎������������Ψ�ȥå�5�ϡ��۶ȡ�1�̡ˡ���ư����2�̡ˡ�������3�̡ˡ��ŵ������4�̡ˡ��������ʡ�5�̡ˤȤʤä���
���������
��������γ����ȥ졼�ɵ����ٶ���: ��20��ǯ��ޤ��ޤ��������� 08��12��
����������γ����ȥ졼�ɵ����ٶ��� �����ȥ졼�ɤιͤ���������������������ηϤ�ؤӡ�����롼����ۤ����
�������1�����鳫�ϤǤ�����64����Ⱦǯ���2����ܡ����ܤ�ͽ��Ǥ���
63����2023ǯ8��12�����ڡˡ�13�������ˡ�19�����ڡˡ�20��������
���������� ���1��������6���ޤ�
���������� ����9��������2��Ⱦ�ޤ�
��ꡧ ����饤���Zoom�� �� ���֤��Թ�ˤ��ꥢ�륿����ǻ��äǤ��ʤ��ͤϡ�����������ˤϹֵ�ư������������ɤǤ��ޤ���
�Գ�����ȥ졼������롼�빽���ٶ���� �� �ʤ������ȥ졼�ɤ����ޤ��Ǥ��ʤ��Τ����� �����ϡ��ʤ����ɤΤ褦�ˤɤ��ޤǾ夬�ꡢ�ޤ��ϲ�����Τ������Ƥ��ʤ�����Ǥ��롣�ʤ��Τ�ʤ��Τ��������������ʸ�����§�ˤ����Ф��Τ�ʤ�����Ǥ����� ���������Ф��ΤäƤ��Ƥ�¹ԤǤ��ʤ��Τϲ��Τ����� ���η�����������Ǥ��� �� �ǤϤɤ���äƷ���������ɤ��Τ��� �� ���������ɤ������ɤ��Τ�ʬ����ʤ����� �����кѡ��ӥ��ͥ���ư�����ɤ������Τ�ʤ�����Ǥ��� �� ����餹�٤Ƥ��η�Ū�˿����˳ؤ֤Τ������ٶ������Ū�Ǥ�����ǯ���Ԥ������ԡ����Ԥ��ܻؤ�����ιͤ����ȼ���ˡ
������ȥ졼�ɤˤ����Ф����������ʤ���Фʤ�ʤ�����̤˽���ʱƶ���Ϳ���뤴���鷺���ʼ�����μ���������Ǥ����Vital Few X�ɤȡ��ΤäƤ��Ƥ��Τ�ʤ��Ƥ��̤ˤ��礷�Ʊƶ���Ϳ���ʤ�����¾¿���ο����μ���������Ǥ����Trivial Many�ɤ�����ޤ������������ٶ���Ǥϡ�Vital Few X�ɡ��äˡ����������ʸ�������§�ˡפȡ��������Сפ˾��������ƤƳؤӤޤ���
���������
��������25����ưʿ�Ѥ�32,000�ߤβ��ͻٻ����Ȥι����� 08��10��
�������ƹ��������³�����DJIA -191.13 @35,123.36, NASDAQ -162.30 @13,722.02, S&P500 -31.67 @4.467.71�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�144���������������߰¿��Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤Ͼ夲��������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������1,340���Ф��ơ�������������441�Ȥʤä���ƭ��쥷���� 103.37%����ڥץ饤�����������4��1415���ߡ�
TOPIX +21 @2,304
����ʿ�� +269 @32,474��
7����ƾ����ʪ���ؿ���CPI�ˤ�ȯɽ�������˹����Ƥ��뤿���ͻҸ��ࡼ�ɤ������桢�����ܤ������ؤ����������ʤȶ����������ƻ���줿���⤷����CPI���Ծ�ͽ�ۤ���忶�줹�����Ϣˮ���������������FRB�ˤ��ɲ����夲���ǽ������ޤꡢ�����㤪���Ȥ������ߤ����ह�롣���ϤΥϥ��ƥ��������濴����꤬ͥ���Ȥʤꡢ����3�����ؿ���·�ä�2��³�����
�ƹ���¤�����ơ����������ܳ����̤ϲ����ƻϤޤä������ڤ��֤��ƾ夲��������¿���ä�������ʿ�Ѥϰ��200�߶����������ȶ��Ӥβ������ԤϺ�������������β��¤Ǥ���32,000���դ�ϲ��ͻٻ����Ȥ��ƶ����ռ�����Ƥ��뤿�ᡢ�����ض�Ť��ȶ����������㤤�����롣�߰¡��ɥ�⤬�ʤߡ������������ܤ����ܤؤ�����ι�Ԥζػߤ����������ˤǤ��뤳�Ȥ���ƻ���졢��ư�ִ�Ϣ�����������Ŵƻ��ɴ��Ź�ʤɥ���Х���ɴ�Ϣ���������줿��8�����������ι�Ԥ��Ƴ������С�23ǯ���ˬ�����ͤ�447���ͤȻ���졢�����ΤޤޤȲ��ꤷ��������198�������ä���ȴ��Ԥ���롣¾�����ʥ����å��¤�ή�������ơ�������쥯�ȥ���䥢�ɥХ�ƥ��Ȥʤ�ȾƳ�γ���Ϣ���������줿��
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ�����ФǾ������60����ưʿ�����β����礭�����߹���������ͤǤϤ��ξ�˿ɤ�����α�ޤä���60����ưʿ�����β������߹�����ޤޤˤʤ餤�¤ꡢ�����������뭦����¤ʲ�����̡ˤȤϤʤ�ʤ�������������ǤĤʤ��äƤ���褦�ʾ��֤Ǥ��롣���Τ˱�������Ȥʤä�25����ưʿ������32,000������Υ�����β��¡ʡ�ͻٻ����ˤȤι�����Ǥ��롣�ɤ��餬�ǽ�Ū�˾��Ĥ��������طʤ��Ѳ�����Ǥ��롣
33�ȼ���30�ȼ郎�夲�����徺Ψ�ȥå�5�ϡ��۶ȡ�1�̡ˡ���������ú��2�̡ˡ��ѥ�ס����3�̡ˡ���ư����4�̡ˡ�͢���ѵ����5�̡ˤȤʤä���
���������
�����������뭦����¤ʲ�����̡ˤ�����ĤĤ��� 08��09��
�������ƹ��������ȿ�����DJIA -158.64 @35,314.49, NASDAQ -110.08 @13,884.32, S&P500 -19.06 @4,499.38�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�143������Ⱦ��������߹���Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤ϲ���������ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������763���Ф��ơ�������������1,004�Ȥʤä���ƭ��쥷����97.06%����ڥץ饤�����������3��8471���ߡ�
TOPIX -9 @2,283
����ʿ�� -173�� @32,204��
���դ���ҤΥࡼ�ǥ�������M&T�Хʤɰ����϶���γ��դ�������������Х����֡��˥塼�衼���������ȥ��ơ��ȡ����ȥ�Ȥʤɰ�������Ԥγ��դ�����������Ǹ�ľ����ȯɽ�������ե�����ɤˤ����Ĵã�����Ȥ����á���ͻ���ɤˤ����ܵ����ζ�����Ĺ�������徺�����Ǥϻ��ͤ�ɾ���ۤϲ����ꡢ�ä˾�����ư������ͻ��ǤϿ��ѥꥹ���ι�ޤ��ä�뤳�Ȥʤɤ���ͳ�Ȥ��Ƶ�줿�������������ƹ���ϲ��������3�����ؿ���·�äƲ�������
�ƹ����ȿ�������ơ����������ܳ����̤Ⲽ�������äˡ��ƶ���β����������ƥᥬ�Х�����Ω�äƲ�����������ʿ�Ѥβ������ϰ��200��Ķ�Ȥʤä������������ܻԾ�ϵپ�Ȥʤ뤿�ᡢ������������Ū����꤬¿���Ф��ȸ����롣8��10���ˤϡ�FRB�ζ�ͻ����������礭�ʱƶ���Ϳ����ȹͤ������ƾ����ʪ���ؿ���CPI�ˤ�ȯɽ����롣��ǯ�����������濴�ˤ��줫��Ƶ��ٲˤ����뤿��Ծ컲�üԤ��������뤳�ȤǡֲƸϤ����פȤʤ��礬¿����
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ������ǽ������ƤӾ������60����ưʿ�����β������߹���������ߤΥ�����β��¤Ǥ���32,000�ߤϤޤ����ͻٻ����Ȥ��Ƶ�ǽ���Ƥ��뤬�������������뭦����¤ʲ�����̡�����������γ����ȥ졼�ɵ��� �����ԡ�210�ڡ����ˤ�����ĤĤ��롣
33�ȼ���21�ȼ郎������������Ψ�ȥå�5�ϡ��۶ȡ�1�̡ˡ��������ʡ�2�̡ˡ�������3�̡ˡ���ԡ�4�̡ˡ��ڷ���5�̡ˤȤʤä���
���������
6����ܰʹߤ������ͤȰ��ͤϽ������ڤ겼���äƤ��� 08��09��
�������ƹ���������礭��ȿȯ������DJIA +407.51 @35,473.13, NASDAQ +85.16 @13,994.40, S&P500 +40.41 @4,518.44�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�143������Ⱦ��������߰¿��Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤Ͼ夲���������������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������993���Ф��ơ�������������772�Ȥʤä���ƭ��쥷����95.78%����ڥץ饤�����������3��6710���ߡ�
TOPIX +8 @2,292
����ʿ�� +123�� @32,377��
�˥塼�衼��Ϣ��Υ����ꥢ�ॺ���ۤ�ʪ���ξ徺Ψ���߲��������Ϣˮ���������������FRB�ˤ���ǯ�ˤ��������Ϥ����ǽ��������Ȥθ������������������ƹ����ȿȯ���Ƽ���3�����ؿ���·�äƾ夲����
�ƹ����ȿȯ�ȡ�����˱߰¡��ɥ���ư��������ơ����������ܳ����̤Ͼ夲��������ʿ�Ѥξ夲���ϰ��280�ߤ�Ķ����������������Ԥ�����갵�Ϥ��������ͤǤ�����ᤵ�줿�����Ǥϳ���������Ω�ä�����Ƥ��뤬������϶��Ӹ��̤����ɤ�����ǤϤʤ������ҳ��㤤�ˤ�����Ը�������ư���Ǥ��롣
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ��������60����ưʿ�����ξ�˺���夷�����������岼�ˤҤ��������û�����ǽ������϶����夲���������ǤϤʤ���6����ܰʹߤ������ͤȰ��ͤϽ������ڤ겼���äƤ��ꡢ�⤷7��12������@31,791�ߤ������ȡ�̾�¤Ȥ�˲��ߥȥ��ɷ����Ȥʤ롣���ߡ�������β��¤�Ƨ�ߤޤ��塢ȿȯ���Ƥ��뤬�����Ȥ�1���ְ���˲�������ž����25����ưʿ�����ξ�˺���夷�Ƥ�8��1����������@33,488�ߤ����Τ˾�ȴ������ʤ������Ū�˼嵤������ꤷ�����Ǥ��롣
33�ȼ���25�ȼ郎�夲�����徺Ψ�ȥå�5�ϡ��ŵ���������1�̡ˡ�������2�̡ˡ������ʡ�3�̡ˡ���ư����4�̡ˡ��������ʡ�5�̡ˤȤʤä���
���������
������β���@32,000���դ�ǥ��ꥮ��ȿȯ 08��08��
�轵���������ƹ�������ϲ�������DJIA -150.27 @35,065.62, NASDAQ -50.48 @13,909.24, S&P500 -23.86 @4,478.03�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�142����Ⱦ�Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤Ͼ夲��������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������1,315���Ф��ơ�������������474�Ȥʤä���ƭ��쥷����100.14%����ڥץ饤�����������3��4327���ߡ�
TOPIX +9 @2,284
����ʿ�� +62�� @32,255��
�轵��������ȯɽ���줿7����Ƹ������פ������ȼ�������ѼԿ���NFP�ˤ��Ծ�ͽ�ۤ�����äȤʤä���ΤΡ�����Ψ�����������¶�ο���ͽ�ۤ���ä������Τ��ᡢFRB�ˤ�뺣��ζ�ͻ���������夲�Ǥ��ߤ�ʤΤ��������Ϥޤ��ٲ����Ƥ����ɲ����夲������Τ��ˤĤ�����Ʃ�����⤯�ʤꡢ�������ν��ФȤʤä�������3�����ؿ���·�ä�³�����
���������ܳ����̤ϡ��ƹ���¤�����Ʋ����ƻϤޤä�������ʿ�Ѥ�����Dz�������300��Ķ�˳��礹������̤����ä�������������Ĵ�ʹ����ȶ��Ӥȱ߹⡦�ɥ�¤ؤ�ư������٤ߤ������Ȥ������㤤ͥ����ž������Χȿȯ�������㤤��������������ʿ�Ѥϼ�����ڤ��֤��������ǽ�������Ω���������Ƴ����ؿ���ʪ����Ĵ�˿�ܤ��Ƥ������Ȥ����ܳ����٤����������������ϤΥϥ��ƥ������ζ��Ӥ��㤨�ʤ����ᡢ��³�����϶���ȿȯ�������˸����롣���������ζ�ͻ��������Ǥ��������Ρּ�ʰո��פ��ɽ������Ĺû��������YCC�ˤˤĤ��Ƥϡֽ����Ĥİݻ����Ƥ���ɬ�פ�����
�פȽҤ٤Ƥ��ꡢ����ˤ����¤���³�����ȥޡ����åȤ��ռ��������Ȥ�������٤�������
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ�����åץ����ƻϤޤä����ڤ��֤���Ĺ�����������澮����ǽ��������轵��������³��2��Ϣ³�����Ȥʤ겼���¤�������������ޤ��������60����ưʿ���������ΤˤϾ�ȴ���Ƥ��ʤ����ޤ������ͻٻ����Ǥ���32,000���դ�ǥ��ꥮ�겼���ߤޤꡢ�����ΤȤ����Ͼ���ȿȯ���������⤦����礭�ʰ����������ӽФ��Ƥ���в�ȴ���������ʰ��֤Ǥ��롣������β��¤Ǽ�Χȿȯ�������㤤�Ȥ�����ѤϽ�ʬ�����������ȴ���Υꥹ���ˤϿ��ȷ��̤ν����Ƥ���ɬ�פ����롣
33�ȼ���23�ȼ郎�夲�����徺Ψ�ȥå�5�ϡ��建�����ӡ�1�̡ˡ������ʡ�2�̡ˡ��������ʡ�3�̡ˡ���̩�����4�̡ˡ���������ú��5�̡ˤȤʤä���
���������
���������פDz����ߤޤä� 08��04��
�������ƹ�������Ͼ���³�����DJIA -66.63 @35,215.89, NASDAQ -13.73 @13,959.72, S&P500 -11.50 @4,501.89�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�141����Ⱦ�ФǤ�ư�����ä������������ܳ����̤�ȿȯ����������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������1,044���Ф��ơ�������������707�Ȥʤä���ƭ��쥷����94.46%����ڥץ饤�����������3��7196���ߡ�
TOPIX +6 @2,275
����ʿ�� +33�� @32,193��
7����Ƹ������פ�ȯɽ�������˹������桢��10ǯ������꤬��ǯ11������4.18%��ؾ徺�������Ȥdz�������³�������3�����ؿ���·�äƲ�������
���������ܳ����̤ϼ�Χȿȯ�����β������㤤�����ꡢȿȯ����������¿���ä����ƹ�Ĺ�������ξ徺�����ܤ�Ĺ�������ξ徺���Ϥ������������ʿ�Ѥβ������ϰ��200�ߤ�Ķ����32,000�������������������������Dz���������礹���û���ڤ���Ԥ�����äƤ�����ʪ���㤤�ᤷ�Ϥ���ȤDz����ߤޤä�����������ڤ���PBR�������������ͻ������������³�����Ȥ�����¬���㤤³���Ƥ��������إå��ե���ɤ��㤤�ݥ������������Ƥ��ꡢ5���ܤ���6����ܤޤǤΤ褦�ʾ徺�����̴��Խ���ʤ���
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ����ߤΥ�����β��¤Ǥ���32,000�����Фdz�������������θ��ڤ��֤��������ǽ������������η��Ȥ��Ƥϡ�������Ϣ³�Dz������褿�����������Ȥʤä���Τ������α����μ�����ʬ�ˤۤ�ξ�������������������������פǤ��ꡢȿȯ�ϤϤޤ��夤�ȸ����롣����ˡ�10���ڤ�25����ưʿ���������Ǥʤ��������60����ưʿ�����β������߹�����褿���ᡢ���60���֤���ä��ͤ�ʿ�ѥ����Ȥ������Ǥ��롢�Ĥޤꡢ���60���֤���ä��ͤ�����ʿ�ѷ��Υݡ��ȥե��ꥪ�ʤ�ۤ������ޤ�»�ȤʤäƤ��롣�⤷��32,000�ߤβ��ͻٻ��������Τ˳�����褦���ȡ��������åȤ���꤬��������Ϥ������������ï���ɤ�����㤤������������Dz����ߤޤ뤫�������ϲ����줹�뤫����ޤ롣
33�ȼ���17�ȼ郎�夲�����徺Ψ�ȥå�5�ϡ�������1�̡ˡ��建�����ӡ�2�̡ˡ��ݸ���3�̡ˡ��۶ȡ�4�̡ˡ���ԡ�5�̡ˤȤʤä���
���������
�ƹ�ijʲ�������å���³����2011ǯ8��Ȥ���ӡ� 08��04��
�������ƹ�������ϲ�������DJIA -348.16 @35,282.52, NASDAQ -310.46 @13,973.45, S&P500 -63.34 @4,513.39�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�143����Ⱦ�Ф�������߰¿��Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤�³�������ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������158���Ф��ơ�������������1,666�Ȥʤä���ƭ��쥷����92.08%����ڥץ饤�����������4��3391���ߡ�
TOPIX -33 @2,268
����ʿ�� -548�� @32,159��
8��1���˥ե��å����졼�ƥ����ƹ�γ��߷���Ĺ����̳�γ��դ���AAA����AA+�˰���������;�Ȥ�³���Ƥ��롣��Ĺ���������ϰ��4.12%�ޤǾ徺���ƺ�ǯ11��9������ι���Ȥʤä�������3�����ؿ����礭����������
�ƹ�������β��������ơ����������ܳ����̤�³���������ʿ�Ѥ�����³��Ȥʤ겼�����ϰ��500�ߤ�Ķ�������ե���ǥ�ե���ȾƳ�γ��ؿ���SOX�ˤ�4%�¡ʺ�ǯ����β���Ψ�ˤȤʤä����ᡢ������쥯�ȥ���䥢�ɥХ�ƥ��Ȥϰ��3%��������TDK��10%�Ⲽ��������ڥץ饤��Ǥϡ�ǯ���������������81�Ȥʤä�������Ǥⳤ�����ϵչԹ�Ȥʤä������ܳ���5�����¾��γ���������٤ƾ徺���Ƥ�������ˡ���ġ�ήư�����⤤����ˡ����׳���Τ��������䤹���������û���ڤ������˾�ä���ʪ��Ƴ�����ųݤ��Ƥ����ǽ�����⤤��
�����13�����ư���������ι���㤤���ڤ�»ܤ���Ĺ�������ξ徺�˻��ߤ���褦�Ȥ��������θ��̤����ꡢ���ٻԾ�Ǥϱ߰¡��ɥ��Ȥʤä���������ƹ�ijʲ�������å��ˤ����㤬���롣2011ǯ��S��P���ƹ�ij��դ���AAA����AA+�˰������������Ȥ����ä����dz������礭��Ĵ�����������λ���8���֤�����ʿ�Ѥ�9%�������9833�ߢ�8955�ߡˡ�����γ����������ƤϤ�����3,000�ߤβ����ˤʤ롣�Ĥޤꡢ30,500�����٤ޤDz�������ˤʤ롣�ʲ����ˤ�ꡢ����ʤ�ķ�������������ʡ�Ĺ�������ˤϾ徺����Ϥ����ä�����ǫ�����ķ��㤤����������Ĺ�������ϲ����������η�̡����ٻԾ�Ǥϱ߹⡦�ɥ�¤��ʤ�����ܳ��β������®������������Ф��ơ�����γʲ�������å��Ǥϡ����ΤȤ����߹⡦�ɥ�¤ȤϤʤäƤ��ʤ�ʬ�����ʲ�������å��Υ���ѥ��Ȥϼ夯�ʤ�Ȥ����Τ�����Ū�ʿ�����������������ɬ���������Ū��ư���櫓�ǤϤʤ��Τ����Ƕ�ʪ�Ǥ��롣
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ�2��Ϣ³���������Ƶ���ơ����á�����ߡפȤʤä���32,000���դ꤬���ͻٻ����Ȥ��ưռ�����������β��¤Ǥ��뤬�������ޤǤ��Ⱦ����Ǥ��롣�⤷��32,000�ߤΥ�β��¤���ȴ�����Ʋ�����ȡ����٤�32,000�ߤ������������Ѥ�ꡢ���ͤ��ޤ���¦����䤬�Ѥ�롣
33�ȼ��桢�����ȥѥ�ס����2�ȼ�����31�ȼ郎������������Ψ�ȥå�5�ϡ���Ŵ��°��1�̡ˡ�͢���ѵ����2�̡ˡ��������ʡ�3�̡ˡ��۶ȡ�4�̡ˡ��ݸ���5�̡ˤȤʤä���
���������
���ƹ�ij��դ��ʲ�������å��פdz����Ϥۤ����̰� 08��03��
�������ƹ�������Ϲ�¤ޤ��ޤ��Ȥʤä���DJIA +71.15 @35,630.68, NASDAQ -62.18 @14,283.91, S&P500 -12.23 @4,576.73�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�142�����Ⱦ��������߰¿��Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤�ȿ�������ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������287���Ф��ơ�������������1,503�Ȥʤä���ƭ��쥷����106.19%����ڥץ饤�����������4��4846���ߡ�
TOPIX -36 @2,302
����ʿ�� -769�� @32,808��
7����Ƹ������פ�ȯɽ�����ͻҸ��ࡼ�ɤ�����Ū�Ȥʤä������������Ω�ķкѻ�ɸ�������Ƽ夤��̤Ȥʤä��Τ�FRB�ˤ���ɲ����夲�β�ǽ�����㤯�ʤꡢĹ�������ϲ�����Ϥ��ʤΤ������ºݤˤ���10ǯ������꤬4.029%��+0.072%�˾夬�ä����������ȳ�30��ʿ�ѤϾ夲������Ĺ�������ξ徺���Ҵ��ʥʥ����å��ϲ�������
���ܻ��֤�ī���������դ���ҥե��å����졼�ƥ����ƹ��Ĺ�����߷���ȯ���γ��դ���Ǿ���AAA�����1�����AA+�ذ������������ƹ�Ĺ�������ξ徺�����Ǥʤ������ܤ�Ĺ����������0.625���2014ǯ4�����ˤؾ徺������YCC���Ѥν������ꤵ�줿����Ĺ��������1.0%�ޤǾ徺�����뤿�ᡢĹ�����������Ѥ���ޤ�䤹�������Ả�ˤ�1�ɥ��143��30����ޤDZ߰¡��ɥ�⤬�ʤ�Ǥ��������ꥹ��������줫��ꥹ�����������ڤ��ؤ�ä��Ȥδ�����������Ǥ���ߤ��㤤���߹⡦�ɥ���������ɤ��ᤵ�줿��¾���������Ǥ���������줿��
�ʥ����å��β����ή��˲ä��ơ�Ĺ�������ξ徺�ˤ����������������礭����������Ĺ����������쥯�ȥ���䥢�ɥХ�ƥ��Ȥʤɡˤ��濴�����������ʿ�Ѥϵ����������ʿ�Ѥβ������ϰ��800�ߤ�Ķ����������2���֤ξ徺��717�ߤ�1����Ģ�ä��ˤ������������軻���Ƥ��ɤ��ä��ȥ西�ϵչԹ�Ȥʤä���¾�����軻���Ƥ��Ծ�ͽ�۰ʲ����ä���¼HD��9%�¡ˤ䥳�˥��ߥΥ륿�ʰ��10%�¡ˤϵ������
�����Ǥ���8�����ܤˤ����Ƴ��������ٲˤ�����ΤǡֲƸϤ����פȤʤ�פ��Ȥ����ء����¤�¥�������������ӽФ����褿�����������ޡ����åȤ�ȿ�����Ҵ������롣�ʤ��ʤ��ƹ����ܤι�ĤϤۤȤ�ɤ��٤��ƥɥ���Ƥǡ�����ʳ����̲ߤ�ȯ�ԤϤۤܤʤ����ʲ����ˤ���ƹ�Ĥ���餶������ʤ����ȡ������ͭ�Ԥ�¸�ߤ��ʤ����������äơ���ͻ�Ծ�ؤαƶ��ϸ���Ū�Ǥ��뤫��Ǥ��롣
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ�7��31���˶��������Ĺ�籢����������ᡢ��ġ�25����ưʿ����10����ưʿ�����Ⲽȴ�����������7��3���ΥХ֥��������������@33,753�ߤι����Ϥ���˱�Τ��������ƹ�ij��դ��ʲ�������å��פ��ƹ������줬���줫��ɤΤ褦�˲�ᤷ���ɤΤ褦��ȿ�����뤫����ǡ����ܳ������˰��ʲ����뤫�����������뤫����ޤ�Ϥ�����
33�ȼ��桢�۶Ȥ�͢���ѵ�������31�ȼ郎������������Ψ�ȥå�5�ϡ��ڷ���1�̡ˡ��ݸ���2�̡ˡ��ŵ���������3�̡ˡ���̩�����4�̡ˡ�������5�̡ˤȤʤä���
���������
���㡼�ȡ���ǥ��ȷ���ˡ��Ϣư�Ȥ���ȯ�ۤ� 08��02��
�������ƹ��������³�����DJIA +100.24 @35,559.53, NASDAQ +29.36 @14,346.02, S&P500 +6.73 @4,588.96�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�142�����Ⱦ��������߰¿��Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤Ͼ徺����������¿���ä�����ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������1,064���Ф��ơ�������������710�Ȥʤä���ƭ��쥷����110.46%����ڥץ饤�����������4��3076���ߡ�
TOPIX +15 @2,337
����ʿ�� +304�� @33,477��
�ƹ�Ǥ����夲��³��¬�θ�����طʤ˳�������³����������3�����ؿ���·�äƾ夲�����������ȳ�30��ʿ�Ѥ��轵26���ޤ�13Ϣƭ��Ͽ������������������Ĵ����ޤ��徺������
�ƹ�����ή�������ơ����������ܳ����̤Ͼ夲��������쥯�ȥ���䥢�ɥХ�ƥ��Ȥʤɤ��ͤ��������濴�����������ʿ�Ѥ�³�����������ٻԾ�DZ߰¡��ɥ�⤬�ʤ�����Ȥǥȥ西���������ۥ���ʤ�͢�д�Ϣ���������줿���ä˥ȥ西��1�ߤα߰¤�450���ߤ����פ����ä���ۤɰ��ش�ư�٤��⤤��ȯɽ���줿�Ф����4��6�����Ⱦ���軻�Ǥ�Ϣ������פ���ǯ��Ʊ����78������1��3113���ߤȤʤꡢͽ�ۤ���ä����ޤ����轵ȯɽ���줿�����Ĺû��������YCC�ˤα��ѽ��Ͼ����������絬�϶�ͻ���¤νи��ˤϤޤ��ۤɱȲ�ᤵ��Ʊ߰¡��ɥ����ɤ���ä���
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ�������Ĺ����Ҥ����ȴ����������2��³�������������ʤ��7��3���ΥХ֥��������������@33,753�ߤ�������Υ�����äƤ������쵤�˾�ȴ�����ƥХ֥�������������ͤ����뤫���������Ƥ��֤���ƥ��֥�ȥåפʤ�̥ȥ�ץ�ȥåפ�������뤫��
�ɤ�ʤ����̤�̤���ͽ�ۤ��Ƥ�������뤫����뤫�Τɤ��餫�פǤ��뤳�Ȥϡֳμ¡פǤ��롣�����餽�Ρֳμ¤˵��뤳�Ȥ�����פ���ѤȤ����롼�����Ƥ�������������롼��˽���ø���ȼ¹Ԥ���ΤߤǤ��롣���Τ褦�ʻͤ����㡼�ȡ���ǥ��ȷ���ˡ��Ϣư�Ȥ���ȯ�ۤؤȤĤʤ��롣��������ڤˤ��뤿��ˤϡ�������������٤�夲��ɬ�פ����롣�������äơ����㡼�ȡ���ǥ�����������ȷ���ˡ�ϼ�����Ӥ��Ƥ������������䤹�����Ȥ������ȤϤ����ˤ��Ƥ�꾡���䤹����������뤫�Ȥ����䤤��Ω�ơ����β������Ȥ����ˤ��٤����ȤǤ��롣����Ū��ĵ�ǼŪ�˹ͤ���Ȱ�ĤΥ롼��ؤȼ�«���Ƥ��롣���Υ롼��ؤ��ɤ��夤�����ϥХå��ƥ��ȤǸ��ڤ��롣�����ͭ��������ʬ�⤤�ȳο����褿�顢ø���ȼ¹Ԥ���ΤߤǤ��롣��ɡ�����롼��ϡ�1����ά����2����ѡ���3����Ʈˡ��3�ĤΥ��ơ����ࡼ���˷Ҥ����Ȥ����פǤ��롣�����Ƽ�ʬ�δֹ礤�˳��������ӹ���Ǥ���ޤǿ��������Ԥ�����������롼��δ����ͤϤɤ��ǯ�Ǥ⽽ʬ�⤯���Ƹ������⤤���Ȥ�����롼��ȸ�����ɬ���Ǥ��ꡢ����������γ����ȥ졼�ɵ��ѡפγ˿���ʬ�Ǥ��롣
33�ȼ���29�ȼ郎�夲�����徺Ψ�ȥå�5�ϡ��ŵ���������1�̡ˡ�������2�̡ˡ�͢���ѵ����3�̡ˡ������ʡ�4�̡ˡ�Ŵ�ݡ�5�̡ˤȤʤä���
���������
����ζ�ͻ���������β���ѹ��Ǿ夲���������� 08��01��
�轵���������������ƹ�������Ͼ徺������DJIA +176.57 @35,459.29, NASDAQ +266.55 @14,316.66, S&P500 +44.82 @4,582.23�ˡ��ɥ�߰��إ졼�Ȥ�141�����Ⱦ���轵��������������߰¿��Ǥ�ư�����ä������������ܳ����̤Ͼ夲������ڥץ饤��Ǥϡ��徺��������1,525���Ф��ơ�������������279�Ȥʤä���ƭ��쥷����106.26%����ڥץ饤�����������5��1035���ߡ�
TOPIX +32 @2,323
����ʿ�� +413�� @33,172��
��Ϣˮ���������������FRB�ˤ��Ż뤹��6����ƸĿ;���ٽС�PCE��ʪ���ؿ��ο��Ӥ��߲���������������夲��³�ؤη�ǰ���¤餮���ƹ�������ϼ���3�����ؿ�·�äƾ夲����
����������Ծ�Ǥ��轵���������ƹ����ȱ߰¡��ɥ���������㤤ͥ����Ÿ���Ȥʤꡢ����ʿ�Ѥϰ��600�߶���Ȥʤä������������㤤����䤷���������Ԥ�����꤬���ͤ��ޤ������������������Ĺû��������YCC�ˤα��Ѥ����ˤ���ȷ��ꤷ��������ľ��ϱ߹⡦�ɥ�¤��礭��ư�������������������θ塢����ο����������ۤϵ��Բǡ����������ﲽ����߽Ф��Ȥ���ư���ǤϤʤ��פȸ�ä����ᡢ�������������ϱ����ϺƤӱ߰¡��ɥ����������ꡢ���ܳ����̤��㤤ľ���줿�������ȼ������������ᤷ�⺮�����礭��ȿȯ����������������ʿ�Ѥ�ǯ������ͤޤǤ⤦�����ΤȤ����ޤ��ᤷ�Ƥ�����ͷٲ������顢����˹⤤�Ȥ����Ǥ������갵�Ϥ���붯���ʤ롣����ˡ����䤬��ͻ����������������ˤϻ��֤���Ĺ�������Ϲ⤤����ư�����ȤϤ��äƤⲼ���뤳�ȤϤʤ��Ϥ��Ǥ��ꡢ���Τ褦�ʷ�ǰ��������Ƭ���ޤ����ȿ仡�Ǥ��롣
����ʿ�Ѥ������㡼�Ȥ�ȡ�����åץ��åפ��ƻϤޤä���Ĺ����Ҥ���û�����Ҥ��������û�����ǽ������������ΤȤ����Ͼ��ͤϽŤ�������������ǤϿ����ְ���˥Х֥��������������@33,510�ߤ��¤֤��Ȥ⤢�ꤦ�롣�����ǰ쵤�˾�����Ǥ���м��γ��⥹�ơ���������롣���������⤷���ޤ������Ƥ��֤����Ȼä��Ϲ������δ��Ԥ���ࡣ
33�ȼ���29�ȼ郎�夲�����徺Ψ�ȥå�5�ϡ���̩�����1�̡ˡ�͢���ѵ����2�̡ˡ�Ŵ�ݡ�3�̡ˡ��ŵ���������4�̡ˡ������5�̡ˤȤʤä���
���������
���ڡ����Υȥåפ�
|
|